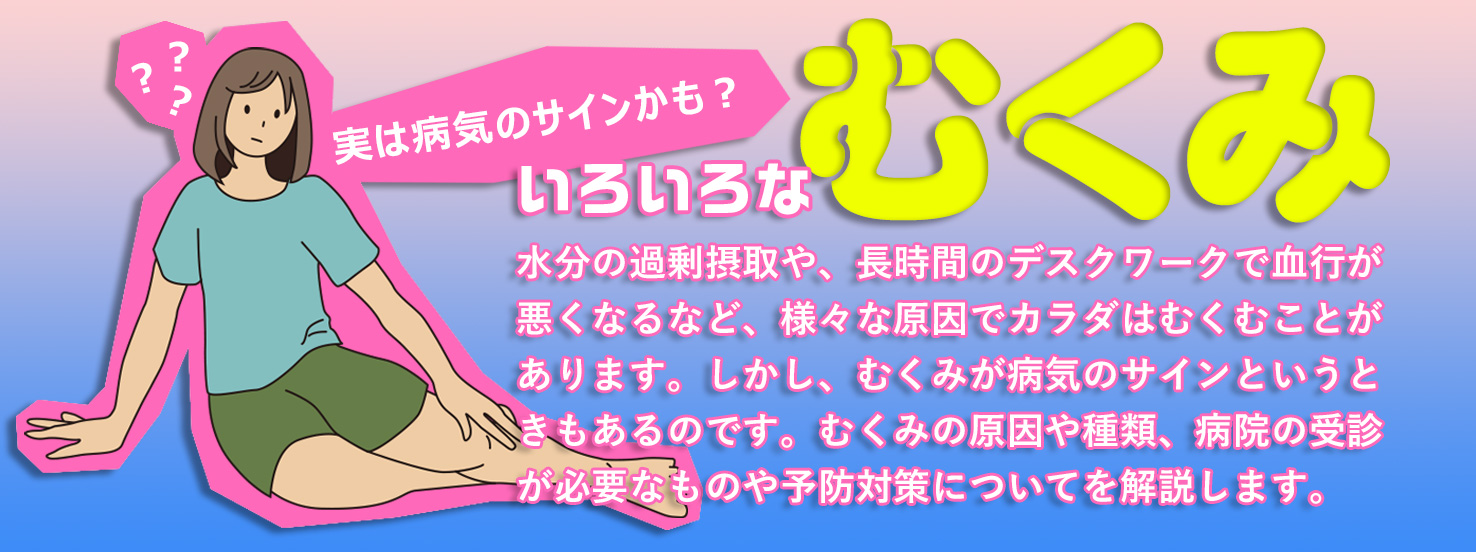2006.11.10
vol.41 腎臓のサインを見逃さない
腎臓の多様な役割

腎臓の役割は?…と聞かれたら、「血液をろ過して、尿をつくること」と答える人が多いでしょう。もちろん、それも大切な役割ですが、腎臓にはあまり知られていない重要な働きがたくさんあります(下記参照)。
<腎臓の主な働き>(※1) 1. 血液中の老廃物をろ過し、尿として排泄
2. 体内の水分と電解質(ナトリウムなど)の調節
3. 血液の酸性・アルカリ性の調節
4. 血圧を調節するホルモン、赤血球をつくるホルモンの分泌
腎臓は尿だけでなく、血液や水分、ホルモンなどを通して、体内環境を全体にわたって調整する役割をしています。それだけに、もし腎臓に異常が起こると、からだのさまざまな部分にいろいろな障害が生じます。
腎臓そのものの病気には、腎炎(腎臓の炎症)、腎結石(
結石ができる)、腎臓がんなどがあります。このうち腎炎は、血液をろ過する腎臓の糸球体に炎症が起こり、ろ過機能が低下する病気です。とくに中高年に多くみられる慢性腎炎は、気付かないうちに進行しやすい腎臓病の代表的なものです。
また最近は、腎臓病が高血圧や糖尿病などの生活習慣病とも、非常に密接な関係にあることが注目されています。
そのため日ごろから、腎臓の状態に気を配る必要がありますが、困ったことに腎臓病はかなり悪化しないと、はっきりした自覚症状がみられません。気が付いたときには、尿毒症を起こしていたり、人工透析を必要とするなど、重症化していることが少なくないのです。
しかし、自覚症状がまったくないわけではありません。
尿の色やからだのむくみ、トイレが近くなったなど、私たちでもチェックできる小さなサインがいくつかあります。腎臓病の予防のために、それらを見逃さないポイントを知っておきましょう。
(※1)腎臓の働きにはこのほか、タンパク質代謝物の排泄や骨をつくるホルモンの分泌などがあります。
腎臓からのサイン 1…尿の色
腎臓からのサインで、最もわかりやすいのが尿の色です。尿の色は、体調によって変わりますが、通常は黄色っぽい澄んだ色をしています(ビタミン剤を飲んだときや疲労時などに、一時的に濃い黄色になることもあります)。
腎臓などに異常があると、尿の色が変わります。
とくに注意したいのは、タンパク尿と血尿です。
<タンパク尿>
腎臓のろ過機能が低下すると、本来は出てこないはずのタンパク質が尿に漏れ出てくることがあります。すると尿の色が濁った感じになり、泡立ちが目立つようになります。
ただし、運動をした後や高熱が出たときにも、一時的にタンパク尿が出ることがあります。
<血尿>
腎臓のろ過機能に障害が起こった場合、赤血球が尿に混じって排出されることがあります。すると褐色のような濃い色味の尿が出ます。膀胱や尿道に出血がある場合は、鮮やかな赤い色が混じることもあります。
血尿というと、腎臓がんを心配する人もあるでしょう。血尿は、急性腎炎などさまざまなケースで起こるので、すぐに腎臓がんと判断することはできません。しかし、腎臓にしこりや痛みなどがある場合は、早めに検査を受けましょう。腎臓は、背中側の腰より少し上の両側にあります。
タンパク尿や血尿は、ふだんから自分の尿を見ていると、変化に気付きます。しかし、もう少し正確に知るには、市販の尿試験紙を利用するといいでしょう。
尿試験紙だと、腎臓の健康状態だけでなく、糖尿病や肝臓病、膀胱炎、尿路感染症など、ほかの病気の可能性についても知ることができます(※2)。もし尿試験紙で異常がみつかったら、自己判断せず、必ず病院を受診して原因を突き止めることが大切です。
(※2)尿試験紙による検査では、比重、pH、タンパク質、ブドウ糖、潜血、白血球、細菌、ビリルビン、ケトン体などを調べることができます。
腎臓からのサイン 2…からだのむくみ
からだのむくみも、腎臓の機能低下を示すサインのひとつです。
まぶたがはれぼったくなる、指輪が入らなくなる、
靴下のゴムの跡がなかなか消えない、靴がきつく感じるようになる…などの症状があったら、むくみが起きている可能性があります。
なんとなく太ったと思っていたら、むくみだったということもあります。
むくみの原因はいくつかありますが、例えばタンパク尿が出ていると、血液中のタンパク質が減り、水分保持機能が低下します。すると血液中の水分が血管の外にしみ出し、これがむくみを起こすことがあります。
とくに血糖値が高い人は、腎臓の機能低下に伴って、むくみの症状がみられやすいので注意しましょう。
腎臓からのサイン 3…トイレが近くなった
中高年になると、トイレが近くなる人が増えます。とくに寒い時期には、飲み物をとるとすぐにトイレに行きたくなったり、短時間のうちに何度もトイレに行くケースもみられます。
あなたは、1日に何回くらいトイレに行きますか。
1日の排尿の回数は人によって、また季節によっても異なりますが、3~10回程度なら正常とされています。10回を超える状態の場合には頻尿を疑って、検査を受けるようにしましょう。
頻尿の原因には、腎臓病のほかに、糖尿病や過活動膀胱などの影響もあります。慢性腎炎や
糖尿病の場合には、尿の量が増え、トイレの回数も多くなります。
また
過活動膀胱というのは、膀胱の柔軟性が低下し、少量の尿でも尿意を感じ、我慢できなくなるものです。飲み物をとるとすぐにトイレに行きたくなったりしますが、尿量が少なく、なかなか出ないこともあります。最近になって知られるようになった病気ですが、中高年にはかなり多くみられます。
高血圧と腎臓
「高血圧は腎臓の病気」といわれるほど、高血圧と腎臓病は密接な関係があります。
腎臓は、血液中の塩分(ナトリウム)を調節する働きをしています。私たちが毎日の食事から大量の塩分をとると、それを処理する腎臓には大きな負担がかかり、腎臓の機能低下を招きやすくなります。
さらに加齢などに伴い腎臓の機能が低下すると、塩分や水分の調整がうまくいかなくなり、その結果、血圧が上昇します。また腎臓は、血圧を調節するホルモンの分泌も担っているため、血圧をコントロールする働きも低下してしまいます。
高血圧になると、腎臓の血管にも負担がかかるため、腎臓の機能がさらに低下し、より血圧を上昇させる要因となります。
こうした
悪循環を起こさないためには、日ごろから血圧の管理をしっかりして、腎臓の機能をできるだけ低下させないようにすることが大切です。
とくに高血圧によって、腎臓の細い血管がダメージを受ける腎硬化症の場合には、タンパク尿や血尿のほかに、頭痛、めまい、吐き気などを伴うこともあります。悪性の場合には、けいれんや意識障害を起こすこともあるので注意が必要です。
すでに血圧が高めの人は、自分でも毎日血圧測定をし、自己管理をしっかり行いましょう。塩分の多い食事を控える、肥満を解消するなど、生活全般にわたって見直すことも大切です(高血圧の改善については、
「生活習慣病基礎知識・高血圧」をご参照ください)。
糖尿病と腎臓
糖尿病を悪化させると、腎臓のろ過機能が低下しますが、最近とくに増えているのが、糖尿病性腎症です。
血液中に糖分が増えすぎると、それを処理する腎臓には大きな負担がかかり、ろ過機能がうまく働かなくなります(糖尿病性腎症)。さらにろ過機能が低下すると、腎不全に陥り、人工透析や腎移植が必要となります。現在、人工透析を受ける原因の第1位は糖尿病で、しかも人工透析患者は毎年1万人もの規模で増え続けています(※3)。
そのため糖尿病性腎症の予防には、血糖値の管理が非常に大切な要因となっています。
糖尿病性腎症になると、アルブミンというタンパク質の一種が尿に出てきます。これは目で見てもわかりませんが、重要な初期症状のひとつです。糖尿病で、血糖値のコントロールがうまくいっていない人、あるいは家族に糖尿病の人がいる場合には、糖尿病性腎症を起こしやすいので、検査を受けるようにしましょう。
さらに症状が進行すると、先ほど紹介したタンパク尿が出るようになります。また、からだのあちらこちらに、むくみがみられるようにもなります。
糖尿病の人はもちろん、血糖値が高めの予備軍であっても、こうしたサインを見逃さず、早めに検査を受けることが大切です(糖尿病の改善については、「
生活習慣病ガイド・糖尿病」をご参照ください)。
(※3)人工透析を導入する原因となる病気は、 1.糖尿病(39%)、2.腎炎(32%)、3.高血圧(8%)、4.不明(8%)、5.その他(13%)となっています(2002年度)。糖尿病は 1998年から原因疾患の第1位となり、糖尿病患者そのものが増加していることから、糖尿病性腎症による人工透析患者の増加も大きな課題となっています。



 腎臓の役割は?…と聞かれたら、「血液をろ過して、尿をつくること」と答える人が多いでしょう。もちろん、それも大切な役割ですが、腎臓にはあまり知られていない重要な働きがたくさんあります(下記参照)。
腎臓の役割は?…と聞かれたら、「血液をろ過して、尿をつくること」と答える人が多いでしょう。もちろん、それも大切な役割ですが、腎臓にはあまり知られていない重要な働きがたくさんあります(下記参照)。