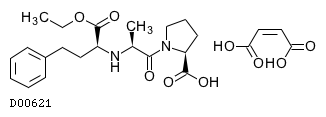内海 聡さんのサイトより
https://note.com/utsuminkoushiki/n/nab4dcfb0c8bd
<転載開始>
① 人間ドック
② 脳ドック
③ 癌検診
④ メタボ検診
⑤ 定期健康診断
これらを五大検診と呼びます。
五大検診は、表向きは国民の健康を守るという建前になっています。
しかし、実情は巨大医療産業の利益を守るために存在します。
五大検診ビジネスは健常人を病人に仕立てて、さらに検査漬け、薬漬け、手術漬けで稼ぐための罠・仕掛けなのです。
人間ドックは日本人だけの奇習です。
人間ドック検診で最も恐ろしいのが、レントゲン検査によるX線被曝です。
定期健診には、病気を防いだり、寿命を延ばす効果はありません。
欧米では、行政も企業も定期健診などしていません。
定期健診は日本だけの奇習です。
日本では労働安全衛生法で雇用主に強制されており、拒否すると処罰されます。
特に怖いのが、胸部X線撮影を国家が強制している事です。
定期とは言えませんがマンモグラフィーの恐怖の検査の代表格です。
https://note.com/utsuminkoushiki/n/nab4dcfb0c8bd
<転載開始>
① 人間ドック
② 脳ドック
③ 癌検診
④ メタボ検診
⑤ 定期健康診断
これらを五大検診と呼びます。
五大検診は、表向きは国民の健康を守るという建前になっています。
しかし、実情は巨大医療産業の利益を守るために存在します。
五大検診ビジネスは健常人を病人に仕立てて、さらに検査漬け、薬漬け、手術漬けで稼ぐための罠・仕掛けなのです。
人間ドックは日本人だけの奇習です。
人間ドック検診で最も恐ろしいのが、レントゲン検査によるX線被曝です。
定期健診には、病気を防いだり、寿命を延ばす効果はありません。
欧米では、行政も企業も定期健診などしていません。
定期健診は日本だけの奇習です。
日本では労働安全衛生法で雇用主に強制されており、拒否すると処罰されます。
特に怖いのが、胸部X線撮影を国家が強制している事です。
定期とは言えませんがマンモグラフィーの恐怖の検査の代表格です。
欧米には人間ドックはありません。
脳ドックもありません。
日本の人間ドックの一日利用コースが約280万人、二日コースだと約25万人。
人間ドックという言葉自体造語で、海外でヒューマンドックといっても通じません。
人間ドックは92%近くが異常と判定されますが、異常の枠を圧倒的に広げることで医療業界が儲かるからです。
そして日本は医療費増大、死人だらけに実際なっています。
人間ドックや検診で使われるものの代表、CT検査。イギリスの研究機関はCT普及率世界一の日本の、CTによる発ガン率は3.2%でイギリスの五倍と発表してます。
CTと並んで人気が高いのがPETですが、CTより線量が高いうえ公式データでも85%の癌を誤診、体内を内部被爆させます。
マンモグラフィーが乳癌を増やし誤診を増やします。
あるアメリカの研究では、マンモグラフィーで癌と診断された女性の殆どは癌ではなかったと報告されています。
定期健診はどうかということこちらも最悪です。
ある研究では肺がん健診の実効性を調べたところ、健診を受けたほうが死亡率が高まりました。
アメリカを含む各国でも同様の大規模調査が行われ、まったく同じような結果が出ました。
ところがこれらの研究の約10年後に日本では、毎年肺がん検診を受けると、肺がんによる死亡率は半分になると、嘘が報道されました。
ところがこの調査はグループ分けさえろくに行っていなかったのです。
OECDデータでは1年間に病院に通う数字が、日本は13.4回でトップ。
福祉先進国と言われるスウェーデンでさえわずか2.8回。
フィンランドの研究では15年かけて行われた調査もあり、健診を受け医者の指導を受けたほうが、死亡、心臓死、自殺すべてにおいて増えました。
こういう調査をどんどん受けて欧米は健診をやらなくなったわけですが、このような職場健診を法律で義務付けられているのは世界で日本だけです。
では、海外ではすべての検診は放棄されているのでしょうか。実はそうでもありません。
やりたい人は自由意思でやることは可能ですが、ここでも統計のトリックがあります。
海外で検診が多いというデータの場合、日本のような法定検診のデータではなく、自主性を含めたデータ、かかりつけ医に頼んで行う非侵襲性的な検診を含めるため、日本と比較できないのです。
日本は病気作りのための検診ですが、欧米の方がまだマシなのです。
つまりたとえば欧米では乳がん検診に類するものをする場合、マンモグラフィーではなく触診が当たり前であり、あとはビタミンDの測定などで危険性を判断し、それを食事や生活指導に結びつけるのです。
これも検診といえば検診ですが、これらを含めてしまうと日本より欧米が検診比率が高い分野もあります。
日本では本質的な予防は決して行いません。
そうすると医療業界や製薬業界、政治家や大企業が衰退してしまうからです。
脳ドックもありません。
日本の人間ドックの一日利用コースが約280万人、二日コースだと約25万人。
人間ドックという言葉自体造語で、海外でヒューマンドックといっても通じません。
人間ドックは92%近くが異常と判定されますが、異常の枠を圧倒的に広げることで医療業界が儲かるからです。
そして日本は医療費増大、死人だらけに実際なっています。
人間ドックや検診で使われるものの代表、CT検査。イギリスの研究機関はCT普及率世界一の日本の、CTによる発ガン率は3.2%でイギリスの五倍と発表してます。
CTと並んで人気が高いのがPETですが、CTより線量が高いうえ公式データでも85%の癌を誤診、体内を内部被爆させます。
マンモグラフィーが乳癌を増やし誤診を増やします。
あるアメリカの研究では、マンモグラフィーで癌と診断された女性の殆どは癌ではなかったと報告されています。
定期健診はどうかということこちらも最悪です。
ある研究では肺がん健診の実効性を調べたところ、健診を受けたほうが死亡率が高まりました。
アメリカを含む各国でも同様の大規模調査が行われ、まったく同じような結果が出ました。
ところがこれらの研究の約10年後に日本では、毎年肺がん検診を受けると、肺がんによる死亡率は半分になると、嘘が報道されました。
ところがこの調査はグループ分けさえろくに行っていなかったのです。
OECDデータでは1年間に病院に通う数字が、日本は13.4回でトップ。
福祉先進国と言われるスウェーデンでさえわずか2.8回。
フィンランドの研究では15年かけて行われた調査もあり、健診を受け医者の指導を受けたほうが、死亡、心臓死、自殺すべてにおいて増えました。
こういう調査をどんどん受けて欧米は健診をやらなくなったわけですが、このような職場健診を法律で義務付けられているのは世界で日本だけです。
では、海外ではすべての検診は放棄されているのでしょうか。実はそうでもありません。
やりたい人は自由意思でやることは可能ですが、ここでも統計のトリックがあります。
海外で検診が多いというデータの場合、日本のような法定検診のデータではなく、自主性を含めたデータ、かかりつけ医に頼んで行う非侵襲性的な検診を含めるため、日本と比較できないのです。
日本は病気作りのための検診ですが、欧米の方がまだマシなのです。
つまりたとえば欧米では乳がん検診に類するものをする場合、マンモグラフィーではなく触診が当たり前であり、あとはビタミンDの測定などで危険性を判断し、それを食事や生活指導に結びつけるのです。
これも検診といえば検診ですが、これらを含めてしまうと日本より欧米が検診比率が高い分野もあります。
日本では本質的な予防は決して行いません。
そうすると医療業界や製薬業界、政治家や大企業が衰退してしまうからです。