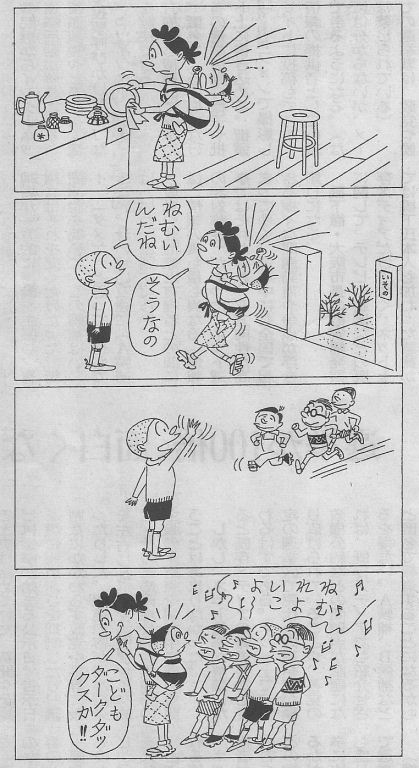勝谷誠彦というのはテレビ画面で一度か二度見たことがあるような無いような、そんな程度の印象しか無いので、その仕事内容は知らないが、確か大病の手術をして、自宅に戻ってすぐに酒を飲んだのが悪くてそのまま死んだとか何かで読んだと思う。
で、そこから、アル中の怖さがネットの話題になっていたと思うが、酒好きの死に方としては理想的なのではないかwww
大伴旅人だったか、中途半端に人であるより、来世では酒甕に生まれ変わりたい、と歌った万葉歌人もいたくらいで、酒好きが酒で死ぬのは本望というものだろう。
ただし、アル中というのは酒の味も何も分からなくなっているのではないか、という気もする。最初は美味くて飲んでいたのだろうが、末期には、酒であれば何でもいい、という、いわば「餓鬼道」に陥っているのをアル中と言うのだと思う。
「白珠の歯に沁みとおる秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり」
と若山牧水が歌った酒の飲み方は、アル中とは程遠いものだろう。
ついでに言えば、長生きが幸福であるなどと私はまったく思わない。50歳以下で死ぬのはさすがに早いとは思うが、60歳くらいまで生きたらだいたい十分ではないか。老化に伴うマイナスを考えたら、70歳くらいで死ぬのが理想的なような気がする。そうすると、70歳定年だと死ぬまで働くことになり、私のようにテレビゲームをしたり漫画を読んだりするのが楽しみで生きている人間にとっては生きた意味も無いように思う。
私は「遊びせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけむ」という梁塵秘抄の唄こそが人生の真実だと思う者である。
偉人の人生も、ある意味、気の毒だな、とすら思う。
(以下引用)
勝谷誠彦氏は肝不全で死去 長生きのために酒量減らす方法
公開日:
コラムニスト・勝谷誠彦氏の死去にビックリした人もいるだろう。1960年12月生まれの57歳。8月に重症アルコール性肝炎で入院し、今月28日に肝不全で死亡した。
勝谷氏は酒好きの上に、うつ病にも悩まされていた。
「とにかく酒が強かった。夕方から飲み始めて深夜1時、2時まで飲むのは当たり前で、一種のアルコール依存症。3年前の5月にうつ病を発症してから引きこもりがちになり、さらに酒量が増えたようです」(担当編集者)
医学博士の米山公啓氏によると、日本酒を毎日3合飲む生活を5年以上続けると、アルコール性障害になる可能性が高まるという。肝臓のアルコール分解機能が低下して重症アルコール肝炎から肝不全で死亡したり、肝硬変から食道静脈瘤破裂や肝がんで死亡するなどいくつかのケースがある。いずれも飲み過ぎが原因だ。

 浅利与一義遠 @hologon15 18時間18時間前
浅利与一義遠 @hologon15 18時間18時間前