[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ふっくらと膨らんだ円錐形の食べ物「甘食」。読み方は「あましょく」となります。その名の通り甘い味が特徴で、洋菓子のマドレーヌに似た味わいや食感があります。表面はしっとりとしていますが、中は触るとポロポロと崩れるような食感です。
甘食は小麦粉や卵、砂糖、重曹、水などから作られ、生地を丸く絞りだしてオーブンで焼きます。重曹を加えることで生地が膨らみ、山のようにぷっくらととがった甘食ならではの形に仕上がるのです。大きさはさまざまで、5センチほどの小さいものから、10センチほどの大きめのものまであります。
甘食が誕生したのは、日本にビスケットやパンなどが輸入されはじめた明治時代だと言われています。甘食発祥には諸説ありますが、中でも有力なのが1894年に東京の「清新堂」というパン屋によって作られたという説です。当時、日本ではヨーロッパの文化が急速に広まり、日本で初めてビスケットが作られたのもこの頃とされています。清新堂で販売されていた「イカリ印のまき甘食」が、甘食の元祖と言われているのです。
他にも、安土桃山時代にポルトガルやスペイン人によってもたらされた南蛮文化の影響を受けているという説もあります。
甘食の名前の由来についても諸説あります。「食事の間に食べる甘い間食」や、「甘いビスケットを大きくしたような食事用のパン」から名付けられたなど、正確にはわかっていないようです。
また、実は甘食はお菓子ではなくパンの仲間だとも言われており、甘食を作っているのはパン屋に多いのも特徴です。甘食の発祥は東京で、全国的にはあまり広まっているとは言えません。関東圏ではどこか懐かしいおやつとして親しまれていますが、西日本では甘食の存在を知らない人が多く見られます。
「オリオン座」は、2つの1等星と5つの2等星を持つ、たいへん豪華な星座。リボンのような形も分かりやすく、最もなじみ深い星座といえるだろう。日本では、雅楽に用いられる鼓(つづみ)に見立てて「鼓星」という呼び方もされていた。
狩人オリオンの腰のあたりに並ぶ三ツ星を挟んで、肩のあたりに輝く赤っぽい1等星はベテルギウス(「わきの下」という意味)、足のあたりに輝く青白い1等星はリゲル(「足」の意味)だ。日本ではこの色の対比を源氏と平氏の旗の色にたとえ、ベテルギウスを平家星、リゲルを源氏星と呼んでいた。最近では、ベテルギウスが近い将来(ただし数百万年以内)に超新星爆発を起こすかもしれないということで注目を集めている。
「オリオン座」のベテルギウスと「おおいぬ座」のシリウス、そして「こいぬ座」のプロキオンを結んでできる三角形を「冬の大三角」と呼び、冬の星座や星を見つける目印になっている。また、リゲルを含む冬の1等星6個をつないでできる大きな形は「冬のダイヤモンド」と呼ばれ、こちらも冬の星座や星を見つける目印になっている。
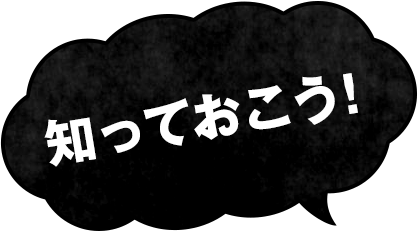
「オリオン座」の三ツ星の下(南)には、「オリオン座大星雲」という星雲がある。宇宙空間に漂うガスやチリが光って見えているもので、空の条件がよければ肉眼でもボンヤリと見ることができる。天体写真では、鳥が羽を広げたような形がとらえられ、人気の撮影対象だ。オリオン座大星雲では新しい星が生み出されており、「星のゆりかご」といった表現をされることもある。
ギリシャ神話では、乱暴者であったために神に遣わされたサソリに刺し殺されてしまう。この一件以来オリオンはサソリを恐れるようになったといわれている。夏の星座である「さそり座」が地平線から上ってくると「オリオン座」が沈み、反対にサソリが沈むとオリオンが上ってくるという、星座の位置関係をうまく表わした神話だ。また、別の神話では月の女神アルテミスの恋人とされている。