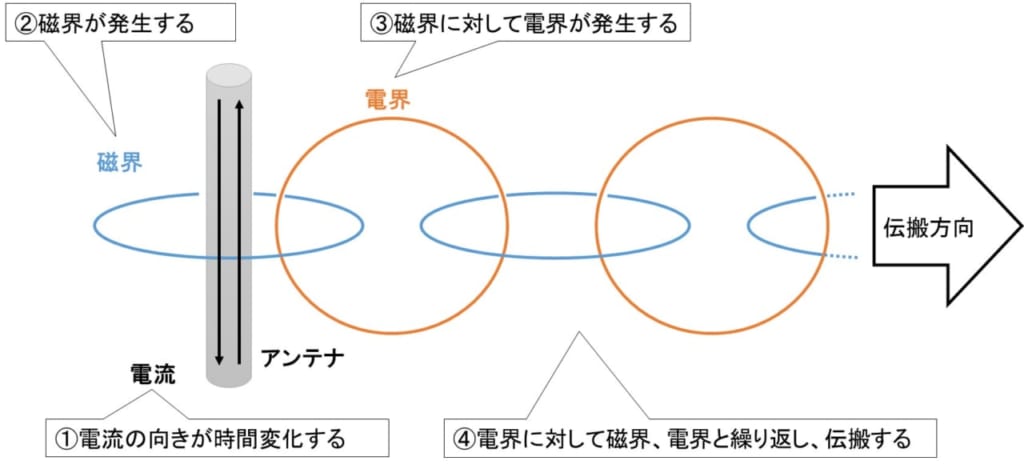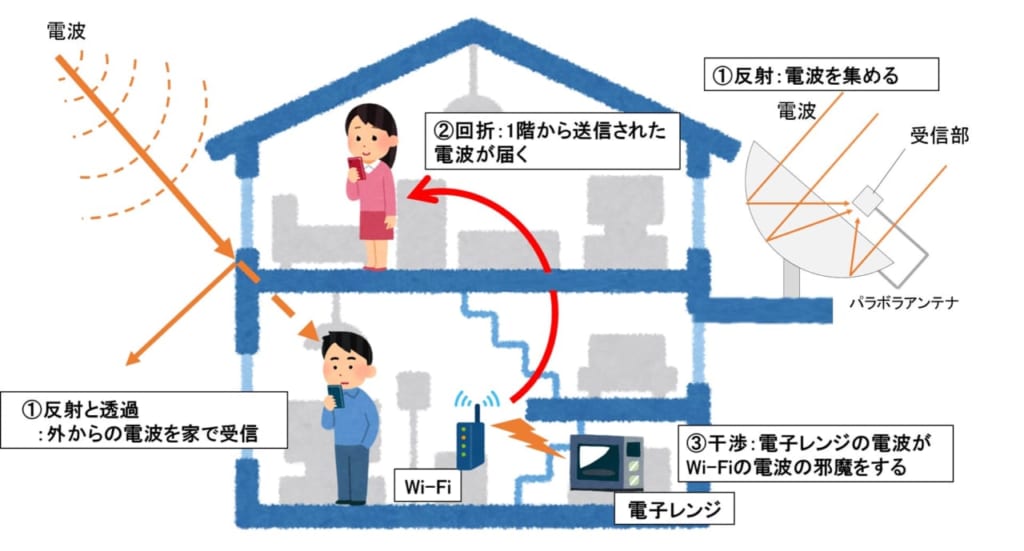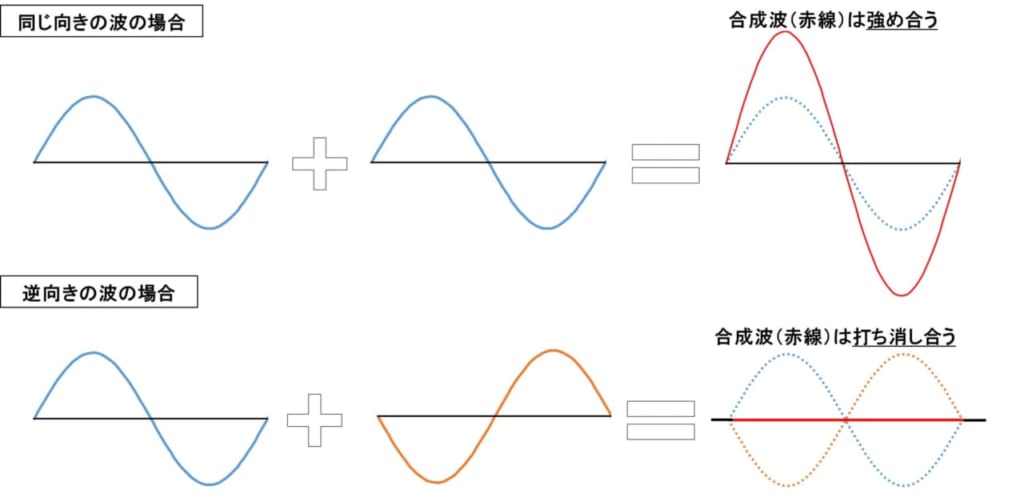1:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:31:55 ID:8Zi
ようやく生活と人間らしい心が取り戻せたように思う
今日もお水が美味い
2:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:32:26 ID:Ne7
お疲れ様
5:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:33:14 ID:8Zi
>>2
ありがとう!
今すごく幸せなんだ
3:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:32:36 ID:8Zi
商社っても専門商社な
その業界では最大手やった
4:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:32:53 ID:PYP
人外になったんか?
6:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:33:59 ID:RcD
測量土木たのちい
10:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:35:16 ID:8Zi
>>6
俺は計測工だよ
作る前の準備段階で動いてるかな
土留め変位計測とかね
7:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:34:22 ID:o2K
なにつくってんの?
8:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:34:52 ID:JHO
平刺き考案してんの?
9:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:35:09 ID:o2K
うそついたの?
11:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:40:10 ID:8Zi
年収→4分の3
実質休日数 100日→120日前後
勤務時間 9:00-18::00→9:00→17:00
残業 みなし20(実質80)→60
12:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:42:02 ID:8Zi
福利厚生と知名度は無くなったけど
営業してた時より毎日のご飯がとても美味しい
13:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:43:41 ID:zgE
マジで何を基準に就活していいかわかんね ちな就活生
18:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:47:52 ID:8Zi
>>13
頑張ってな
まずは大手行くのが良いよ。そこで続けば1番だし
でも、大きくても小さくても続けれるかどうかは入ってみないと分からないからさ
公務員も土方も大手で無理やった時にいったら良いのさ~
14:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:44:28 ID:8Zi
俺結婚してたんだけど、転職するときに離婚したんだ
子供もいて辛かったけど、もうすぐ小学生あがる
生きてて良かったと思う
15:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:44:48 ID:emH
良かったね(*´ω`*)
16:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:46:35 ID:edQ
土留めってドーザか何かで締め固めてないの?
ユンボかなんかで抉りとってるだけなん?
19:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:49:53 ID:8Zi
>>16
今担当してる現場は杭打ってソイルで固めてから掘削してるよー
その杭と切梁に計測器つけてます
20:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:52:38 ID:edQ
>>19
真っ先にアンちゃんがアンカー打ってるのね
アンちゃんがロープ命綱にして打ってるの?それとも機械があるの?
22:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:54:45 ID:8Zi
>>20
杭打ち機か揚重でドーン!だよ
17:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:46:50 ID:LVx
このへんでそろそろホモビの副業でもしようぜ!
21:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:53:37 ID:WN0
もともとそんなブラックでもなさそうやん
23:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:56:27 ID:8Zi
>>21
うーん
医者と薬剤師相手に頭下げて無理難題聞く仕事やったからね…
あと勤務中は全く一息つける時間がなかった
24:風吹けば名無し 2017/06/23(金)21:59:41 ID:R6K
MRか
26:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:01:16 ID:8Zi
>>24
惜しい!MSだったんだなー
MR資格は持ってるけど
28:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:02:12 ID:WN0
>>26
msって何?
モビルスーツしか浮かばないんだけど
32:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:05:55 ID:8Zi
>>28
医薬品卸の営業をMSて言うんだ
MRはメーカーさんの営業
25:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:00:23 ID:8Zi
土方の世界入るときはすごいドキドキしたけど、よくも悪くもすごい人間として扱ってもらってる
たまたまかも知れんけど
27:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:01:25 ID:WN0
mrなんて移動時間待ち時間暇そうやん
31:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:04:46 ID:8Zi
>>27
1日40-50件回って飛び入りの要求と通常業務と社内業務全部こなして定時+1時間で終わらせろ言うんだぜ…
移動時間ギリギリで高速130-140が巡行速度になってた(^o^)
29:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:02:23 ID:WN0
マイクロソフトもあった
30:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:03:41 ID:R6K
営業はどこも大変そうだよね
33:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:07:51 ID:8Zi
MSも待ち時間あるけど全然暇じゃないんだ…
待合室でPC広げたり通話するのが先生に失礼だからしないだけで、急ぎの仕事常にあるんだぜ…
35:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:26:07 ID:WN0
>>33
レス遅れてごめん。
スズケンかな?
相手の医者によってはメンタル大変だと思うよ。
お疲れさまでした。
36:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:31:19 ID:8Zi
>>35
メディセオでした
肉体の疲れより精神の疲れが辛いってのは本当だよ(^o^)
34:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:13:31 ID:8Zi
元嫁はともかく、子供がちゃんと成長してくれてること
俺ももっかい結婚意識できる相手が見つかったこと
仕事が今楽しくて心も身体も健康なこと
色んなことが幸せです
52:風吹けば名無し 2017/06/25(日)07:07:12 ID:Vg3
>>34
ああ、良かったなぁ。
ホント、良かった。
37:風吹けば名無し 2017/06/23(金)22:50:41 ID:G2s
商社勤めの俺仕事はそこそこ楽しい
月曜日からタイいってくるわ
38:風吹けば名無し 2017/06/23(金)23:36:41 ID:8Zi
>>37
いいなぁ
俺もそーいう営業憧れてたけど、向いてなかったぜ!
39:風吹けば名無し 2017/06/23(金)23:47:06 ID:G2s
>>38
商社なのに海外出張なかったの?
俺も向き不向きで言ったら向いてないとおもうぞ英語喋れんし
44:風吹けば名無し 2017/06/24(土)01:15:51 ID:GOo
>>39
医薬品商社は国内しかほぼないで
40:風吹けば名無し 2017/06/23(金)23:51:49 ID:xFp
車何乗ってる
42:風吹けば名無し 2017/06/23(金)23:54:08 ID:G2s
>>40
NX
43:風吹けば名無し 2017/06/23(金)23:54:21 ID:xFp
つまりは土木作業員か?
45:風吹けば名無し 2017/06/24(土)01:16:43 ID:GOo
>>43
そだよん
車はハリアー乗ってたけど嫁に取られた(^o^)
46:風吹けば名無し 2017/06/24(土)21:37:30 ID:RMT
俺はMRだけどこの仕事やってらんねぇよな
虚無感すげぇわ
47:風吹けば名無し 2017/06/25(日)02:43:40 ID:23E
専門商社でおすすめの業界ある?
48:風吹けば名無し 2017/06/25(日)02:45:10 ID:1ZC
>>47
型枠大工、鳶、土木作業員
49:風吹けば名無し 2017/06/25(日)02:48:49 ID:23E
食品卸とかどうなんかな?
50:風吹けば名無し 2017/06/25(日)02:50:01 ID:rQO
ドカタはドカタでも技術職か
乙
51:風吹けば名無し 2017/06/25(日)06:50:57 ID:FDh
リアルサラリーマン君だな
53:風吹けば名無し 2017/06/25(日)07:19:32 ID:D6G
来週一級土木の試験があることを思い出した
勉強しなくちゃ