[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
皇太子時代の昨年7月、研究者の一人として講演する天皇陛下=東京大学伊藤国際学術研究センターで(陽明文庫HPより) |
 |
天皇陛下は、平安時代以降の貴族の乗り物「牛車(ぎっしゃ)」に関する論文を、即位前に出版された刊行物に寄稿されていた。学習院大学史料館客員研究員として二十年以上にわたる研究成果の一つで、研究を通じて交流のあった専門家の証言などから、一次史料に誠実に向き合う学者・天皇の素顔が浮かび上がってきた。 (編集委員・吉原康和)
二〇一八年七月十五日、東京大学(東京都文京区)のホールに、皇太子時代の天皇陛下の姿があった。
日本学術振興会の科学研究費による財団法人「陽明文庫」設立八十周年記念特別研究集会で、陛下は「陽明文庫に残された三点の牛車絵図」と題して約三十分間、講演した。
|
一次史料に向き合う天皇陛下が講演で取り上げた、代表的な牛車絵図の一つ=陽明文庫蔵 |
 |
陛下は「天皇は牛車に乗ることはなかった」とし、その理由について、車を引く牛が暴走する光景が描かれている中世の絵巻物を紹介。「牛車は安全な乗り物ではなかった」と指摘した。この講演は学習院大学史料館客員研究員の木村真美子さんとの共同研究の集大成で、平成の最後に出版された『陽明文庫 近衛(このえ)家伝来の至宝』(吉川弘文館)に論文として収められている。
宮内庁によると、陛下は講演の日の朝、側近を通じて出席者分の講演用レジュメを会場に届けた。側近は「この日の研究発表に限らず、陛下は前日ぎりぎりまで発表の準備をなされている」と話している。また、集会終了後の情報交換会にも出席。滞在時間は「異例中の異例」(側近)の八時間に及び、情報交換会では参加者約六十人の一人一人と和やかに交流した。
集会で報告者の一人として参加した国立歴史民俗博物館准教授の小倉慈司(しげじ)氏(古代史)は「陛下の牛車絵図研究は数十点にも及ぶ写本調査の上に築かれたもので、そのなかには研究によって史料的価値が明らかとなり、国の重要文化財(重文)指定に結びついた史料がある。史料研究は地味ながら、さまざまな研究の基盤となるものであり、陛下の研究もまた、今後、長く評価、参照され続けることになるのではないか」と話している。
|
徳仁親王名の講演用レジュメなどの資料 |
 |
昨年末刊行された『御料車と華族の愛車』(霞会館、非売品)所収の論文「前近代の『御料車』」で陛下は牛車との出合いについて初めて言及。「車は、自分を短時間で遠いところへ連れて行ってくれる有り難い存在であった。一方で、子供時代の私は、街を自由に歩きたくても、車があるためにそれができないうらめしさを、少しばかり車に対して抱いていたことも確かである」と述べている。
陛下は皇太子時代、研究のための体験として、宮内庁京都事務所に保管中の牛車に計三回乗車。二〇〇七年の初乗車では、学習院大学史料館の「ミュージアム・レター」(同年九月十五日)に「車輪の回転に伴い、キーキーという独特な摩擦音があたりに響く。平安の都は、日夜このような牛車の音に満ちていたのだろうか。ゆるやかな時の流れに身をゆだねながら、しばし、当時にタイムスリップしたような感覚にとらわれた」と体験記を寄せた。
|
天皇陛下が研究の一環として乗車体験された牛車=宮内庁京都事務所提供 |
 |
水問題の専門家として知られる陛下が牛車研究に本格的に取り組むようになったのは、一九九六年に学習院大史料館に寄託され、車絵が大量に収められた西園寺(さいおんじ)家文書の調査を始めてからだ。側近を通じて愛知県西尾市岩瀬文庫に所蔵されていた江戸時代の「車之図」の複写史料を取り寄せるなど、牛車絵図の写本調査や乗車体験を行い、研究を深めてきた。
学習院大学で共に中世史を専攻した学友の乃万暢敏(のまのぶとし)さん(60)は「陛下の研究姿勢は極めて緻密で実証主義に基づいている。学生時代に培ったフィールドワークを大切にされる研究姿勢も感じる」と語った。
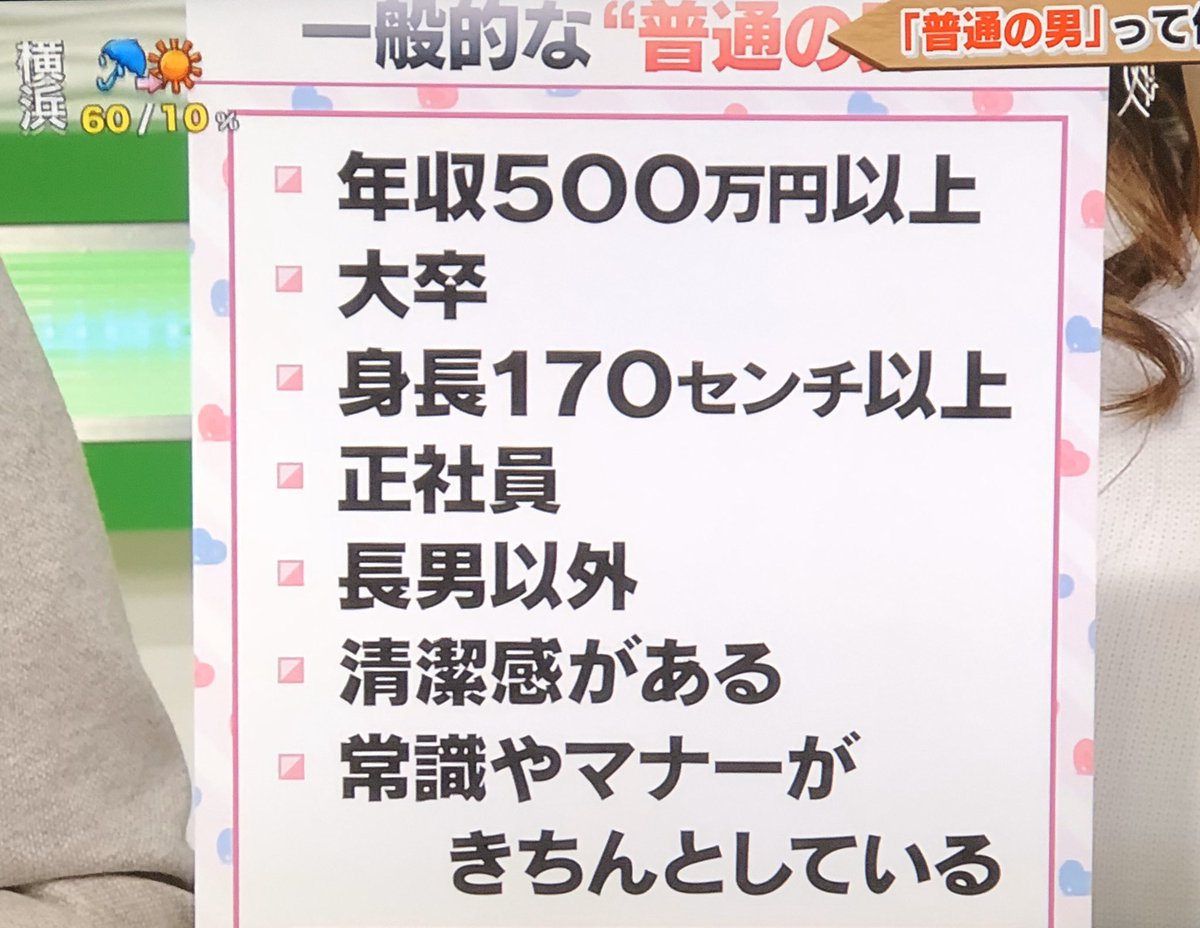
英語の weak flour とか,strong flour の訳じゃないでしょうか。
次のYahoo!辞書の6の項とか
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=WEAK&dtype=1&stype=0&...
何故英語で weak を使うのかとか,最初に翻訳した時,弱でなく薄を選んだのか,その辺は
不明ですが。