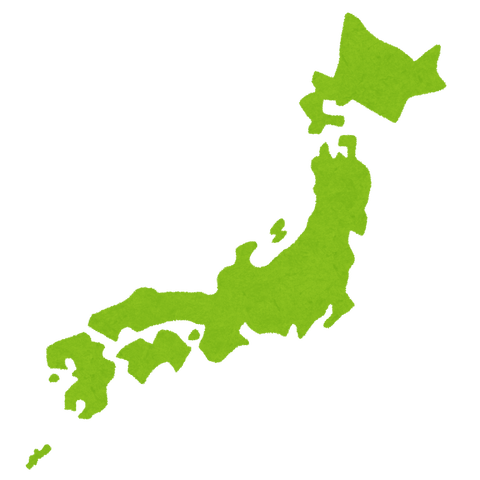1:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:27:25 ID: ID:WWQ
大陸との往来が盛んな九州が最も栄えていた
小国が乱立していて連合政権は成立していなかった
朝鮮半島南部とは一体の勢力圏だった
2:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:28:29 ID: ID:sa9
3:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:29:23 ID: ID:WWQ
九州北部の奴国が大陸との関わりを深める
まだ連合政権は出来上がっていない
4:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:29:59 ID: ID:Tuu
7:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:32:35 ID: ID:WWQ
中国の史書は考慮に入れたけど
所詮は素人の妄想やで
8:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:33:53 ID: ID:Tuu
なんや三国志や後漢書あたりは普通に読んでそうやな
寝落ちするまで見とるで
11:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:35:35 ID: ID:WWQ
サンガツ
5:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:30:32 ID: ID:vsu
6:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:31:17 ID: ID:WWQ
九州北部の小国の中から伊都国が台頭して奴国などを支配下に置く
北九州に当時の日本列島では最も先進的な連合政権が成立する
10:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:35:14 ID: ID:WWQ
伊都国王の帥升は倭国(北九州の連合政権)の王でもあった
彼が奴隷を後漢に献上した
奴隷は伊都国の支配に反抗した小国の人間と思われる
当時の倭国は後の倭国とは性質が異なるため、仮に初期倭国と呼ぶ
12:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:36:02 ID: ID:VhX
13:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:36:31 ID: ID:trr
古代日本は大陸と繋がりがあってロマンあるンゴねえ
15:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:37:35 ID: ID:WWQ
伊都国中心の初期倭国の政権は1世紀後半から100年弱続いたが、この時期に多数の小国が反乱を起こして支配が乱れる
いわゆる倭国大乱である
16:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:37:58 ID: ID:trr
18:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:43:31 ID: ID:Tuu
ヒミコの他にヒミココなる者がいる事実
17:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:42:37 ID: ID:WWQ
この時期までには吉備・出雲・大和にもある程度の規模の連合政権が成立していた
倭国大乱のさなか、日向の小国を支配する豪族(かつては初期倭国の構成員)は東に逃れ吉備政権と同盟を結ぶ
20:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:44:11 ID: ID:trr
仮想戦記みたいですこ
21:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:46:31 ID: ID:WWQ
吉備政権と同盟を結んだ日向の豪族は大和に入り、唐古・鍵遺跡を中心とする旧大和政権を支配下に置く
新たに纒向遺跡を中心とした新大和政権を造り上げる
ここに畿内~吉備の大規模政権が誕生する
22:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:50:44 ID: ID:VhX
23:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:54:18 ID: ID:jl1
なるほど
24:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)00:54:36 ID: ID:WWQ
大和吉備連合政権は今度は西に向かいかつての宗主国・伊都国を支配下に置く
伊都国の監視とそれより北の壱岐、対馬、朝鮮南部の検察のために伊都国に一大率が置かれる
しかし肥後の狗奴国は連合政権に対抗姿勢を見せて九州は北部のみの支配となる
この時点での連合政権の支配域は畿内~瀬戸内~北九州~朝鮮半島南部
出雲政権は少なくとも積極的に連合政権に協力することは無かった
25:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:02:11 ID: ID:WWQ
旧日向豪族の卑弥呼(記紀のヤマトトトヒモモソヒメ)が連合政権の女王として擁立される
親魏倭王の金印を給る
弟の崇神天皇が実務を支えた
事実上の初代天皇とも言える
依然として狗奴国の抵抗は続くが、卑弥呼が亡くなってしまう
26:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:06:05 ID: ID:jl1
33:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:14:55 ID: ID:WWQ
ない
ただ倭国大乱中に東征して大和政権を創始した人物がいたと仮定すると、それは崇神天皇だと思う
神武天皇も崇神天皇もハツクニシラススメラミコトなので
神武=崇神
34:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:17:47 ID: ID:jl1
なるほど
欠史八代を考慮したらそれは有力
27:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:09:31 ID: ID:pO5
28:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:10:35 ID: ID:WWQ
卑弥呼の死後は吉備政権の男王が立てられるが連合政権側の中でも反乱が起きる
そこで卑弥呼の親族の台与(記紀のトヨスキイリヒメ)が女王に立てられた
台与の支配下の連合政権が狗奴国を倒して政権は一応の安定を得る
30:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:12:02 ID: ID:pO5
管理人※
卑弥呼色とはなんぞや・・・(´・ω・`)
35:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:17:54 ID: ID:jl1
36:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:23:18 ID: ID:WWQ
台与と出雲政権の王族が婚姻関係を結び出雲が連合政権に組み込まれる
大和政権は吉備と同盟関係で既に日本列島最有力なので出雲政権が従う形
ただし旧出雲勢力は暫くは有力であり続けた
またこの時期には東海や北陸へも進出して行った
37:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:30:13 ID: ID:WWQ
引き続き東征が行われると共に朝鮮半島への出兵も行われる
既に加耶地域は支配下であったが、百済、新羅も下して朝貢させることに成功する
ただし実効支配にまでは至らない
38:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:31:28 ID: ID:WWQ
39:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:32:09 ID: ID:jl1
41:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:37:20 ID: ID:WWQ
もうちょい後かな
43:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:40:34 ID: ID:jl1
了解やで
40:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:36:56 ID: ID:WWQ
一度目の王朝交代が起きる
大和王朝は度重なる征服事業の疲弊により求心力が低下する
その期に河内の豪族が王権を奪取する(応神天皇)
政権の中心地が大和の三輪から河内に移る
42:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:40:12 ID: ID:WWQ
河内政権が朝鮮出兵で高句麗を攻める
高句麗は以前の大和三輪政権は手出しできなかった強国だった
敗北を喫するも政権は揺らがなかった
44:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:42:10 ID: ID:pO5
これが広開土王のやつか?
46:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:43:46 ID: ID:WWQ
せや
45:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:43:27 ID: ID:WWQ
この頃には王権の支配は関東にまで及んでいた
倭の五王(河内王権の王で連合政権の王でもある)が次々と南朝の宋に朝貢していた時代
政権は比較的安定していた
47:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:44:37 ID: ID:jl1
49:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:48:43 ID: ID:WWQ
誉田御廟山もやな
あの辺りの時代にそれまでより巨大化した古墳が河内に造られるようになるから、王権交代があったと思う
52:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:50:25 ID: ID:jl1
そう考えると符合するな
48:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:47:18 ID: ID:WWQ
雄略天皇の治世
埼玉稲荷山古墳からワカタケルと刻まれた鉄剣が出土し、熊本江田船山古墳からも同様の鉄刀が出土しているため、考古学的に実在が確実な最初の天皇
50:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:49:38 ID: ID:J1w
51:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:49:51 ID: ID:WWQ
河内王権の安定的な支配の時代
特記事項は無し
53:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:56:38 ID: ID:WWQ
二度目の王朝交代の時代
武烈天皇の時代に河内王権で内紛が起きて支配力が低下
有力豪族の大伴金村らが越前の有力豪族を擁立(継体天皇)
この継体天皇の系統が現在の天皇家へと続く(途中で天武朝に乗っ取られるが光仁朝で復活)
54:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)01:57:52 ID: ID:WWQ
55:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)02:00:34 ID: ID:WWQ
56:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)02:03:41 ID: ID:jl1
それなりに練られてて面白かったで
58:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)02:06:56 ID: ID:Rw3
良スレ見れてえかったわ
59:名無しの歴史部員 2018/10/13(土)02:08:52 ID: ID:pO5
やっぱ古代史はロマンがあってええな