 茄子の煮浸しと、キュウリの酢の物。夏の定番です。茄子は半割りにしてフライパンで焼いて、タレに漬ける。タレは出汁、醤油、みりん。生姜すりおろしとネギと鰹節トッピング。キュウリは薄切りにして、タレに漬ける。タレは煮浸しのタレにお酢を加えたもの。乾燥ワカメも入ってます。 |
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 茄子の煮浸しと、キュウリの酢の物。夏の定番です。茄子は半割りにしてフライパンで焼いて、タレに漬ける。タレは出汁、醤油、みりん。生姜すりおろしとネギと鰹節トッピング。キュウリは薄切りにして、タレに漬ける。タレは煮浸しのタレにお酢を加えたもの。乾燥ワカメも入ってます。 |
目次




元慶応大学の“強姦コンビ”による犯行がまた、発覚した。
昨年3月、同じ女性に別々に暴行を加えたとして、埼玉県警大宮署は11月21日、渡辺陽太(ようた)容疑者(24)と光山(こうやま)和希容疑者(24)を強制性交の疑いで逮捕。
「2人は深夜、JR大宮駅付近で20代女性に声をかけてカラオケ店に入った。そこでまず渡辺が強姦し、その後、光山が女性の腕を引っ張ってインターネットカフェへ連れ込み、レイプした」(テレビ局記者)
容疑者らは調べに対し当初、「弁護士が来るまで何も話さない」と無言を貫いていた。
慶応義塾大学時代からの友人である2人は、過去にも同様の事件で逮捕されている。
「2018年11月、2人は酒に酔わせた女性にわいせつ行為をしたあげくに財布を盗み、逮捕されています。
それだけではなく、渡辺容疑者は同年9月にも、路上で見つけた泥酔状態の女子大生を凌辱したうえ、女性の腹を蹴って現行犯逮捕。本人に犯行の意識はなく、なぜ逮捕されたか理解できていなかったそう」(前出・テレビ局記者)
今回の事件で渡辺容疑者は少なくとも6回、光山容疑者は2回目の逮捕となった。
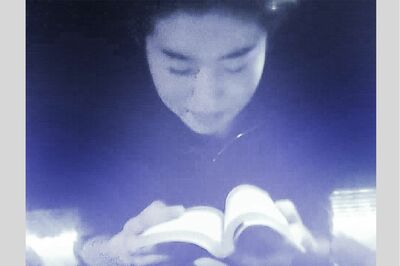
渡辺容疑者は在学中の2016年、「ミスター慶応」コンテストでファイナリストまで残ったほどのイケメン。実家は千葉県で土建業を営む大富豪で、当時は元麻布にある家賃100万円ほどの高級マンションに住んでいた。
「実家の子会社で社長に就任し、何もしなくても多額の金が入っていた。昔から素行が悪く、高校は3か月で退学。その後、留学したスイスでも女性問題を起こした。
2年前の逮捕では被害者の告発が噴出し、身体の関係を拒んだ女性が暴力をふるわれたといった話が大量に報じられた。泥酔する女性に放尿する動画も公開していた」(同)
これだけ卑劣な行いをしてきた容疑者らだが、
「昨年1月にはいずれの容疑も不起訴となっています。理由は明らかにされていませんが、裕福な渡辺容疑者の実家が、被害者に対し莫大な示談金を支払ったのではないかと考えられます」(司法担当記者)
今回の事件は不起訴が決まった2か月後の犯行。反省の色はまったく見えないが、最近はどうしていたのか。
無職となった渡辺容疑者は、千葉県にある父親の経営する会社の社員寮で暮らしていた。近隣住民が1か月くらい前に目撃した意外な姿とは──。
さらに光山容疑者の母と渡辺容疑者の祖父に話を聞き、“強姦コンビ”が犯行を繰り返す理由に迫った『ミスター慶応“強姦コンビ”がまた逮捕、全く反省せず卑劣な犯行を繰り返すワケ〈容疑者の母は「示談金狙い」「騙されたとしか思えない!」と擁護〉』を、12月4日、6時配信のYahoo!ニュース有料記事にて【全文公開】する。
| 院号居士 院号大姉 |
居士 大姉 |
信士 信女 |
|
| 本寿院 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
| A社 | 15万円 | 5万円 | 2万円 |
| B社 | 20万円 | 6万円 | 2万円 |
| C社 | 20万円 | 6万円 | 2万円 |
| D寺 | 25万円 | 15万円 | 8万円 |
Q10 ワクチンは本当に効いているのか? A ファイザー社ワクチンが世界でもっとも多く使われています。効果が高く、副作用も少ないと説明されていますが、本当でしょうか? 有効性を示す唯一の根拠とされているのが、昨年12月31日に発表された1編の論文でした。そこで示された「有効率95パーセント」との情報が世界を駆け巡り、ワクチンを推進する人たちのバイブルとなっています。この論文を掲載した専門誌も、よほど自慢らしく、会員となっている私の手元にも、繰り返し「掲載のお知らせ」が届きます。しかし、この論文には数々の疑惑があります。 疑惑その1 疑惑その2 疑惑その3 さて、このややこしい話はどう理解すればよいのでしょうか? なぜ執筆者らはわざと低い値を報告したのでしょうか?もう、おわかりだと思います。「ワクチンは2回打たないと効果がない」という話にしたかったのです。そうでなければ、会社の売り上げが半分に・・・? 疑惑その4 途中で脱落していく人が多ければ、グループ間に偏りが生じるなど、調査結果の信頼性を著しく損ねることになります。実際、ずさんな調査ほど脱落者が多いことは、歴史が示しています。「副作用がきつくて嫌になった」などは、脱落理由の定番として知られています。 今日現在、判明している疑惑は以上です。この論文の掲載を決めた編集長エリック・J・ルービン氏(ハーバード大学非常勤教授)は、「全人類」の未来永劫にわたる健康被害(?)に対する責任を負ったことになりますが、どのように考えているのか、聞いてみたい気がします。 南スーダンに派遣された自衛隊を取材、政府の隠ぺい体質を告発した、布施祐仁・三浦英之著『日報隠蔽』(集英社)という優れた報道ノンフィクションがあります。その帯に書かれていた言葉を最後に引用させていただきます。 「結局、すべてがウソなんじゃないか」 |
||
どの国の首相も政府もどうしてこんなに横並びに徹底して従う意味がこれですな。 まずもって従わなければどうなるか暗に脅迫され分かり切っているからでしょう。 菅がいつもビクビク怯え切って発言する意味もこれでしょう。 逆に媚び打った言動ではしゃぎすぎてるのが河野。 どうあれ未来的に凶悪犯罪の罪で裁かれ尻尾切りされる運命なのが常ですが。 |
||
311は麻生の仕業ww |
||
今起きていることは、 戦争だという認識を持たないと、 特に、国のトップにいる人間は、 敵対する相手に簡単に首を取られてしまうんだよ。 今回の戦争は、従来型の国と国との戦争ではない。 宇宙的観点で言うと、悪対正義、悪魔対天使、 この現実的な地上的観点で言えば、 世界制覇を狙う邪悪なビルゲイツら支配層対人類 という構図だ。 奴らは、今回生物兵器を仕掛けてきて、 試みている訳だ。 こういう認識が、ハイチの大統領らにあれば、 易々と奴らに殺されないんだよ。 先ずは、スパイ的人間を排除したり、 それから、各国の味方の政治家連携する。 例えば、プーチン、トランプだ。 彼らは、完全に正義の側にいることが分かる。 彼らと連携すれば、簡単にはやられない。 特にプーチンは超強力な味方だ。 シリアのアサドを見たら分かる。 何回も暗殺されてもおかしくない人間だ。 ということで、軍を味方につけたトランプが、 先ずは米国で奴らをとっ捕まえて、 処分して欲しいものだね。 |
||
|
||
|
||
力あるものが正義____ 力あるものが正義を振りかざし、嘘まみれのプロパガンダで洗脳し、略奪と殺戮を繰り返してきた ○「ニュースは流すものではなく、造るものだ。」 ~メディアはカダフィ体制の崩壊を「独裁の終焉」と報道し、戦争行為を肯定した。しかしリビアでは新婚世帯に約5万ドルの住宅購入補助金を支給、失業者には公共住宅を提供、車購入の際には補助金50%を支給し、全てのローンは無利子、さらには所得税などもゼロだった。水道や電気、医療費は無償なうえに、国内で必要な治療が受けられない場合は外国での治療費と渡航費までもが援助されるシステムだ。カダフィは特に教育政策に力を注ぎ、初等教育から高等教育、さらには大学まで全てを無償化した。対し米国では4700万人が医療保険に未加入であり、350万人が路上生活を強いられ、大学生の70%以上が2万5000ドル平均の学資ローンを抱え苦しんでいる。 緑の革命を掲げ、人類史上例を見ないほどの福祉国家を作り上げたカダフィ大佐。 一方、自由と民主主義を掲げる西側諸国は、アラブの春を演出後、自作自演の911を理由にイラクを始めとしたアラブ諸国へ武力侵略。イラクでは、大量殺戮と同時に何世代にも健康被害を及ぼす劣化ウラン弾を投下。真のねらいは傀儡政権の擁立による国家資源の半永久的な略奪であり、前世紀と同様の植民地化のための侵略戦争だったのである。 >リビア、カダフィ大佐の死亡、彼の業績に関する追悼のツイート 10523字 >カダフィーの真実~理想社会を創った英雄 |