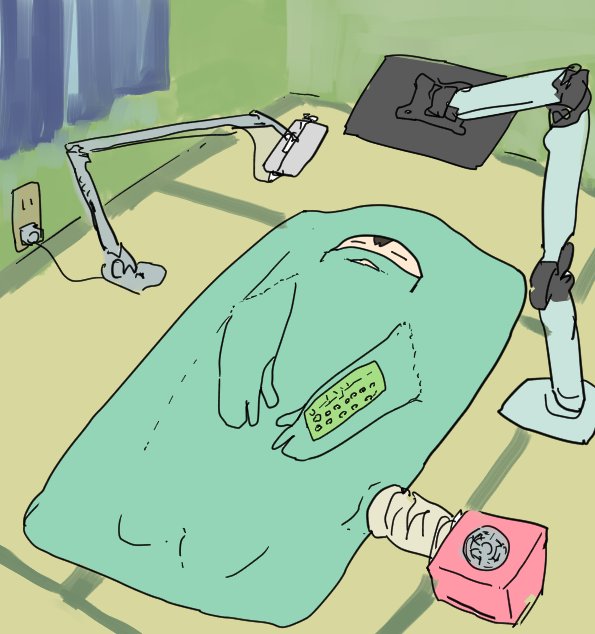毎日ビールを飲めば90歳まで生きる確率が高くなることが判明。オランダのマーストリヒト大学病院がこの新しい研究結果を学術誌「Ages and Ageing」に寄稿しています。
マーストリヒト大学病院の研究チームは、1916〜1917年生まれの男女5,479人を対象に追跡調査を実施。
被験者に飲酒習慣を尋ねた上で、どれだけの人が90歳まで長生きするかをモニタリングしたのでした。
するとビールを毎日約240ml(アルコール摂取量5〜10g)飲む男性は、非飲酒者に比べて、81%も高い確率で90代まで生きることが判明。女性も30%近くに同じような結果が出ています。
<海外の反応>
誰が240ml程度のビールで満足するよ!?
ビール1杯飲めば2杯目を飲みだすのは自然の摂理、宇宙の法則なんだが
一杯ってこれぐらいでいいんけ?
オレが毎日4リットル飲んで100歳超えたるわwww
せめて缶ビール10本はいるわ
900歳まで生きるからまぁ見ててくれ
アルコールなんかよりもストレスの方が死を早めるよ
タバコ好きの100歳超えとかもいっぱいいるし、この手の研究は信じないわ
「アルコール摂取と長寿に関連があることが分かりました」と話すのは、Piet A van den Brandt教授。
少し嗜む程度であれば健康に良いものの、一方で多くのアルコールを摂取した場合(15g〜)は、むしろ早死に繋がると言います。
<海外の反応>
以上、ビール会社の提供でお送りしました(笑)
飲んで90まで生きれるかは知らんが、スカートを履き出す確率は3倍になるよ
嗜む程度しか飲んでないワイ大勝利
酒に酔ってると死ぬ気がしない
チビチビ飲んで長生きするのと豪快に飲んで早く死ぬのとどちらがいいかは明白だ
ようこそアル中の世界へ!!
お酒飲まない私はどうなるの\(^o^)/