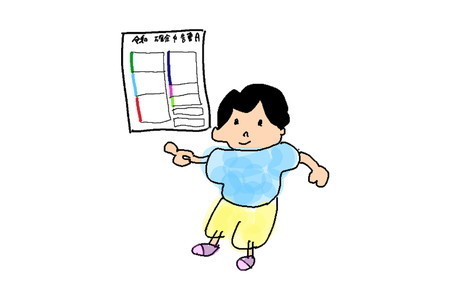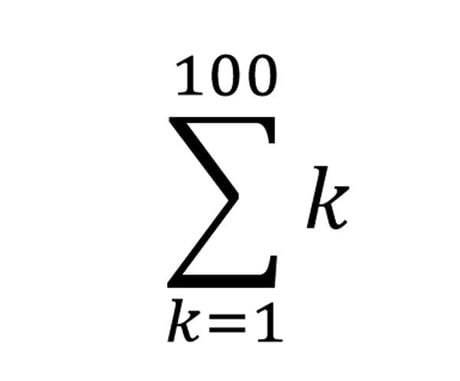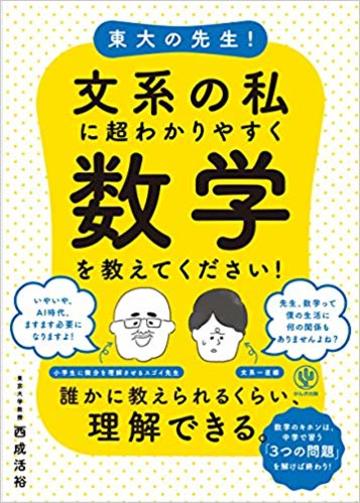元国税局職員 さんきゅう倉田です。好きな加算税は「重加算税」です。
例年なら、確定申告期間が折り返したくらいの時期ですが、今年は延長されています。4月になってから申告するという方もいるでしょう。でも、ぎりぎりになって税や確定申告について調べても理解できないかもしれません。 普段から、少しずつ学んでいただくと良いと思います。
確定申告に関する用語解説
確定申告の本やサイトを見ていると、収入や所得、控除、所得税などよくわからない単語が登場します。用語の説明が添えられている場合もありますが、その説明すら難しい。主要な用語を確定申告書に登場する順番で見ると
【1】収入ー給与所得控除or経費=所得【2】所得ー控除=課税される所得金額【3】課税される所得金額×税率=所得税の額【4】所得税の額ー源泉徴収税額=納める税金or還付される税金
このような関係になります。
収入について
「収入」は、「年収」「売上」と同義ですね。10種類ある所得ごとに分けて収入を計算し、そこから「経費」を引いたのが「所得」です。
そこで、会社員やパート・アルバイトは経費が認められません。でも、仕事に関する個人的な支払いがありますよね。例えば、スーツやカバンの購入、資格の取得にあたって、お金を使うことがあると思います。そのため、「給与所得控除」が用意されています。
控除について
「控除」は収入から引けるものなので、給与所得控除はあなたの納税額を減らしてくれます。この金額は、経費のようにレシートを集めて計算するのではなく、あなたの年収によって決定されます。
「所得」からは、様々な控除を引くことができます。医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの控除はみなさんも知っているかと思います。
社会保険料とは、年金や健康保険のことで、1年間に支払った金額を所得から控除できます。会社員に許された数少ない節税である「ふるさと納税」も寄附金控除で所得から引くことができます。
所得税について
確定申告では「課税される所得金額」に所得税率をかけて、所得税を計算します。所得税は累進課税になっています。中学か高校の授業で習った気がするので、みなさん、なんとなくご存知でしょうか。
所得が高くなればなるほど、税率が高くなっていく制度です。昔、テレビで芸人さんが「どんだけ稼いでも半分持っていかれる。やってられへん」とおっしゃっていました。現在の所得税の最高税率は45%、ここに10%の住民税が加わって負担は55%になります。大体半分ですね。なお、一番低い税率は5%です。
「課税される所得金額」に税率をかけて計算した所得税から源泉徴収税額を引いて、確定申告によって納める所得税が決まります。
源泉徴収税額のほうが多ければ、所得税は還付になります。会社員の方は、医療費控除や住宅ローン控除などがあると、源泉徴収税額の方が多くなって、還付になります。還付する確定申告を「還付申告」といいます。
ただし、会社からもらう給料以外に収入があれば、納税になることもあります。
源泉徴収について
「源泉徴収」についても説明しておきましょう。
日本のルールでは、自分の収入や所得税を自分で国に伝えなければいけません。でも、働いている数千万人の人全員が確定申告をするとなったら、税務署はパンクします。会社員全員に確定申告の方法を学ばせるのも、効率的でない。 簡易な方法で税金が徴収できたら良いですよね。 源泉徴収は、毎月のお給料から所得税を天引きする制度です。勤務先の会社がみなさんの代わりに計算してくれてるので、みなさんはとっても楽です。
でも、毎月ちょっと多めに天引きしているんです。だから、年末になったらより正確に計算して、多く集めた源泉所得税を還付します。これが「年末調整」です。みなさん年末調整が大好きですよね。
確定申告に関する用語、少しでもご理解いただけたでしょうか。
源泉徴収と年末調整によって、多くの会社員・パート・アルバイトは確定申告が不要となっています。ただし、勤務先の年末調整では対応できない何かがあれば、例えば、医療費控除や副業収入があるような場合ですが、確定申告が必要となります。