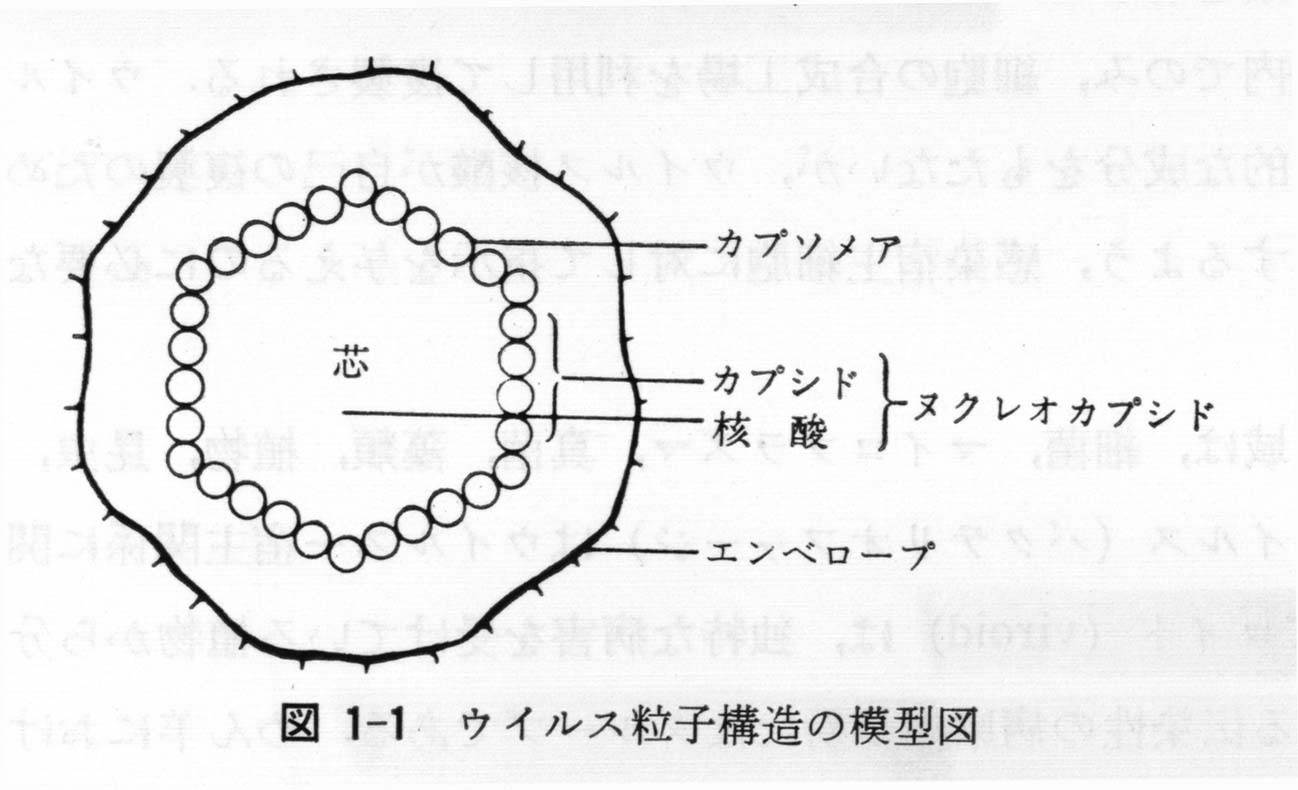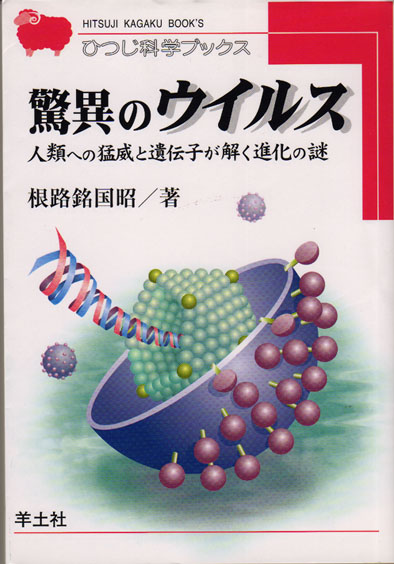20世紀初頭は欧米大衆小説の黄金時代だったと私は思っているが、そのころの小説を読むとよく出て来るのが「鼻眼鏡」である。これがなかなかイメージしにくい。鼻に載せる(掛ける)だけの眼鏡なら、すぐに滑り落ちるだろう、というのは、こちらが鼻の低いアジア顔だからだろうが、西洋人なら大丈夫だとも思えないわけだ。
(以下引用)
眼鏡が発明された当初には耳にかけるテンプルがなく、いわば鼻眼鏡は眼鏡の原型である。テンプルが発明されるのは眼鏡が発明されてから500年近くも経った1700年代のことだった。テンプルの発明された後も鼻眼鏡はすぐに消え去ったわけではなく、長く耳掛眼鏡と併存した。15世紀から17世紀の間に一般庶民に徐々に浸透し、1840年代に現代的な鼻眼鏡が登場した。
1880年から1900年にかけては鼻眼鏡が大流行した。テンプルが発明されて長い年月が経ったのちに鼻眼鏡が流行したことを、眼鏡業界誌の『20/20』は、自動車からタイヤが見栄えのために取り除かれたような奇妙な出来事だと評し、その理由を眼鏡の必要性を軽く見せたい気持ちと、自分の鼻に合わせて特注された金銀の細工をステータスシンボルとしたい気持ちの二点から説明した[6]。
初期は金属製のリム(眼鏡の枠)だったが、次第に枠無し (Rimless) のもの、さらにセルロイド製のものが登場してきた。銀(スターリングシルバー)製のもの、鼈甲製のものも存在した。1879年にニューヨークの眼鏡商が発行したカタログでは、鉄製、鼈甲製、ゴム製、金メッキ、銀製、金製の順に鼻眼鏡が紹介され、金メッキ以降が際立って高く値付けられていた。鼈甲製は鉄製やゴム製と並んで安価であった[7]。鼻パッドは、初期はブリッジと一体化された金属製のもの、あるいはコルクを貼り付けたものだったが、後年にはセルロイドを添付したものや落下を防ぐために粘着性にしたのもの[8]が作られた。
20世紀初頭に検眼の発展により近視や乱視を矯正する処方が増えると、レンズの安定しにくい鼻眼鏡の欠点が許容されがたくなり、レンズを安定させるべくスプリングなどの工夫もされたが、結局、かつて忌み嫌われたテンプルが再発見され、鼻眼鏡は一般的でなくなっていった[9]。21世紀初頭においても、鼻眼鏡は一般的でない。
実用性[編集]
鼻眼鏡の流行していた当時から、レンズを眼の前に固定する手段として鼻眼鏡は耳掛眼鏡ほど実用的でないことが知られていた[10][11]。鼻眼鏡の長所として当時言われていたことは、掛け外しの手軽さ、見た目が良く洒落ていること、外見を極力変えずに視力を矯正できることであった。短所として指摘されていたことは、長時間の装用が耳掛眼鏡ほど快適になりがたいこと、顔つきによっては掛けられないこと、そして光学上の問題点であった。19世紀末にはすでに近視・遠視・老視のみならず乱視や斜位の矯正法も知られていたが、乱視や斜位の矯正では処方どおりの角度でレンズを眼前に固定することが求められるため、レンズが回転してしまいやすい鼻眼鏡はこれらの矯正に適さないことが指摘されていた[12][13]。レンズが回転しやすい短所は、C-ブリッジ型の、ブリッジ自体がバネを兼ねる構造によるものであり、それを解消するためにスプリング・ブリッジ型を始めとするブリッジとバネを分離した形式が作られたが、重く不恰好であることが嫌われてなかなか一般化しなかった。鼻の上の落ち着きやすいところに置いただけではレンズと眼との間隔が正しくなるとは限らないことも光学上の問題点として指摘され、当初レンズと同一平面上にあった鼻当てを後方に片寄せたオフセット・ガードも工夫された。
19世紀末の書籍では、プリズムが不要で乱視もないか軽い人が適切に調整されたオフセット・ガードつきのものを掛けるならばとの条件つきで、縁無しの鼻眼鏡がもっとも「現代的」で端麗な眼鏡として推薦されていた[14]。ガードによって引っ張ることで当時手術の難しかった蒙古ひだを「除去(remove)」することが可能だとする記述も見られる[15]。1921年に眼科医フランク・G・マーフィーも、耳掛け眼鏡をかけると鼻眼鏡より装用者が老けて見えるとし、その理由を耳掛け眼鏡のテンプルが目尻のしわに似るからだとした[16]。
鎖や紐[編集]
落下に備えた安全策として、鼻眼鏡に鎖や紐を取り付けて掛ける人(参考写真)もおり、1879年にニューヨークの眼鏡商が発行したカタログには鼻眼鏡には標準でケースと絹紐が付属するとある[17]が、鎖などを付けずに掛ける人々(参考写真)も多かった。鎖などを付けても鼻眼鏡が鼻から外れること自体は防げないが、外れた後に地面まで落下して破損したり紛失したりすることを防ぐことができる。鎖などの他端を固定する手段として、1912年のアメリカン・オプティカル・カンパニーのカタログでは、耳かけ(ear loop)、服に留めるホック(hook)、ヘアピン(hair pin)の3通りを紹介し[18]、指定なき場合の鎖の長さを
- ヘアピン用で229ミリ(9インチ)
- ホック用で330ミリ(13インチ)
- 短いヘアピン用で203ミリ(8インチ)
- 耳かけ用で102ミリ(4インチ)
と記載している[19]。
鎖も紐もヘアピンなどの金具と組み合わされ個装されて販売された他、金具なしの紐のみは個装のみならず、半ダースや1ダースの包装でも販売された。ヘアピンや耳掛け、ホックなどの金具にも様々な意匠のものが用意され、予め組み合わされた商品の他、好みの鎖の太さ・長さと金具を指定して注文することもできた[20]。鎖・紐を環状にしてネックレスのように首からかけている写真も多く見られる。ライト兄弟の妹、キャサリン・ライトの写真では、鎖をいったん耳にひっかけてから髪に留めている[21]。鎖などの他端を固定する手段として、上記の三種の他に、カタログの他のページで「オートマチック・アイグラス・ホルダー」と称する、巻き尺のように鎖を巻き取る仕組みのものも紹介され、装飾の多寡の異なる数種が用意されていた[22]。
1921年に眼科医フランク・G・マーフィーは、顔をより美しく見せるために鼻眼鏡を吊る鎖や紐の長さを加減すべきだと主張した。鎖や紐によって顔に線を描くことでその線の方向に顔が長く見える錯覚が起こるとの理論から、丸顔の人が鼻眼鏡をかける場合、丸顔を目立たなくするために鎖やひもを長くたるませて顔に縦の線を描くべきだとした。馬面の人が鼻眼鏡をかける場合、鎖や紐を耳方向へたるみなく引っ張って顔に横の線を描くことが有効だと考えた[23]。
鼻眼鏡の一般的でなくなった今日でも、似た例として補聴器や人工内耳体外装置の落下防止策として被服や頭髪へ紐で留めることがある。特に耳にかけずにもっぱら体内のインプラントへの磁石の吸着力に頼って装着する型の人工内耳体外装置では、紐で被服や頭髪に留めることが取扱説明書で紹介され、装置にも予め紐を取り付ける穴または窪みが用意されている[24][25][26]。
ハンドル[編集]
右のレンズ脇の金具は英語でハンドル handle と呼ばれた[27][28]。日本語ではつまみと呼ばれた[29]。もともとは眼鏡を持つための持ち手だったが、もっぱら上述の鎖や紐を取り付ける金具として使われるようになり、小型・簡素化され、ついには省略されることもあった。
1912年のアメリカン・オプティカル・カンパニーのカタログに掲載された鼻眼鏡は、型式によって様々なハンドルが取り付けられていたり、またはハンドルが省略されていたりしたが、注文により好みのハンドルを取り付けることもできた[30]。同カタログでは、当時の「良質」な鼻眼鏡のハンドルは最も簡素な1Hや、輪の根元にボール状の意匠を加えた5Hが一般的になってきており、装飾的なハンドルはその分減ってきたとしている。
好みのハンドルを注文できるように、ハンドル部品にも型番が割り振られていた。縁のある鼻眼鏡のためのハンドル部品は26種が掲載され、型番は数字+Hの形式であった。もっとも簡素な、紐を取り付ける輪に過ぎない1Hから始まって、18Hまで数字が大きくなるほど大きなものや意匠を凝らしたものになっていた。彫金を施したハンドルに対しては、例えば4Hに彫金を施したものに104Hというように別の型番が与えられ、金製の鼻眼鏡フレームでのみ注文可能であった。縁なしの鼻眼鏡のためにはハンドル部品が10種掲載され、型番はアルファベット+Hの形式であった。紐を取り付ける輪に過ぎないAHから始まってNHに至るまで、後になるほど大きなものや装飾性の高いものになっていた。
縁なしの鼻眼鏡ではハンドルは注文なきかぎり省略されたが、その場合、右レンズの脇に紐などを取り付けるための穴(hole for cord)[31]を空けることがあった。眼鏡レンズを縁なし眼鏡用に穴空け加工する際、穴の数はレンズ一組あたりの穴の個数で指定された。つまり、穴2つとは、2枚のレンズに穴をひとつずつ空けるという意味であった。穴の数の選択肢は、縁なしの耳掛け眼鏡用の四つ穴、縁なしの鼻眼鏡に紐などを取り付けない場合の二つ穴、そして縁なしの鼻眼鏡に紐を取り付けるための穴を加えた三つ穴の3通りであった[32][33]。当時の眼鏡処方箋の書式には、丸で囲むだけで指定できるようにあらかじめこの3つの選択肢が記されていた[34]。
-
右のレンズ脇の「ハンドル」に紐を取り付けた鼻眼鏡(1913年)
-
|
レンズ規格[編集]
レンズの型には規格があった。小数点以下には出典によって差異がある[35]が、1913年の書籍に掲載されたものを紹介すれば下表のとおりである[36]。縦横比3:4ほどの横長の楕円が一般的だったが、近業の多い者には真円に近づけ縦方向の視野を拡げた短楕円が勧められた。短楕円はまた、PDすなわち両の瞳の間隔の狭い者にも勧められた。当時の眼鏡はレンズの大きさを変えることでレンズ中心の間隔と瞳の間隔を合わせたため、横長の楕円形のまま狭いPDに合わせて小さなレンズにすると縦方向の視野が狭くなりすぎたからである。その他に、眉骨の飛び出た者のために短楕円の上辺を切り落とした木の葉型もあった[37]。楕円、短楕円、木の葉型より他の型を、当時の書籍は見た目が悪くグロテスクであるとして退けていた[38]。
1913年当時のレンズ規格
| 呼び名 | 縁あり用楕円 | 縁なし用楕円 | 短楕円 |
|---|
| ジャンボ |
46×38 |
46×38 |
44.5×39.5 |
|---|
| 0000 |
44.3×36 |
44×36 |
42.5×37.5 |
|---|
| 000 |
40.9×31.9 |
41×32 |
39.5×33.5 |
|---|
| 00 |
39.7×30.7 |
40×31 |
38.3×32.5 |
|---|
| 0 |
37.8×28.8 |
38.5×29.5 |
37×31 |
|---|
| 1 |
36.5×27.5 |
37×28 |
35.5×29.5 |
|---|
| 2 |
35×25.5 |
- |
- |
|---|
| 3 |
34×25 |
- |
- |
|---|
| 4 |
33×24 |
- |
- |
|---|
| A |
39×25 |
- |
- |
|---|
| B |
40×26 |
- |
- |
|---|
| C |
37×21 |
- |
- |
|---|
-
Hard-Bridge型の鼻眼鏡を着用している吉田茂
-
Hard-Bridge型の鼻眼鏡を着用している佐藤春夫
|
日本において[編集]
1928年、眼科医石津寛は、日本人には鼻根の低い者が多く、鼻眼鏡には鼻根の低い者に適合する鼻型が少ないため、合わないものを無理にかけて皮膚に不自然な皺をよらせ、容貌を崩してしまいがちで、日本人には鼻眼鏡の合う人が少ないようだとした[39]。
1968年、大阪大学名誉教授の宇山安夫は、鼻眼鏡を眼鏡の種類として耳掛眼鏡に次いで大切だとしながらも、日本では鼻眼鏡を掛ける人はきわめて少ないと述べた[40]。
日本の有名人では、吉田茂や後藤新平、佐藤春夫らが愛用していたことが有名である。今日の日本でもハード・ブリッジ型の鼻眼鏡を復刻させて製造・販売する眼鏡店があり、吉田茂を題材にしたテレビドラマの小道具としても採用された。多彩なバリエーションを揃えたフチなし眼鏡のシリーズの一環としてツルなし眼鏡との売り文句で販売している眼鏡店もある。