[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 mos68499367
mos68499367思い出した。これPC98とIBM-ATでの文化の違いじゃなかったかな。露見したのがDOS/Vに至るDOS Extensionの頃だったと思う。IBM関連の仕事で呼称がまちまちでDOSのプログラミングガイドの英語版を見たら表記がこっちでって記憶を思い出した twitter.com/senooyudai/sta…
2021-12-02 12:01:49unicodeではLowline,JISはアンダーラインと呼んだかな。 quotation→ダブルクオーテーション、apostrophe→シングルクオーテーションなんて呼ぶかも。 JISキーで@の上にある記号の読み方も色々。 twitter.com/senooyudai/sta…
2021-12-02 09:05:19@Kelangdbn これは昔からそうだったし、アンダーバーが間違ってるということでもないと思いますよ。 リンク先をご確認くださいませ。 catb.org/jargon/html/A/… ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8…
2021-12-02 16:20:21編集業務やメアドなどを口頭で伝える際に、この記号は「アンダーバー、もしくはアンダースコア」って言うようにしている。 twitter.com/senooyudai/sta…
この手の話題は定期な気がするけど、私が書き込んだのは初めてなので良かろうと自己完結。
数が溜まらないと他の見解を持つ人々に届かないので、各自はりきってイラつきを便所の落書きすれば良いと思う、迷惑にならない便所で。
「めんどくさ~い生理を(略)」
演者に文句があるわけではない。タイトル通りメーカーによらず生理用ナプキンのCMには概ねイラつくのでな。
生理用ナプキンのPRなんだから「使えば楽になるよ」という方向性でやるのは理解できるが万人が「楽になる」わけじゃないのでイラつくのである。
性能的に向上したとか、素材がこうだ、とか形状がこうだ、っていう方向性でPRしてくれれば心も安らか。
何がアレって、生理なんて軽いやつはパンツにうんこ付いたくらいの無痛で終わる的な例えがあんまり極端じゃ無いし。こういうヤツらはナプキンなんか何だって変わらないんで。
ナプキンに拘るのは重いやつとか肌が敏感なヤツとか。
重いやつは生理前も生理後も死んでいるし15分ごとに赤ん坊がうんこしたオムツみたいにベショベショのナプキン取り替えて、便座の中の水を真っ赤に染めてんだよ。月の四分の三くらい生理関係で発狂してても婦人病じゃないからね、何事にもボーダーラインはあるしグレーゾーンがあるって事。あとピルは合わない人間も一定数居るので安易に使えとか言うな。膣に差し込んでおく系も合う合わないがあるので使えとか言うな。この辺りを説明した上で産婦人科の医師が言うなら文句は無い、どんどん発信してくれ。
なので、絶対に「楽に成らない」と分かっているナプキンを、さも「万人が幸せになる」ようなスタンスでPRするCMがイラつくのである。やべぇ新興宗教とか、やべぇウォーター売りつける商売と何が違うのか、みたいな気持ちにさせられる。
あと、もっとイラつくのが、世の中に「ナプキンつかってれば生理中の女でも通常通り活動できる」的なイメージを植え付けることだ。
スポーツが男女で分かれているのと同じようなアレで生理中の女は生理中じゃない女と同じではない。軽い重いがあるだけだ。
軽い女の一部と男は、このあたりを分かっていない。
日常生活で気を使えとか言いたいわけではなく、スポーツで男女が別なのは当然よねっていう気持ちでいて欲しいだけだ。最近、このあたりもややこしいけど、私は生まれた時の肉体が持つ性別で分ければいいと思ってるのでスポーツは。
駅のホームは「プラットホーム」ですが、最近よく見る「製品やサービスの基盤」なら「プラットフォーム」。同じ単語(platform)なのに表記を使い分けるのは、「日本語になった外来語」と「まだ外国語感のあるもの」の違いと言えるでしょうか。
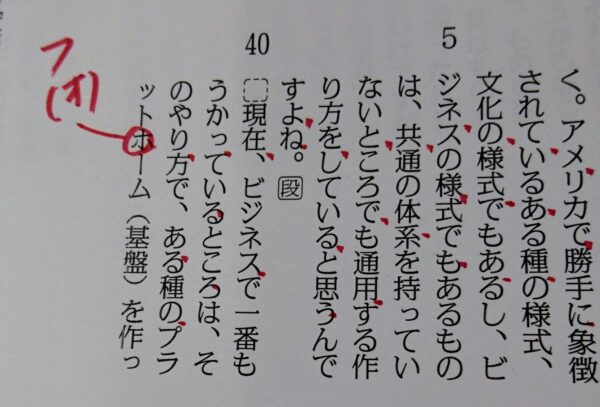
「platform」は「土台」「平らな形」の意(大辞林4版)。ビジネス分野などで「プラットフォーム」が盛んに使われるようになってきたのを受け、毎日新聞では2013年から「プラットホーム」に加えて「プラットフォーム」の表記も使い始めました。
辞書では、「プラットフォーム」も併記しながら主見出しとして「プラットホーム」を採用しているものが多いのですが、2020年に出た新明解国語辞典8版などでは、特に「駅のホーム」以外の意味で「プラットフォーム」の表記が使われることを示しています。
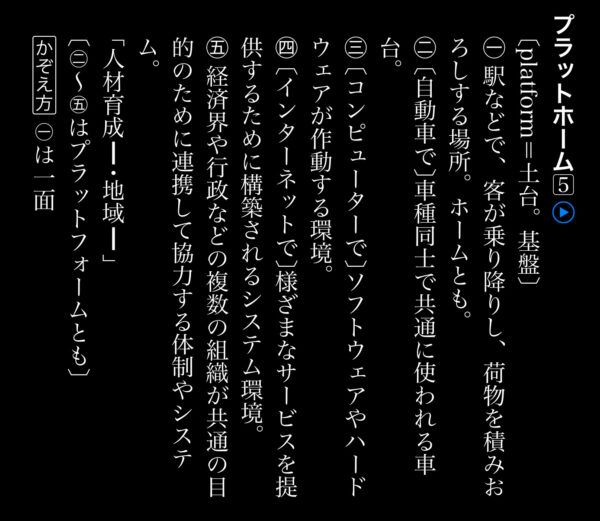
新明解国語辞典8版