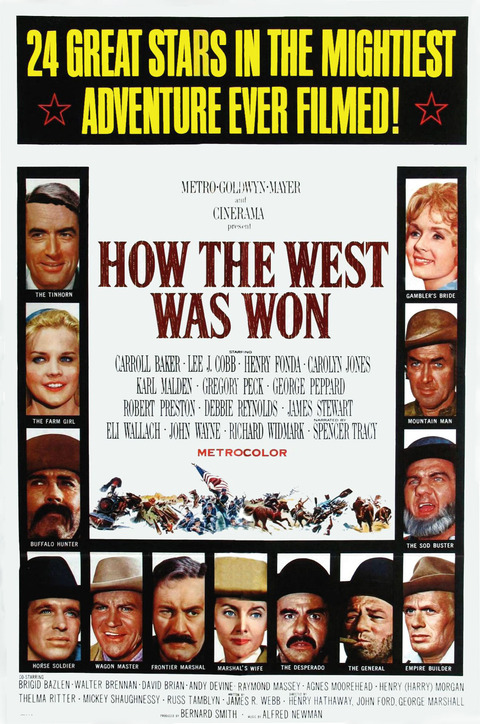[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
分かりづらいのがゲイとホモとオカマの違いではないでしょうか。実はとても大きな違いがあります。
性に関しては
の5つの項目から構成されていると言われ、この観点から考えるとわかりやすいです。
冒頭の方でも書いたとおり、ゲイというのは主に男性の同性愛者のことを言います。
性自認が男性で、性的指向や恋愛的指向が男性の方を男性同性愛者(ゲイ)と言うことができます。
ホモというのは男性同性愛者の『差別的な表現』になります。当事者同士がゲイをホモというのは問題になることは少ないと思いますが、当事者以外がゲイをホモと表現する場合には差別的な意味を含んでしまうので注意が必要です。
当事者以外の方はなるべく、ホモという言葉を使うのではなくゲイという言葉を使うようにしましょう。中にはゲイという言葉よりも、ホモという言葉の方がフランクに感じて良いという方もいらっしゃるようです。でも、多くはないので、ゲイという言葉を使った方が良いかと思います。
オカマとは元々、肛門を意味する江戸時代の俗語で、お尻を使い性的な行為をすることもある女装男娼を指す言葉です。(参考:Wikipedia)
現代においては『女性的な男性同性愛者、オネエ言葉を使う方、女装趣味の方などに使われることが多い言葉』となっています。『オカマという言葉は基本的には差別的な表現』なので、当事者同士が使うのであれば問題になることは少ないと思いますが、非当事者が使うと当事者に対してネガティブな印象を与えてしまうことがあるので注意してください。
ホモというのはゲイ男性の差別的な表現に対して『オカマという言葉は同性愛者、非同性愛者に関わらず女性的な男性に対して使われることがある蔑称』かと思います。
オネエというのは、オネエ言葉を使ったり『女性的な仕草をする女性的なゲイのこと』です。2006年に日本テレビ系「おネエMANS」が始まった頃から、オネエの解釈が拡大されて、メディアを中心にゲイと同じ意味で使われることが多くなってきました。(参考:Wikipedia)
メディアでも多く使われていることから、差別的な意味は含まないと思いますが、ゲイの多くは自身をオネエとは認識しておらず、オネエと言われることに抵抗がある人が多い印象を受けます。かくいう僕自身も「オネエ系?」と言われると、非常に気持ち悪いなと感じます。ゲイは、自身を男性として認識しているので、オネエ(お姉)という本来女性に対して使う言葉を使われるのは、決して気持ちが良いものではないでしょう。
オネエという言葉は、決して差別的な表現ではないとは思いますが、当事者の視点から言うと、正直あまり良い言葉でないように思います。意外にも、ホモやオカマといった言葉以上に扱いが難しい言葉かもしれません。あまり使用しない方が良いかと思います。
ドラァグクイーン(英: drag queen)は、女装をして行うパフォーマンスの一種で、女装パフォーマーを指します。その名前は、衣装の裾を引き摺る(drag)ことから来ています。ドラァグクイーンはもともと男性の同性愛者が性的指向の違いを超えるために、ドレスやハイヒールなど派手な衣裳に厚化粧で大仰な応対をすることで、男性が理想像として求める「女性の性」を過剰に演出したことが起源とされています。サブカルチャーとしてのゲイ文化の一環として生まれた異性装の1つであり、多くのドラァグクイーンは男性の同性愛者や両性愛者ですが、近年では男性の異性愛者や女性がドラァグクイーンとして活動することもあります。
ドラァグクイーンは「女性のパロディ」あるいは「女性の性表現を遊ぶ」ことを目的としており、トランスジェンダー女性が女性用衣服を着用することとは異なります。ロシアではドラァグクイーンを規制する法律の罰則を厳しくする動きもあります。
日本においては、歌舞伎の女形の伝統があり、古くから男性が女装して人前で芸を披露する文化が存在していました。近年では、マツコ・デラックスやミッツ・マングローブなどがメディアで活躍し、ドラァグクイーンがより広く認知されるようになっています。
ムーア人(英: Moors、西: Moro)は、中世のマグレブ、イベリア半島、シチリア、マルタに住んでいたイスラム教徒のことで、キリスト教徒のヨーロッパ人が最初に使った外来語である。ムーア人は当初、マグレブ地方の先住民であるベルベル人を指すものだったが、8世紀初頭以降イベリア半島がイスラム化されるにつれ、イスラム教徒を意味するようになった。
ムーア人は明確な民族でもなければ、自らを定義する民族でもない。1911年のブリタニカ百科事典は、この言葉は「民族学的な価値はない」と述べている。中世から近世にかけてのヨーロッパでは、アラブ人や北アフリカのベルベル人、イスラム教徒のヨーロッパ人に様々な呼び名が使われた。
また、ヨーロッパでは、スペインや北アフリカに住むイスラム教徒全般、特にアラブ系やベルベル系の人々を指す、より広範でやや侮蔑的な意味でも使われてきた。植民地時代には、ポルトガル人が南アジアやスリランカに「セイロン・ムーア人」「インド・ムーア人」という呼称を伝え、ベンガル人のムスリムもムーア人と呼ばれた。フィリピンでは、16世紀にスペイン人入植者が現地のイスラム教徒を指して導入したこの言葉が、「モロ」として一部ムスリム住民の自称にも用いられている。
地中海沿岸の北アフリカ地域の住民を指した古代ギリシア語 Μαυρόςおよびラテン語Maurusから。もともとは現地の部族名で、フェニキア語Mauharim(「西方の人」の意)に由来するとの説もある[1]。
7世紀以降には北アフリカのイスラム化が進み、イベリア半島に定着したアラブ人やベルベル人は原住民からモロと呼ばれるようになる。次第にモロはアラブ、ベルベル、トルコを問わずイスラム教徒一般を指す呼称となり、レコンキスタ以降は再び北西アフリカの異教徒住民を指すようなる。
寒さが徐々に緩み、自動車の冬用タイヤを夏用に付け替える時期が始まろうとしている。交換後、注意が必要なのがタイヤの脱落だ。重大事故につながるおそれをはらむが、実は車は右より左のタイヤの脱落が圧倒的に多く、脱輪事故の95%が左タイヤだったという統計もある。
国土交通省によると、タイヤ脱落事故は大型車に多く、11~3月に集中的に発生する。北海道や東北、北信越など積雪が多く、冬にタイヤ交換が必要な地域で発生率が高い。
自動車整備士資格を有する北海道科学大の北川浩史准教授(機械工学)は「タイヤ交換後は、ナットを専用のトルクレンチで締め直す『増し締め』を行ってほしい。交換や点検が不安な人は、プロである整備士に任せて」と呼びかける。
特に外れやすいのは左のタイヤだ。北海道警の調べでは昨年、道内で起きた脱輪事故60件のうち、57件が左側のタイヤだった。
北川准教授によると、車道は排水のために端が低くなっており、左側走行の日本では左に重心がかかる。右左折時も左後輪に負荷がかかりやすく、点検で注意が必要だという。
北川准教授は違法な車両改造のリスクも指摘する。札幌市では23年11月、車検通過後にタイヤを付け替えた違法改造の軽乗用車から左前のタイヤが外れ、当時4歳の女児に直撃する事故が発生。女児の意識は今も戻っていない。
北川准教授は「違法車両はプロの点検が受けられないため整備不良を見つけにくく、事故を起こしても保険適用されないことが多い。安全を軽視した無責任な行為で『うっかり事故』とは別物だ」と警鐘を鳴らす。【後藤佳怜】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
昭和21年11月3日 公布
昭和22年5月3日 施行