「ブイヨン(bouillon)」とは、フランス語で「だし」のことを指します。和食にかつお昆布だしがあるように、フランス料理にも牛や鶏、野菜で作っただしがあり、さまざまな料理を作るうえで欠かせません。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1830年、フランスでブルジョワ共和派が復古王政を倒した革命。七月王政の立憲君主政が成立した。
復古王政倒れる
1830年7月27日早朝、発行された『ナショナル』『グローブ』などの新聞が直ちに警察によって没収されると、印刷所では抵抗が始まり、パリ市街に暴動が起こった。一旦鎮圧されたが、軍が引き揚げた後、バリケードが築かれ、学生と労働者、カルボナリの残党がパリ12区の蜂起のための委員会を作った。翌日、パリ市庁、ノートルダムで激しい衝突が起こった。銀行家ラフィトはポリニャック首相に勅令撤回・内閣交替の要求を国王に伝えるように要請したが、面会を拒否された。その夜、ラフィト邸が抵抗運動本部となった。夜通しの戦闘で市庁舎は奪回され、翌朝、ラ=ファイエットを国民軍司令官とし、ラフィトらをパリ市委員会に任命、市庁舎に乗り込んだ。政府軍の一部が共和派に寝返り、戦局は一転、ルーヴルでもスイス人守備隊の抵抗を排除して市民が突入し、時計台に三色旗を掲げ、玉座にひとりの戦死者を座らせた。ヴェルサイユから9キロのサン-クルーにいたシャルル10世もようやく内閣会議を開き、勅令撤回と内閣の交替を決定した。これが『栄光の3日間』といわれる戦いだった。ドラクロワ『民衆を率いる自由の女神』
(引用)「栄光の三日間」、画家はパリ市民とともにあった。ドラクロワが民衆のなかに見たものは、「民衆をみちびく自由の女神」のすがたであった。女神は厚い胸もあらわに、右手に三色旗をふりかざし、左手に銃剣をひっさげ、バリケードの上に歩をはこぶ。この女神はなよやかな深窓の女ではなく、勤労にきたえられた、たくましい女性の肉体をもっている。「ノートル・ダムの塔上に燃える黄と青の空のもとに」政府軍のしかばねこえて、女神と市民は前進する。女神の左側に青いシャツを着た傷ついた労働者が、女神を見上げている。そのかたわらに、シルクハットを耳までずらせ、ラッパ銃を手にした市民がいる。これがドラクロワの自画像だといわれている。その背後にはベレーの労働者、その下に三角帽の理工科大学の学生も見える。自由の女神の右手には、どこかで見つけてきたピストルを両手に、なにかさけぶ小僧がいる。これはパリ特有の浮浪少年で、当時ガマンとよばれた。・・・どこで寝ているかわらないし、なにで生活しているか、だれも知らない。さわぎさえあれば、お祭り気分で集まり、群衆のあいだをすりぬけて、いたずらをしてまわる。・・・<井上幸治『ブルジョワの世紀』世界の歴史12 中央公論社 p.208>注意 七月革命の絵であること ドラクロワの俗に「自由の女神」といわれる絵画はあまりにも有名であるが、よく勘違いされている。これが1789年7月のフランス革命を描いているとか、1848年の二月革命を描いている、という勘違いだ。それは誤解で、ドラクロワのこの名画は1830年のフランス七月革命を描いています。もっともフランスは革命の連続によって王政を倒し、共和政を実現したので、この絵はイメージ的にすべてのフランスの革命に共通している、と言えないこともないが、世界史を学ぶ上では、1789年、1830年、1848年の革命の違いは明確におさえておく必要があります。
(引用)もっともこの誤解には無理からぬ点もある。三色旗はむろんのこと、自由の女神も共和政のシンボルであるマリアンヌのイメージに重ね合わされている。にもかかわらず、栄光の三日間がもたらしたのは共和政ではなく、ルイ=フィリップを戴く立憲君主政だったからである。<谷川稔『世界の歴史22 近代ヨーロッパの情熱と苦悩』1999 中央公論社 p.68>七月革命では共和政とはならず、七月王政という立憲君主政ができあがった。民衆の願いは裏切られて政治から切り離され、経済的にも産業資本家(ブルジョワ)の覇権が成立して民衆の困窮は続いた。そのような七月革命の影を描いたのがドーミエの風刺画「七月の英雄」である。ドラクロアとドーミエの絵を題材に、七月革命の表と裏を考察しよう。
七月革命の影響
1830年にフランスで起こった七月革命は、ウィーン体制下の反動的権力に抑えられていたヨーロッパ各地の自由主義運動、ナショナリズム運動に大きな影響を与えた。それらの動きには次のようなものがある。内視鏡検査や内視鏡治療は消化管出血を伴う可能性があり、その危険性をできるだけ抑えることが必要です。しかし、一方で心筋梗塞や脳梗塞の血栓塞栓症の治療や予防のために血液をサラサラにする薬(アスピリンなどの抗血小板薬やワルファリンなどの抗凝固薬などをまとめて抗血栓薬といいます)を内服されている方が増加してきており、これらの薬は出血し易いという副作用があります。そのため、以前は内視鏡検査や内視鏡治療を行う前には抗血栓薬を休薬することも多かったのですが、休薬期間中に致死的な血栓塞栓症を発症するケースも少なくないことがわかってきました。また、抗血栓薬と一言でいっても、現在その種類は豊富になっており、薬剤によって内視鏡検査や内視鏡治療を行った際の消化管出血のリスクが違うことがわかってきました。
日本消化器内視鏡学会では「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」を2005年に作成しましたが、2012年に従来よりも血栓塞栓症を重視したものに改訂し、出血と血栓塞栓症という相反する二つの危険性の間で休薬による血栓塞栓症の危険性を最小限に抑えることを目標にしたガイドラインとなっています。
このガイドラインでは、出血の危険を伴う内視鏡検査や処置を行う場合について、行う内視鏡処置の出血しやすさ(出血危険度)と内服している抗血栓薬の数や種類によって休薬のルールを細かく設定しています。具体的には、抗血栓薬が単剤であれば生検などの出血低危険度の内視鏡処置を施行する場合には内服の中止はは必要ありませんが、抗凝固薬であるワルファリンの場合は薬の効き具合をあらかじめ血液検査(PT-INR)で確認する必要があり、PT-INR値が高い場合には、出血危険度が高いため生検は施行しません。また、新しい薬である直接経口抗凝固薬(DOAC)および抗凝固薬の新たな知見を加えて2017年にガイドライン追補を作成しています。
抗血栓薬を内服している方でも、内視鏡検査を受けるだけ(観察だけ)の場合には基本的に休薬は必要ありません。しかし、検査中に病変を発見した場合、生検や内視鏡治療を行う場合もありますので、実際には、個人の状況に応じて内視鏡医と抗血栓薬を処方している処方医が連携をとりながら休薬の要否について決定しますので、検査を受ける前に、主治医とよく相談し、確認しておくことが重要です。
虎の門病院 消化器内科 布袋屋修
「ブイヨン(bouillon)」とは、フランス語で「だし」のことを指します。和食にかつお昆布だしがあるように、フランス料理にも牛や鶏、野菜で作っただしがあり、さまざまな料理を作るうえで欠かせません。
ブイヨンの材料は牛骨や鶏ガラ、香味野菜、スパイス、ハーブなどです。これらを大きめに切って鍋に入れ、水を加えて弱火で3〜4時間じっくりと煮込み旨味を抽出します。深い旨味がありながらもクセの少ない味わいなので、コンソメやポトフ、ポタージュなどさまざまな料理のベースとして使われます。
「コンソメ(consommé)」はフランス語で「完成された」という意味で、そのまま飲んでもおいしいスープとして親しまれています。こちらはブイヨンをベースに大量の牛赤身肉や香味野菜、卵白などを加えて2時間程煮込み、旨味をしっかりと抽出したものを漉して透き通ったスープに仕上げます。
旨味がギュッと凝縮された濃厚な風味は、まさに「完成されたスープ」と呼ばれる上品な味わいです。塩で味を調えていただくほか、冷やし固めたものをヴィシソワーズにのせるなど、ほかの料理と組み合わせて使うこともあります。
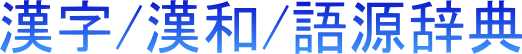 |
||||||||||||||||||||
| 漢字・漢和辞典-OK辞典⇒⇒⇒「鹵」という漢字 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||