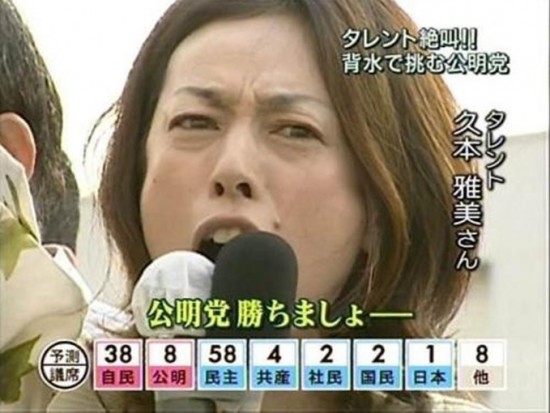私の場合は、ゴルフ場の坂道でカートが凍った路面でスリップして崖下に転落したのだが、その前にカートが蛇行した時に、傍の芝の上に身を投げ出して助かったのである。私は普段は物凄く思考速度が遅い人間で、通常の思考速度だと、絶対に、わずか1,2秒の間に状況を認識し、飛び出すメリットや危険性、カートに乗ったまま助かる可能性の計算や判断はできなかったと思う。
要するに、人間は、その持っている能力の数分の一、数十分の一くらいしか普段は使っていないと思われる。もっとも、その限界まで使って生きるのが幸福なのかどうか、分からないのだが。
3: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:08:00.05 ID:vmPvVK1XH
折角貰った命ですることが2ch
7: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:08:45.46 ID:cvpnHSpYa
スローモーションになるのはガチやで
実際は自分もスローやけど
13: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:09:35.26 ID:1ccK41mIK
>>7
これな
8: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:08:46.33 ID:M2mV2Wdbd
ワイトラックに引かれた時あるけどスローモーションにはならんなった
その代わり気絶してる間長い夢を見てたな
2: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:10:35.51 ID:+aYwslcV
9: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:08:57.70 ID:CYrKzRcZ0
ワイは時間飛んだで
10: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:08:58.29 ID:Due1BcRc0
何故人生のシミュレートが出来ないのか
11: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:09:10.06 ID:MYmD5QFTM
スローモーションになるのはマジにある
だからと言ってシミュレーションする余裕なんかない
14: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:09:36.13 ID:cEEh1aoLr
日常的にちんたら生きてるから常時スローモーションみたいなもんやろ
19: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:10:24.54 ID:oY+e74fO0
ゲームでめっちゃ集中した時に
視界の9割くらい白黒に見えたことはある
21: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:10:42.75 ID:OPNs3g5Ed
スローモーションじゃなくて視界が断片的になるから遅く見えるように錯覚してるだけだぞ
22: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:10:59.56 ID:Qh6ezDTt0
スローモーションでは見えるけど思考は完全にストップしてるわ
25: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:11:14.19 ID:V23XbG/K0
わいが横から追突されて窓から飛び出した時は、スローモーションじゃなくて周りが加速してワイが動けなくなるって感覚やったけどな
27: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:11:52.96 ID:2+yu3nIa0
T字路チャリで直進してて横から鼻先突き出してきた車に軽くぶつけられるってパターンの事故
何回かやったけどスローにはならんかったで
33: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:12:58.78 ID:eXqOIsPK0
スローモーションの経験はないけど走馬灯の経験はあるわ
36: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:13:53.63 ID:MrNPhQUap
これはガチ
ドッジボールが強い奴からのボール飛んできたときにスローになったからとれた
ちなインキャ
37: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:13:55.07 ID:o7bzm5Ild
えこれ俺もあったしガチなんやが嘘扱いなのかなcってかなんか悔c
39: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:14:15.16 ID:/b1RPXrA0
やーぱアドレナリンってすげぇわ
42: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:14:51.93 ID:x+Zbo+nx0
スローモーションはガチやぞ
44: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:15:07.98 ID:poJMH7BH0
事故ったことないやつが嘘松いうのは可笑しいよなぁ!?
46: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:15:32.60 ID:9dglD5Bmx
スローはガチやけど自分の体は加速しないぞ
57: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:17:50.52 ID:o7bzm5Ild
>>46
これやな
ワイも受け身とろうと思ったけど意識的に動かせたのは指くらいやった
65: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:20:01.19 ID:KjIXsMdA0
>>57
顔の向きもいけたで
体は無理やわ
48: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:16:17.05 ID:NQFyEOdSM
無音になって第三者視点になる
51: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:16:27.85 ID:qANN9zmT0
スローになるけど「ヤバイ」って思うことしかできん
52: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:16:44.44 ID:RxcfQdFF0
リアルタイムにスローなのか思い出したときに鮮明に思い返せてスローに見えるのか分からん
55: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:17:39.48 ID:vycYAQbe0
スローというか吹っ飛んだ瞬間自分の思考が早回しになってる感じちゃうん?
59: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:18:11.54 ID:PYEImHL00
車にはねられたことあるけどスローモーションというより一瞬時間が止まったような感覚で気がついたら吹っ飛んでる感じ
60: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:18:29.72 ID:D2o6zZUHd
お前ら事故りすぎやろ
61: 救世主 2017/12/02(土) 13:18:58.86 ID:SiL6PRob0
死を回避するために感覚が鋭くなることはありうる
64: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:19:42.84 ID:t675LevR0
ワイが正面衝突した時は気づいたら地面に歯撃っとった
おまけに出っ歯なせいで唇噛むし血だらけやったわ
68: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:20:20.40 ID:rZt5bF9u0
スローっぽく感じるけど別にオーバークロックみたいに判断力上がるわけやないやろ
69: 風吹けば名無し 2017/12/02(土) 13:20:49.53 ID:RYz6jH7ka
こういうのってスローに感じたとしても全てがスローになるもんちゃうんか
4: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:12:30.66 ID:W0mweA6d
スローモーションに成るけど結局何もできない
その瞬間を記憶に留めるだけ
10: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:16:49.47 ID:xGWfQZwL
20年以上前の話だが、バイク事故を起こした
右折車がオレを見落として車に直撃
一回転して顔面からアスファルトに叩き付けられたが
まるでコマ送りのようにぶつかった、その時アスファルトの石と石の繋ぎ目がはっきりと見えた
静止画を一枚一枚見るように。
12: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:22:23.91 ID:4x8doSSe
仕組みがわかって人為的に再現できるようになったら中二病が捗る
18: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:31:36.10 ID:x6Pq3uUo
なるね。私も子供の頃に車にはねられたときそうなったよ。
21: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:33:59.86 ID:GLusxAPE
以前交通事故で後ろからひかれてフロントガラス突き破ったんだが
ほんの一瞬だったはずなのにその時の割れたフロントガラスが飛んでる映像が10分くらい続いたと感じた
何やらわからん苦しいこの状態がいつまで続くんだろうと
つまりその時点では何が起こったかすら知らないのだから危機意識や感情とも違う
275: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/07(火) 18:22:11.15 ID:fI+2lZZI
>>21
怖すぎる
26: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:44:18.65 ID:nZOx+iId
雪道で滑ってしりもちつく時はスローに見える
転ぶのは回避出来ないけど受け身はとれるかも
29: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 21:52:49.04 ID:hEu5M4Vd
>>26
それはあるかも。
まず頭守る。次に手足尻、複数の接地点でダメージの分散図る。余裕あれば荷物守る。
短い時間で対応してるな。
出来てなければこれまで数回は骨折していると思う。
33: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:04:25.48 ID:aj/4bKOJ
確かに、事故にあやうく巻き込まれそうになった時にゆっくりに感じた、けども、どうなんだろ主観だからなあ
38: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:13:33.84 ID:3k1Rlxd4
あるよ。自動車と衝突したとき時間が止まったように感じた。相手のあっ!と言
う顔がはっきり見えた。
39: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:13:52.29 ID:CcULr6x4
俺も経験あるわ。自転車に乗ってて前輪が段差を乗り切れず自転車が前転。
俺は空中に投げ出された。そのとき非常にゆっくりだった。「そうだ受け身を
しなきゃ」と思った。そして地面に叩きつけられたとき受け身してダメージは
全くなかった。見ていた女子高生が笑ってた。
42: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:16:17.03 ID:aj/4bKOJ
ゆっくりに感じるんだけども、その時にこのままだと事故で大変な目に合うと言う予測も解ってた
にもかかわらず、なんか他人事みたいに遠くの出来事のように感じた。もっと慌ててどうにかするべきなのに
あー、やばいな~、みたいに重いながら観察してしまった。
たまたま事故に巻き込まれなかったが、そういう感じもあった
52: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:32:37.03 ID:KYjfZAf/
命の危険を感じた瞬間、無闇と思考が早くなるのよね
俺も経験した
でも体がついてこないので結局何もできないって言うwwwww
53: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 22:35:06.90 ID:FZ8zEE7v
ここだけの話だぞ、心眼と組み合わせて使うのだ(´・ω・`)
62: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 23:07:48.98 ID:hFcTtbC2
絶体絶命の本当の危機に陥ると、瞬間的に人間は驚異的な能力を発揮する。
感覚能力も鋭くなる。
69: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 23:18:39.49 ID:0qXEPtF4
過負荷がかからないように普段はリミッターがかかってるんだろう
火事場の馬鹿力
73: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 23:31:24.72 ID:/k6g3Qf/
おれも階段から落ちた時時間が止まったわ
80: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/30(月) 23:55:39.83 ID:HlnbhRk9
俺の経験したスローモーションは、子供の頃にクリスマスのシャンパンが開かない親父がキレて瓶をテーブルに叩き付けた瞬間
瓶からニョロっとホースみたいな泡が伸びてブシューっと天井まで噴出した時だな。
ケーキも料理も全部台無しになった
84: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 00:10:32.95 ID:uTdMpfW3
別に危険でなくともスポーツの時にもたまにあるよ。
124: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 08:02:34.73 ID:JAMeaWgC
>>84
スポーツの時、あるある
自分は中学の時リレー補欠だったが、ほんとに競技直前になって「選手が足くじいたんで代わりに出てね」と言われた。
はぁ?て感じで出場して走ったが、その時前を行く選手が止まって見え、無我夢中で走った。
あと少しで追いつくというところで通常モードに戻ったが、その後しばらく「伝説の走り」と言われた。
あんな周囲がスローモーションに見えるような事をしょっちゅうできる奴が1流選手なんだろうなと思ったよ(´・ω・`)
87: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 00:28:32.22 ID:5sCLcWWp
交差点で信号無視の400ccバイクに側面から突っ込まれた瞬間は
スローでバッチリ覚えてる
89: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 00:38:48.92 ID:AoVTm4mk
経験があるけど、瞬間的に音と色がなくなる代わりに
動きがゆっくり見えて危険が回避出来た。
101: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 03:08:58.03 ID:g1xkZgZu
崖から落ちそうになった時そうなったな
リアル膝矢状態になったけど落ちずにすんだ
151: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 13:57:25.35 ID:eOr49fh3
スローモーションっていうか脳が覚醒して
処理能力が瞬間的に上がってるってことなんだろうな
156: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 18:33:15.69 ID:YD+V+kWP
やっぱりスローモーションの感じするんだね
事故った時にそうだった、友達にもそう話してる
ちょっとした接触事故だけど、こっちの車が突き上げられた感じ
その瞬間がスローモーション
スピード出ていなかったので、身体に衝撃はなく、後部座席の娘たちはそのまアイスを舐めていた
自分も経験しているけどやっぱり不思議
そういう経験は、後にも先にもあの時だけ
171: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 21:38:43.81 ID:tTx+3ArC
信号のない交差点。車で飛ばしていたら、脇から急にとびだしてきた。
思わず、急ブレーキ、車が滑って当たった。
その滑っている数秒間にこれまでの人生が走馬灯のように全てスローに見えた。
双方けがなしで物損ですんで良かったが、今でも脳裏に残っている。
186: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/01(水) 07:13:07.36 ID:QR6T5Ukf
はね飛ばされて空中にいるときは長く感じたね。
おかげで受身が取れて頭を打たなかった。
もちろん腕はずる向けに成ったが。
あーいたたた。思い出しても痛い。
187: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/01(水) 07:16:41.58 ID:dyGqjdqT
野球で打席に入った時ボールがスローモーションに見えることがあったけど
あれも危険を感じる瞬間だったのだろうか・・・ゾーンに入っていたと思っていたけど
195: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/01(水) 08:41:45.15 ID:CybSD9sT
死の間際の走馬灯も
「死」という危機から脱出するための知恵や経験は無いかと記憶を走査しているという仮説がある
234: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/01(水) 16:41:18.09 ID:TzlJ8QeS
子供の頃ガラスのドアを手で押したら
われてしまった。
細かく粉々に砕けて落ちていくガラスがしっかりと見えた。
強い雨みたいな感じだった。
周りにいた人たちはバーンともの凄い音と同時に硝子が砕け散っただけにしか見えてなかった、当たり前だけどな。あれは綺麗だったな~
245: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/06/01(水) 18:20:48.17 ID:M7dTlF6v
スキーで派手に転倒するときは、空中にいるコンマ何秒が
やけにスローモーションに感じて、
次に訪れる雪面に叩きつけられるのを身構えている。
98: 名無しのひみつ@\(^o^)/ 2016/05/31(火) 02:19:54.19 ID:6Rm7GmYl
ここの話を聞いてると飛び込み自殺とかは最後まで
意識がはっきりしてるのかな