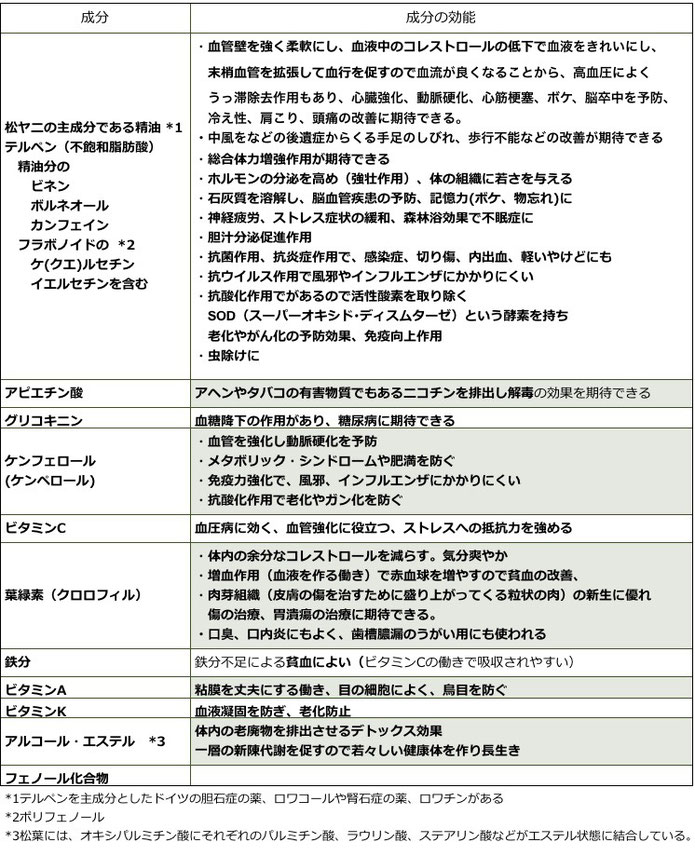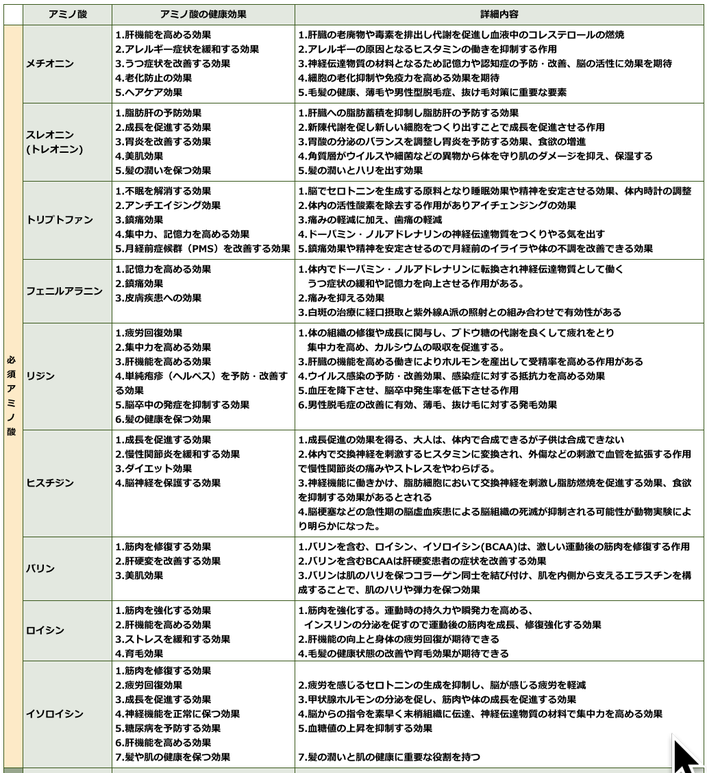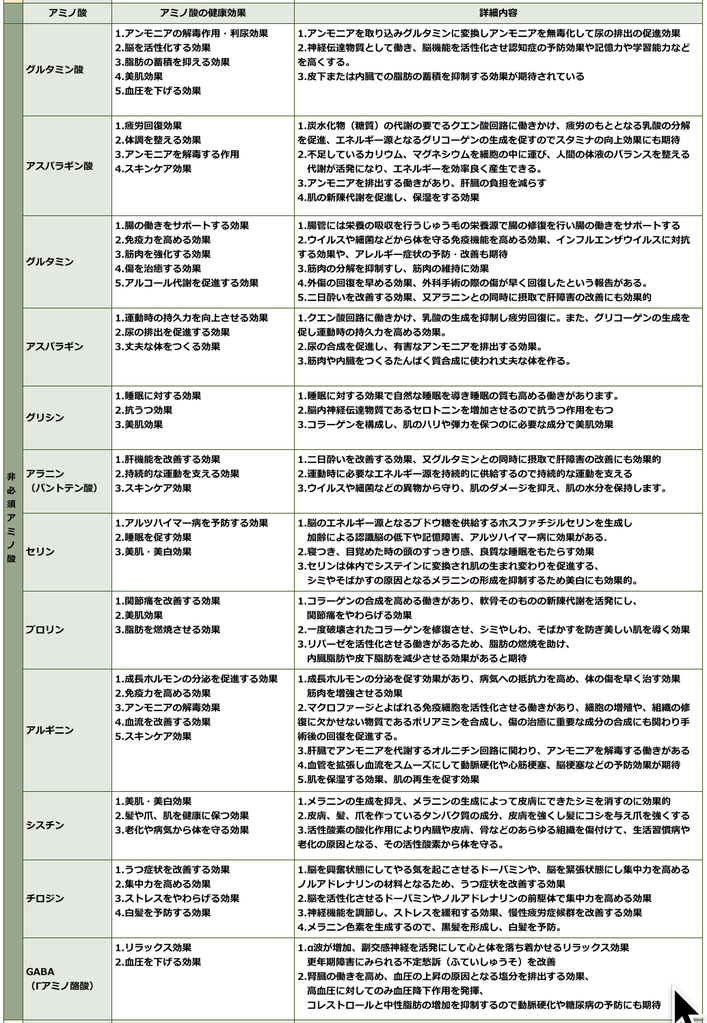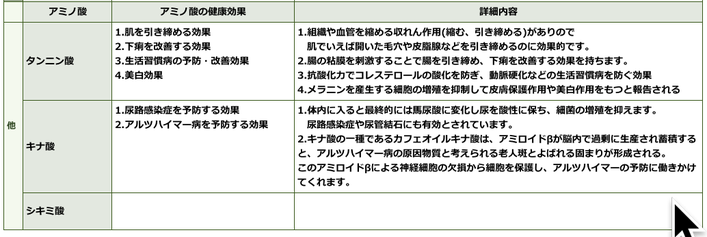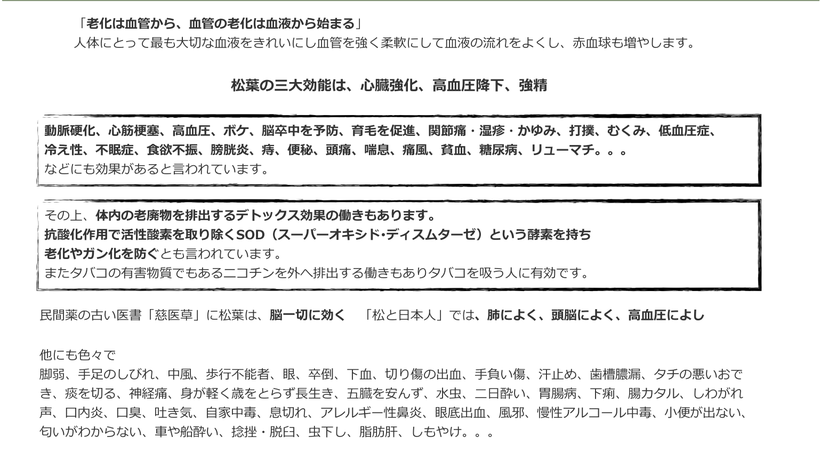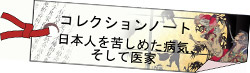内海 聡さんのサイトより
https://note.com/utsuminkoushiki/n/n9dd0db1b77dd
<転載開始>
まずはこの言葉を作ったじじいの嘘八百から調べていただきたいとは思いますが、とにかくいえるのはコレステロールや血圧や糖尿病や尿酸の薬を飲んではいけません。
こんなものは食事で治すしか方法は存在しないモノであり、そもそも治す必要がない=基準値が間違っているということをまだまだほとんどの人が知りません。
コレステロールは副腎皮質ホルモンや性ホルモンなどの原料になる重要栄養素、これをわざわざ下げるとか病気になりたいと公言しているようなものです。
このコレステロールが悪役というのは医学界と製薬業界とマスメディアによる嘘丸出しのマーケティングに過ぎません。
https://note.com/utsuminkoushiki/n/n9dd0db1b77dd
<転載開始>
まずはこの言葉を作ったじじいの嘘八百から調べていただきたいとは思いますが、とにかくいえるのはコレステロールや血圧や糖尿病や尿酸の薬を飲んではいけません。
こんなものは食事で治すしか方法は存在しないモノであり、そもそも治す必要がない=基準値が間違っているということをまだまだほとんどの人が知りません。
コレステロールは副腎皮質ホルモンや性ホルモンなどの原料になる重要栄養素、これをわざわざ下げるとか病気になりたいと公言しているようなものです。
このコレステロールが悪役というのは医学界と製薬業界とマスメディアによる嘘丸出しのマーケティングに過ぎません。
コレステロールが上がっても動脈硬化リスクはほとんど上がりません。
まったく変わらないというデータもあります。
ではなにが問題かというとコレステロールが下がれば下がるほど、癌、感染症、老人の自立度低下などがおこるのです。
一番癌にならないのは無制限にコレステロールが高い人々であり、総合的にいうと年齢により上がっていくこと、240~280程度の人が最長寿と推測されること、85歳以上の高齢者で一番長生きしたのはコレステロール値が高い人たちであることがわかっています。
つまり現行の220以下が正常というのは噓であり、一番死にやすい数字であるとさえいえるかもしれません。
しかもコレステロールのクスリ自体が非常に発ガン性が高い毒物です。
血圧も同じです。
以前は高血圧の基準は160/95でこれでも要注意でしたが、こっちが本当の意味でよい基準でした。
血圧も同様で年齢が上がるにつれて上がるのが正常であり、血圧を下げて良かったことは心筋梗塞が少し下がったことくらい、血圧が下がると癌、感染症、老人の自立度低下などがおこります。
昔は年齢に90を足せと教えたそうですが、私は年齢に100を足せとよく指導します。
東海大学の元教授で日本総合検診医学会評議員でもあった大櫛陽一氏は性別、年齢別の正常値を設定しています。
私はこの表をよく参考にさせてもらっていますが、これでいうと血圧は170くらいまでOK、コレステロールも260~280くらいまでOKなのです。
また代表的な降圧薬はカルシウム拮抗薬とARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)も、癌の発生率を増します。
またカルシウム拮抗薬が長期的には心不全を増やすこと、ARBが心不全に使われた場合も突然死が起きることも分かっています。
尿酸なんてますます食事療法すれば済むものの代表格であり、糖尿病は糖質制限、もしくは断糖するに勝るものはありません。
粥状動脈硬化の主たる原因はコレステロールではなく、糖とトランス脂肪酸と塩素になると思われます。
飲料に多く含まれるフルクトース(果糖)は約10倍グルコースより糖化反応を起こしやすいこともわかっています。
ただ、もし糖尿の薬を飲んでいる方がいてもいきなりやめないで、相談できる治療家などと徐々にやめていく必要はあります。
これはインスリン注射でさえもそうであり、内服糖尿病薬の弊害とインスリンの弊害についてこれから説明します。
糖尿病のクスリにはいくつか種類があり、基本は血糖降下剤、血糖吸収抑制剤、インスリン抵抗改善剤、インスリン注射などに分かれます。
血糖吸収抑制剤はもっともマイルドな作用ですが、これなどちょっと食事を変えるだけでよくなるレベルなので、まったく飲む必要がないものです。
SU剤はもっとも使われてしまっている血糖降下剤ですが、低血糖症やアシドーシスなどの副作用は添付文書にも掲載されていますし、ほかの弊害もたらします。
たとえばある研究ではSU剤を使用したグループと使用しないグループで、前者で心筋梗塞が増えるという皮肉な結果になりました。
またビグアナイド薬はインスリンを出すβ細胞の働きを抑える作用があり、とてもお勧めできる薬ではありません。
このような血糖降下剤はインスリンを無理やり出したり無理やり抑えたりしているのであり、原因(糖質過剰、炭水化物過剰)を除去せず対症療法していれば、一時的に良くなっても必ずますます悪くなってしまうのです。
グリタゾン剤は抵抗改善剤に属しますが、代表格のクスリであるアクトスは心不全や心筋梗塞が増えることが判明しており、骨折しやすくなる事や膀胱癌が増えることがわかっています。
とてもではないが使えるクスリではないのです。
インスリン注射については全否定は難しいところがあります。
よく糖尿病には二種類があり、1型糖尿病と2型糖尿病があるといわれます。
1型とは膵臓のβ細胞が破壊された糖尿病をさし、以前はインスリン依存型糖尿病などといわれていました。
こちらはなかなかインスリンなしでは難しいのですが(それでも本当はインスリンを使わなくすることもできます。ここでは書けませんが)、2型糖尿病の場合はインスリンを使う必要はまずありません。
インスリンを使うタイミングがあるとすれば、高血糖でこん睡している救急疾患の方たちなどになると思います。
非常に悪い糖尿病の数値の方でもインスリンを使わず改善させることは可能です。
それには断糖が必要ですが自分だけでは行わず、必ず分子整合栄養学などを学んだ方とともに行ってください。
なぜインスリンを使わないほうがいいかというと、これはあらゆるホルモン全体に言えるのですが、インスリンを打ってしまうことで身体がインスリンを産生しなくなってしまうからです。
これは脳ホルモンでも甲状腺ホルモンでも性ホルモンでも同じことが言えます。
それだけでなくインスリンは劇薬のため、低血糖やアシドーシスや昏睡ももたらしやすいクスリであり、やはり糖尿に代表される生活習慣病は食生活の改善でよくすることが重要なのです。
まったく変わらないというデータもあります。
ではなにが問題かというとコレステロールが下がれば下がるほど、癌、感染症、老人の自立度低下などがおこるのです。
一番癌にならないのは無制限にコレステロールが高い人々であり、総合的にいうと年齢により上がっていくこと、240~280程度の人が最長寿と推測されること、85歳以上の高齢者で一番長生きしたのはコレステロール値が高い人たちであることがわかっています。
つまり現行の220以下が正常というのは噓であり、一番死にやすい数字であるとさえいえるかもしれません。
しかもコレステロールのクスリ自体が非常に発ガン性が高い毒物です。
血圧も同じです。
以前は高血圧の基準は160/95でこれでも要注意でしたが、こっちが本当の意味でよい基準でした。
血圧も同様で年齢が上がるにつれて上がるのが正常であり、血圧を下げて良かったことは心筋梗塞が少し下がったことくらい、血圧が下がると癌、感染症、老人の自立度低下などがおこります。
昔は年齢に90を足せと教えたそうですが、私は年齢に100を足せとよく指導します。
東海大学の元教授で日本総合検診医学会評議員でもあった大櫛陽一氏は性別、年齢別の正常値を設定しています。
私はこの表をよく参考にさせてもらっていますが、これでいうと血圧は170くらいまでOK、コレステロールも260~280くらいまでOKなのです。
また代表的な降圧薬はカルシウム拮抗薬とARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)も、癌の発生率を増します。
またカルシウム拮抗薬が長期的には心不全を増やすこと、ARBが心不全に使われた場合も突然死が起きることも分かっています。
尿酸なんてますます食事療法すれば済むものの代表格であり、糖尿病は糖質制限、もしくは断糖するに勝るものはありません。
粥状動脈硬化の主たる原因はコレステロールではなく、糖とトランス脂肪酸と塩素になると思われます。
飲料に多く含まれるフルクトース(果糖)は約10倍グルコースより糖化反応を起こしやすいこともわかっています。
ただ、もし糖尿の薬を飲んでいる方がいてもいきなりやめないで、相談できる治療家などと徐々にやめていく必要はあります。
これはインスリン注射でさえもそうであり、内服糖尿病薬の弊害とインスリンの弊害についてこれから説明します。
糖尿病のクスリにはいくつか種類があり、基本は血糖降下剤、血糖吸収抑制剤、インスリン抵抗改善剤、インスリン注射などに分かれます。
血糖吸収抑制剤はもっともマイルドな作用ですが、これなどちょっと食事を変えるだけでよくなるレベルなので、まったく飲む必要がないものです。
SU剤はもっとも使われてしまっている血糖降下剤ですが、低血糖症やアシドーシスなどの副作用は添付文書にも掲載されていますし、ほかの弊害もたらします。
たとえばある研究ではSU剤を使用したグループと使用しないグループで、前者で心筋梗塞が増えるという皮肉な結果になりました。
またビグアナイド薬はインスリンを出すβ細胞の働きを抑える作用があり、とてもお勧めできる薬ではありません。
このような血糖降下剤はインスリンを無理やり出したり無理やり抑えたりしているのであり、原因(糖質過剰、炭水化物過剰)を除去せず対症療法していれば、一時的に良くなっても必ずますます悪くなってしまうのです。
グリタゾン剤は抵抗改善剤に属しますが、代表格のクスリであるアクトスは心不全や心筋梗塞が増えることが判明しており、骨折しやすくなる事や膀胱癌が増えることがわかっています。
とてもではないが使えるクスリではないのです。
インスリン注射については全否定は難しいところがあります。
よく糖尿病には二種類があり、1型糖尿病と2型糖尿病があるといわれます。
1型とは膵臓のβ細胞が破壊された糖尿病をさし、以前はインスリン依存型糖尿病などといわれていました。
こちらはなかなかインスリンなしでは難しいのですが(それでも本当はインスリンを使わなくすることもできます。ここでは書けませんが)、2型糖尿病の場合はインスリンを使う必要はまずありません。
インスリンを使うタイミングがあるとすれば、高血糖でこん睡している救急疾患の方たちなどになると思います。
非常に悪い糖尿病の数値の方でもインスリンを使わず改善させることは可能です。
それには断糖が必要ですが自分だけでは行わず、必ず分子整合栄養学などを学んだ方とともに行ってください。
なぜインスリンを使わないほうがいいかというと、これはあらゆるホルモン全体に言えるのですが、インスリンを打ってしまうことで身体がインスリンを産生しなくなってしまうからです。
これは脳ホルモンでも甲状腺ホルモンでも性ホルモンでも同じことが言えます。
それだけでなくインスリンは劇薬のため、低血糖やアシドーシスや昏睡ももたらしやすいクスリであり、やはり糖尿に代表される生活習慣病は食生活の改善でよくすることが重要なのです。