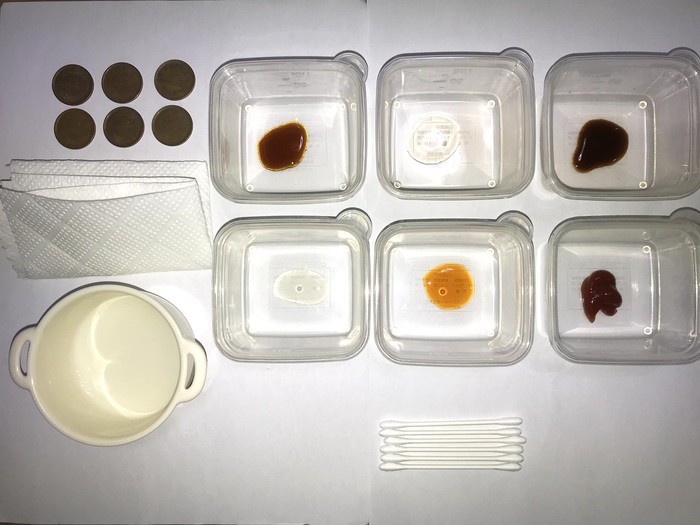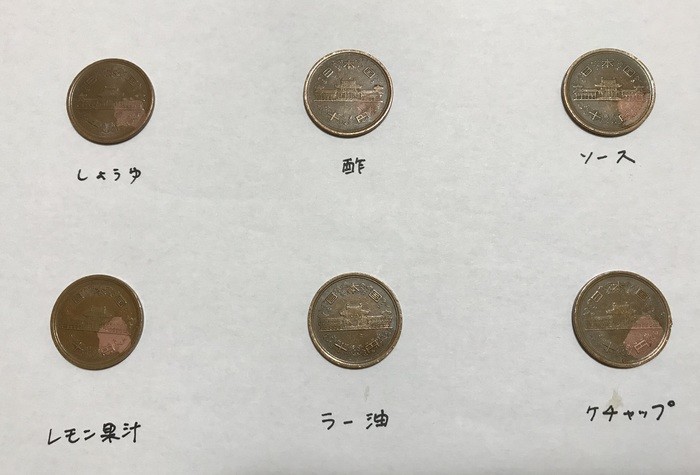2:
名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:09.96 ID:/N248KCw0
塩
4: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:25.91 ID:TkqrPo51p
素パスタ
5: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:56.43 ID:o6ppE5DeM
塩分控えまひょか
6: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:05:57.04 ID:r0Np5ueDa
イタリアでは主流定期
7: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:22.32 ID:U7Gz6ihE0
筋トレしとるんか
8: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:23.03 ID:loGv930Y0
茹でる時にしっかり入れた方がかけるよりうまい
9: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:35.37 ID:sdI9wktX0
米の方が安いやろ
10: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:40.96 ID:P/t7XmcEM
そら味ついてるパスタにはなかなか塩は足さんだろ
11: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:06:51.01 ID:qtO/H9Km0
せめてにんにくとオリーブオイルくらいは入れてもろて
12: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:06.39 ID:UTWWjj360
ハーブソルト買えば素パスタも素パンも最高に美味くなるからそこだけはケチるな
13: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:08.26 ID:MX0rlRZu0
炊飯器買えない貧困層おるんやで
15: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:03.98 ID:zIiJZ9570
>>13
それスタート地点はどこなんだよ
14: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:07:48.38 ID:0KOmAFgaM
16: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:07.51 ID:ODrDhzHYa
やめてください
17: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:17.54 ID:fToxvr5P0
パスタふりかけ美味いぞ
味道楽とかめっちゃ合うで
18: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:32.16 ID:rlKZBpqu0
パスタ作ったお前
19: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:08:50.22 ID:iZRbL3zL0
ニンニク入れろ
20: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:09:12.08 ID:XMjDgWL50
実際どうしたら安上がりや?
最低限人が食うものとして
22: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:10:37.61 ID:HC1tS2Ko0
>>20
とうもろこしの粉を水で溶いて固めたもの
37: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:14:24.02 ID:qtO/H9Km0
>>20
塩にんにくオリーブオイル鷹の爪
これが高いと言うなら稼ぎのほうを増やせ
38: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:22.58 ID:LCyRTwdBa
>>20
オートミール安いと思うわ
健康目当てに食べるけど
53: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:22:18.08 ID:GBrT1ZZod
>>38
ワイもオートミール食ってるわ
安いし美味いし最高や
24: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:11:50.11 ID:b/QLB1xR0
醤油も買えないのか
28: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:39.66 ID:idi5sij00
いくら金無くても卵は食え
29: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:44.86 ID:IkGKiYNXa
黒胡椒にしとけよ…そういうパスタあるらしいし
30: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:12:45.53 ID:wMwgvqC60
ペペロンチーノってめちゃくちゃ貧乏な食い物よな
32: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:13:34.48 ID:QIGUe5Xj0
貧しすぎるよ…
34: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:13:45.30 ID:GBrT1ZZod
味の素と醤油と生卵で食ってたことはある
あ今卵高いのか
35: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:14:04.23 ID:LCyRTwdBa
味ついてないって言う意味あんの?
39: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:24.12 ID:idi5sij00
ちゃんと作ったら焼きそばとパスタどっちが安いんや?
どちらもイオンの麺として
40: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:15:27.57 ID:AC1NPYWU0
塩は極端すぎるにしてもふりかけはほんま虚しくなる
逆ににんにくは一かけら入れるだけでその虚しさが消えるからよい
46: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:17:30.53 ID:3X1sYD2ga
明太子パスタ食べてーな
47: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:17:59.54 ID:p2swmwW2M
ペペロンチーノってアホみたいに安く作れるしうまいけどすぐ飽きるよな
49: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:11.69 ID:a84Gqq+MM
塩パスタは割と美味かったぞ
50: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:18.57 ID:mWZvIIUo0
パスタって何もつけなくても美味くない?
51: 名無しのぽけまとめーる 2023/03/05(日) 03:19:30.24 ID:ySWrXrqMM
パスタってオリーブオイルかけて塩コショウ味の素だけで美味いぞ
卵もいらん