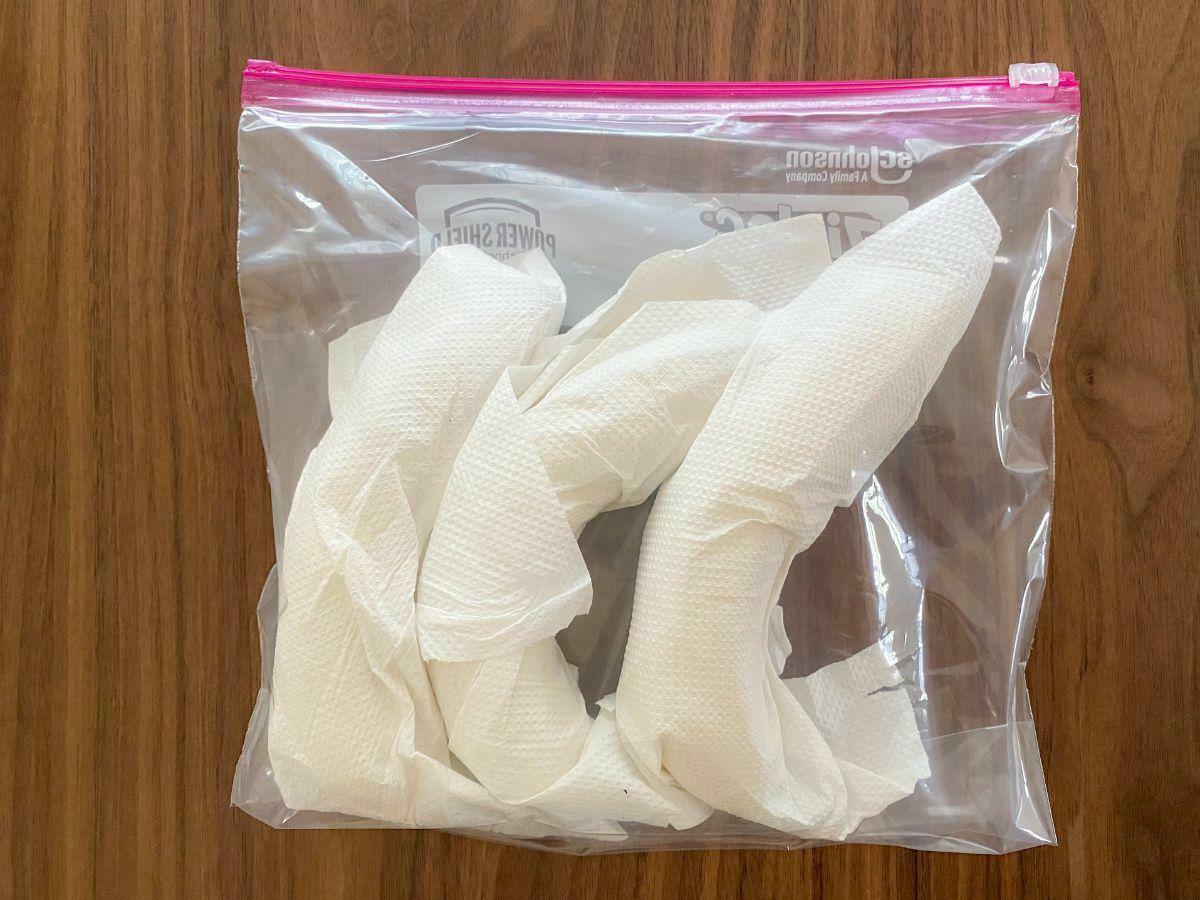3: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:00:44.17 ID:/bOTBjzdd
仕事どうやってみつけたの
6: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:01:09.02 ID:3XOpx3Uva
>>3
ハロワの就労支援うけてて
そこから
12: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:02:12.64 ID:/bOTBjzdd
>>6
そんなんで就職出来るん?
いま月給手取りおいくら?
16: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:02:45.40 ID:3XOpx3Uva
>>12
安いよー
手取り15万くらい
だって個別指導塾のバイトだもん
4: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:00:51.90 ID:A7WzUNPQ0
なんの仕事してるの
9: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:01:59.74 ID:3XOpx3Uva
>>4
ハロワ→工場
今は
学習塾よ
14: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:02:39.70 ID:/bOTBjzdd
>>9
学歴あったんか
17: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:06.04 ID:3XOpx3Uva
>>14
地方の公立の大学卒
13: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:02:13.02 ID:O8jbaP+80
ワイも20代なまぽで30前に就職したで
22: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:51.27 ID:3XOpx3Uva
>>13
よお受け続けられたな
15: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:02:41.36 ID:5ZyyHR3X0
何歳?ワイの友人川崎で生活保護受けるわ言うて失踪したわ
19: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:22.12 ID:3XOpx3Uva
>>15
31歳よ
18: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:16.72 ID:bxpVGZsy0
学歴は?
20: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:33.92 ID:3XOpx3Uva
>>18
地方の公立大学卒
21: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:03:48.22 ID:mPAbd7sw0
生きてて楽しい?死にたくならないんか?
24: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:04:18.73 ID:3XOpx3Uva
>>21
死にたいなぁ
大学にもどって新卒カードもちの就活したかったわ
35: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:07:13.40 ID:YfDHd9LwM
ワイ特殊技能でなんとか生き残る��
37: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:07:28.82 ID:3XOpx3Uva
>>35
なんの技能よ
39: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:08:17.81 ID:YfDHd9LwM
>>37
パソコンの大先生からネットワーク屋さんから映像機器屋さんや��
38: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:07:30.90 ID:2hszo6El0
やろうと思えば生活保護のままで居続けられたの?
41: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:08:44.55 ID:3XOpx3Uva
>>38
いつづけられたと思う。
今の制度上、申告もれの不正受給
さえなければ怠惰が理由で
打ち切りはかなり難しいと思う
42: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:08:49.25 ID:rQbJeMg2a
働かなくても最低賃金と同じ額貰えるのにわざわざ最低賃金近い給料で働く意味とは
48: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:10:45.40 ID:3XOpx3Uva
>>42
シンプルに孤独に耐えられなくなった
たぶん今もナマポだったら
首吊ってた可能性が高い
想像してみるんや
小屋みたいなアパートに押し込まれ
1日中なんもせず
だれにも相手されず
ネットでコミュニケーションとっただけの気分
死にたくなるぞ
69: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:16:28.74 ID:2hszo6El0
>>48
それでも今やってるのはたぶんフルタイムの仕事やろ?
週2~3日くらいのバイトって選択も有ったわけやから偉いと思う
74: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:18:17.33 ID:3XOpx3Uva
>>69
塾のバイトは最初
フルタイムじゃなかったけど
やってるうちにフルタイムみたいになったパターン
46: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:10:30.56 ID:Xx+stTay0
4年もよく受けれたな
54: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:11:43.89 ID:3XOpx3Uva
>>46
鬱で逃げ切れてた
47: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:10:33.68 ID:osZh1kec0
なんで生活保護やったん?
51: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:11:00.71 ID:3XOpx3Uva
>>47
鬱で引きこもりから
53: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:11:28.12 ID:Xx+stTay0
生活保護なんて単身世代やと12万ももらえないし生活保護でいいなんて言ってるやつは世捨て人やで
61: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:12:32.85 ID:3XOpx3Uva
>>53
そやね
東京以外の地域ならほとんど
12万未満の金額しかもらえない
9万円台の地域もある
65: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:13:04.87 ID:V3mg0xVR0
実際どうせ負け組で底辺なら働くより生活保護で寝て暮らした方が遥かにいいに決まっとるよな
底辺で働いたところで収入なんかたかが知れてるし、何より底辺で嫌な思いしてヒイヒイ言いながら稼いだなけなしの金の一部が税金として徴収されて、
それが金持ちの生まれが多くてしかも将来たんまり金を稼ぐであろう旧帝大学とかの連中の優雅なキャンパスライフを支えてるとか思うとクッソ腹立ってくるしね
なんで自分のことを軽蔑してるガキどもの養分にならなあかんねん
そんなら生活保護貰って完全に国を養分として生きたほうが一億倍ええわな
68: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:14:26.62 ID:3XOpx3Uva
>>65
この理論も至極わかる
ワイもずっとそう思ってた
でも孤独に耐えきれなくなり
働きだした。
まあもしかしたらまたナマポに戻る可能性はあるかもしれん
71: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:16:57.01 ID:Alj/YtbEM
>>68
とにかく暇で気が狂うよな
60: 風吹けば名無し 2021/03/13(土) 03:12:23.70 ID:LoQCihXx0
まぁいつまでも税金の世話になってるよりはマシやな。がんばりぃ