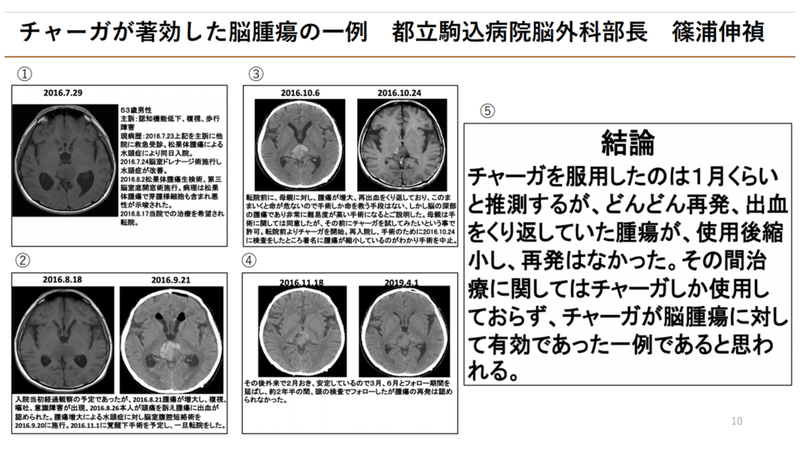1:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:11:10.83 ID:EqIlxAku0
3:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:12:14.52 ID:S5ZXDFUQ0すまん、もう税金払わんでもええか?
356:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:01:15.65 ID:vnnye1Qia>>3
はい逮捕
5:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:12:29.91 ID:SMGU2K/N0ほんとに終わりだよこの国
8:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:13:07.20 ID:Dl+Mt5zC0一部だろ?全体が悪いみたいに言うなよ
あと税金はしっかり納めろ
101:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:26:09.86 ID:NRkxs8Mfd>>8
一部しか発覚していない
が正しい
17:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:14:33.45 ID:8IpWNntrr税金に関わる人間が税をコケにしたら死刑でいいだろ
18:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:14:42.40 ID:2+Lgw/yt0こいつらが国民の税金は厳しく取り立ててるんやから草
21:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:16:08.31 ID:FqzXi9RT0舐め腐ってた
23:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:16:36.15 ID:STeIVHfV0こういう税金泥棒の話聞くたびに税金納めるの馬鹿馬鹿しくなるわまじで
26:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:17:17.42 ID:8VS0Waht0メディアや芸人は田口や遊覧船社長はクッソ叩くけど国税庁職員は叩かないよなあ
66:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:22:30.59 ID:b+SASMJD0>>26
結局特定の人物が叩ければ鬱憤ばらしが出来てスッキリするわけで、組織とか国ぐるみ的な特定人物で無い犯罪は叩こうにもスッキリせん
34:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:18:42.83 ID:3JmB1iyspなあこれどう責任とってくれんの?
4630万どころの話じゃないぞ
57:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:21:24.90 ID:CoBplxP4M「素行の悪さを指摘される職員ではなかった」
善人のふりして盗んでたってことやな
盗むために善人のふりしてたって方が適切か
72:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:23:15.81 ID:/l2SOdUh0邪悪すぎるわ
ガチクズ
86:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:24:49.49 ID:G9bxo14Q0派手にやったからばれただけで氷山の一角なんやろなあ
118:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:28:14.57 ID:fhwGyuCk0どうせ田口みたいにこの世の終わりのように怒涛の報道はされねぇだろうな
上に立つ連中は責任も取らないゴミみたいな連中なのに国民が率先して国民をいじめるシステム
国民を引っ張る気のない連中が責任のある立場とやらに居るんだから落ちぶれるわな負の連鎖で無理だなこりゃ
128:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:29:17.17 ID:4yqQJFG/M発展途上国レベルで公務員が腐り始めてるよな
131:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:29:51.55 ID:sGfV0IDkd政治家や公務員が腐りきってるもんな
そりゃ日本衰退するわ
139:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:31:19.76 ID:cMLwlQVp0やっぱ日本の権力構造デカすぎ&複雑すぎ問題どうにかせんとあかんわ
153:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:32:57.93 ID:VVhBymkX0こんなになるまで気づかれないシステムなのも悪い
213:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:38:47.81 ID:CoBplxP4Mまじで死刑でいいよ
現実的なところなら懲役10年とか
225:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:40:09.21 ID:higKSabiMこういうのって普通より刑罰重くなるようにならんとあかんよな
257:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:43:43.48 ID:ILpTRKaLa>>225
刑罰は法の平等性の観点から重くしたらアカン
税に関する資格の剥奪くらいやったら職務規定の範疇やからそこで裁かれたらええ
309:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:52:03.52 ID:uyKbkGOLr>>257
今後税金に対する詐欺は別途法律作って最低でも無期懲役にしたらええねん
233:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:40:44.75 ID:fOA+oi4f0今思い返せば自己責任論も国が責任を持たず傍若無人に振る舞いますよ宣言だったな
237:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:41:40.96 ID:WnmhhNVmM腐りきってんな
304:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:51:14.83 ID:50ycfo5p0めちゃくちゃガバガバなんやろ
317:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:53:30.94 ID:EtIRRf7b0金融系の詐欺したやつマジで終身刑にしたほうが良いわ金融系の犯罪しても箔が付くおかしな状態になってる
334:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:57:54.39 ID:EtIRRf7b0あとインサイダーの取り締まりマジで強化しろ株仮想通貨でインフルエンサーの発言による釣り上げ多すぎ
352:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:00:47.44 ID:ciqCy90MM>>334
あれ酷すぎだよな
簡単に株価操作できるやん
371:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:03:27.33 ID:qnEEKUPaa>>334
そんなん言い出したらタックスヘイブンとかのが問題やわ
401:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:09:14.00 ID:EtIRRf7b0>>371
タックスヘイブンも問題やけどインサイダーに関しては大量の被害者が出てるのがアカンわ
398:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:08:09.41 ID:X7EmrpLodクーデター起きないのは凄い
399:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 02:08:56.86 ID:m1KlYq2VM>>398
YouTubeやSNSに忙しくて国がやばいことを気付いてないからな
323:風吹けば名無し:2022/06/04(土) 01:55:19.70 ID:6dOd20Gq0ところで使途不明金はどうなったんですかね…