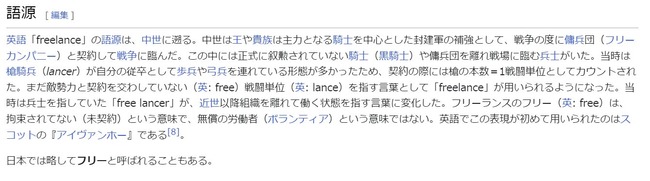4/14(日) 11:01配信
自宅で家族が亡くなった場合、警察に連絡すると事件性もないのに死因の調査や搬送、保管料で10万円も取られる……。このような内容がXに投稿されたところ、《悪質なデマ》《鵜呑みにしてはいけない》などと多くの批判に晒された。投稿は現在削除されている。
ところが、問題の投稿を巡り、《神奈川県警だけは話が別》《保管料の名目で賄賂をもらってた神奈川県警に当たった説》などの投稿が相次ぎ、神奈川県警で過去に発覚した”遺体の運搬を巡る収賄事件”を引き合いに、事実の可能性もあるとして話題になっている。
神奈川県警の収賄事件とは、’21年に知人の妻らが経営する葬儀会社を遺族に勧めた見返りに現金などを受け取ったとして、警部補らが逮捕された事件のこと。変死体を警察署などに搬送する際、全国で神奈川県警だけが公用車を使わず、慣例的に遺族が自ら葬儀会社に連絡し、数万~十数万円の搬送費用を負担していたという。
当時の「毎日新聞」の報道によると、神奈川県では公用車の稼働率が低く、遺族負担の慣例化を招き、県警と葬儀会社の癒着構造を維持する役割を果たした可能性があると指摘されていた。こうした事態を受け、神奈川県警は公用車を追加で購入し、全54署に配備すると報じられていた。
そこで神奈川県警に、遺体の運搬費用の遺族負担について聞いた。まずは警察が遺体を運搬するケースについて、一課の刑事は次のように解説する。
「一般論としてですが、お亡くなりになった方がいる場合、119番で救急車を呼ぶなどして、亡くなった原因がわかればお医者さんに死亡診断書を書いてもらえます。その場合、警察が関与することはまずないです。
しかし、例えば、ご自宅で亡くなった状態で時間が経っていてもう病院に運べる状態じゃないような場合は、警察が呼ばれることもあります。警察が取り扱うことになった場合、ご遺体にお怪我がないかなどもしっかり観察した上で、 発見者などいろんな人にお話を聞いて、事件性があるかないかを判断するために警察の施設にお運びします」
その上で、運搬、保管の費用については次のように話す。
「警察が神奈川県警の用意した公用車などでお運びする際に、お金を取ることはありません。捜査のために保管しておく間も、警察が保管料を取ることはありません。過去にうちの職員で不届き者がいたことは事実ですが、現在は54の全署で代用車含め専用の車が配備されているので、保管料や運搬料が取られることはありません。
そもそも、警察は一切お金を取りません。以前に神奈川県警で一般の会社に運搬をお願いしていたという状況はありましたが、現在はそうしたことはありません。ご遺族の方が知っている業者さんにどうしても依頼したいなどの希望があれば、そこにお金が生じることはあるかもしれませんが、今も昔も警察から請求がいくことは一切ありません」
なお、解剖にかかる費用については神奈川県警のWEBサイトによると《警察の判断により行う解剖に要する費用は、公費で負担されます。医師の判断によりご遺族の承諾を得て行う解剖に要する費用は、ご遺族の負担となります》と記されている。
躊躇わず、必要な機関に通報しよう。