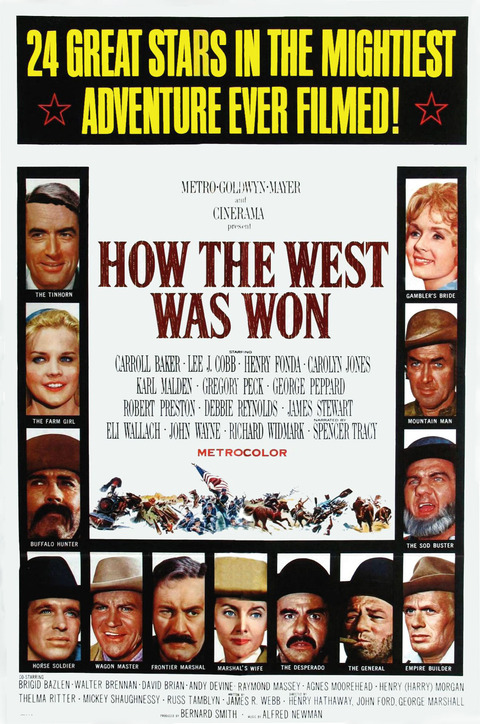新生活狙いなのか何かしらないけれど、本当にこのナンバーからの営業電話が最近増えたなと思うお。
あと050系IP電話からの営業電話も。
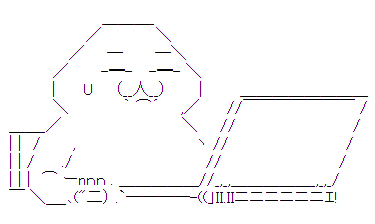

青天を行く白雲のごとき浮遊思考の落書き帳
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
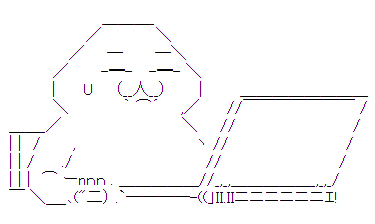
日々の生活で頻繁に使用する手は、他の部位に比べて特に過酷な環境にさらされやすく、その結果としてしわしわした状態になりがちです。
手や指にシワができる原因にはさまざまな要素が絡んでいます。
それぞれの要因に応じて適切なケアを行えば、より柔らかく健康的な手を手に入れることができます。
ここでは、手や指にシワができる主な原因を詳しく解説していきます。
加齢は、手や指のしわの形成に深く関わっています。
年齢を重ねるにつれて、皮膚の構造を支えるコラーゲンやエラスチンといった重要な成分が体内で減少し、肌の弾力やハリが失われていきます。
この結果、手元にしわが増え、目立つようになることがあります。加齢による変化を少しでも和らげるためには、日頃から保湿力の高いクリームを使うことや、手袋を活用することで手を優しく守ることが推奨されます。そして、このような日常のケアを欠かさないことが大切です。
乾燥は手のしわの形成を引き起こす大きな要因の一つです。特に寒い季節には空気が乾燥しやすく、肌の水分が失われやすくなります。この結果、肌の表面が硬くなり、しわが目立ちます。乾燥による影響を避けるためには、保湿は欠かせません。
手を洗った後や乾燥しやすい時期には、しっかりとクリームで保湿を心がけることが重要です。
手は普段から紫外線にさらされており、知らず知らずのうちにダメージを受け続けています。紫外線はコラーゲンを破壊し、皮膚の弾力を奪います。このため、十分なUVケアを怠ると、手のしわが増えてしまうことがあります。日焼け止めをこまめに塗る習慣や、日差しが強い時には手袋を活用することが効果的です。
不規則な食生活や乱れた生活習慣も、手のしわの原因となります。栄養が偏ることや、睡眠が不足すること、ストレスがたまることは、肌の状態に直結します。こうした影響を防ぐためには、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動が重要です。
これにより、皮膚の新陳代謝が促進され、手の健康が維持しやすくなります。健康的なライフスタイルの維持が、しわしわした手から卒業するための鍵となります。
日々の手入れと生活習慣の改善で、しわしわのない健やかな手を目指していきましょう。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/21 06:18 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
現在、削除の方針に従って、この項目の一部の版または全体を削除することが審議されています。 削除についての議論は、削除依頼の依頼サブページで行われています。削除の議論中はこのお知らせを除去しないでください。 この項目の執筆者の方々へ: まだ削除は行われていません。削除に対する議論に参加し、削除の方針に該当するかどうか検討してください。また、本項目を既に編集されていた方は、自身の編集した記述内容を念のために控えておいてください。 |
全文が確認できる公になった最古の出典は江戸時代、延宝7年の先代旧事本紀大成経にあり、全文漢字による表記がなされている。
他に各地の神社において神璽や守符、奉納文などに用いられている文字である阿比留草文字での伝承があるとされる。[1]
大成経とは別書の、ひふみ十音の記述が見られるものに先代旧事本紀がある。本書は江戸時代の国学者らに偽書と断定された。しかし先代旧事本紀は成立は平安以前までさかのぼれる。先代旧事本紀
また秋田物部文書を継承する唐松神社には、古来は大祓詞を中臣氏が奏上し、天津祝詞の太祝詞の部分を物部氏がひふみ祝詞を奏上したとする伝承がある。[2]。 また島根の物部神社、奈良の石上神宮でもひふみ祝詞が古くから奏上される。同社に伝えられる鎮魂法とともに物部氏の伝えた十種神宝の伝承と深く関係する祝詞と思われる。
画家で大本教信徒であった岡本天明が神がかりによる自動書記で書き上げたとされる予言書。本書でひふみ祝詞が重要視され、近年政治関係者が取り入れたり子供向けテレビ番組で取り上げられた事により、一部からひふみ祝詞そのものが批判されている問題である。 しかしひふみ祝詞自体は古くからあり、ひふみ十音や「ももち、よろず」などの文言は能のセリフなどにも古くから伝わって伝承されている。寿式三番叟 歌詞 同書はひふみ祝詞を3、5、7に区切りながら読むなど、独自の解釈を加えている。また日月神示の内容については後に岡本天明が「一部嘘を書いた。」と証言したとされている。
「ひふみよいむなやこともちろらねしきるゆいつわぬそをたはくめか うおえにさりへてのますあせへほれけ」
古来からの伝承では一息で言い切れるようになるのが本義とされる。息を継ぐ場合は「そをたはくめか」で区切るとされている。(石上神宮で行われる鎮魂法において使われるひふみ祝詞の用い方による。)神道行法・鎮魂2