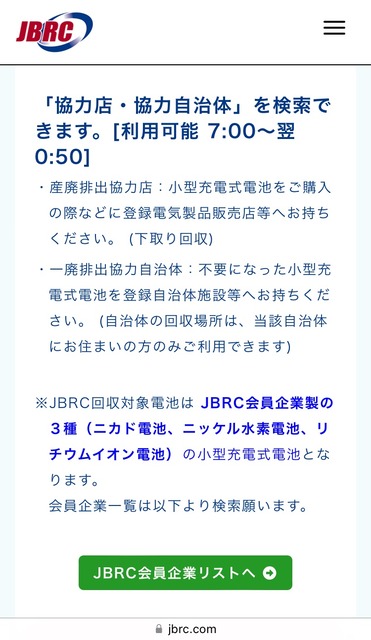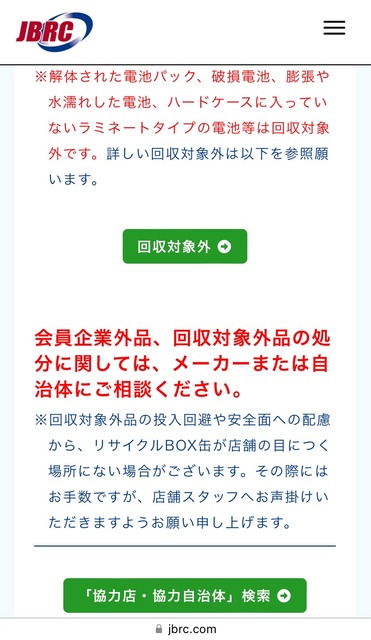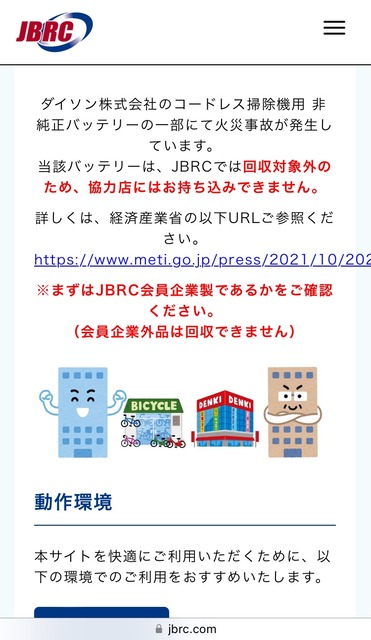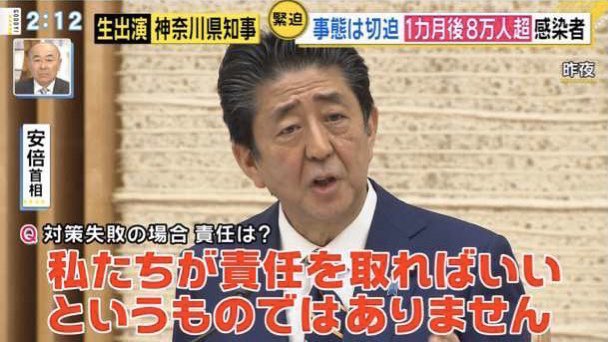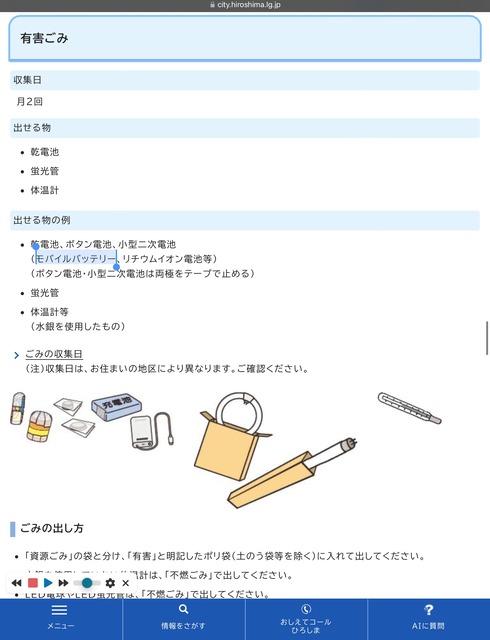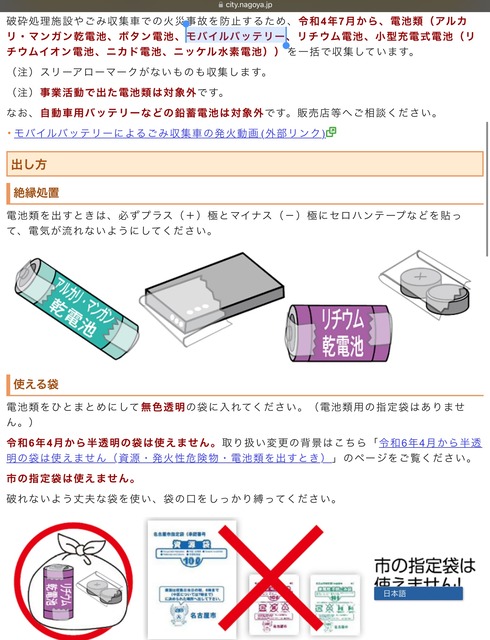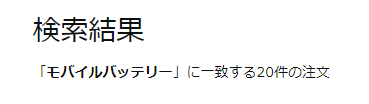67:名無し :2025/03/26(水) 22:18:29.358ID:yJwwNE6AW
モバイルバッテリーの捨て方を自治体のサイトで調べた結果wwwwwwwwww
自治体「JBRCのサイトで調べろ」
JBRC「破損や膨張したもの、会員企業外の製品は回収対象外だからメーカーや自治体に相談しろ」

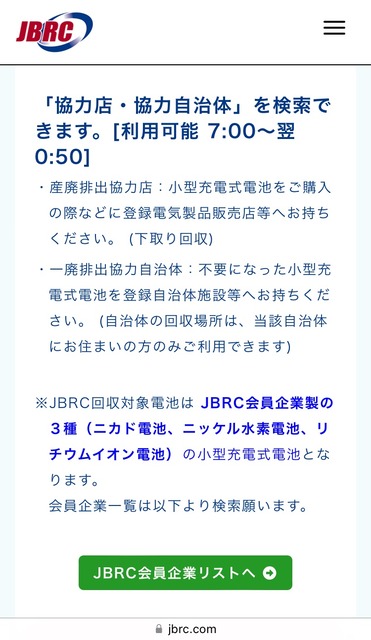
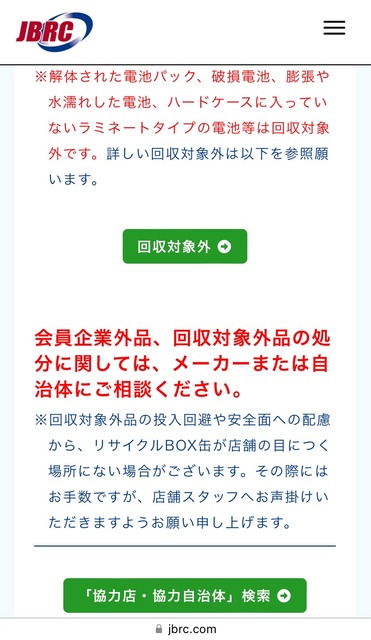
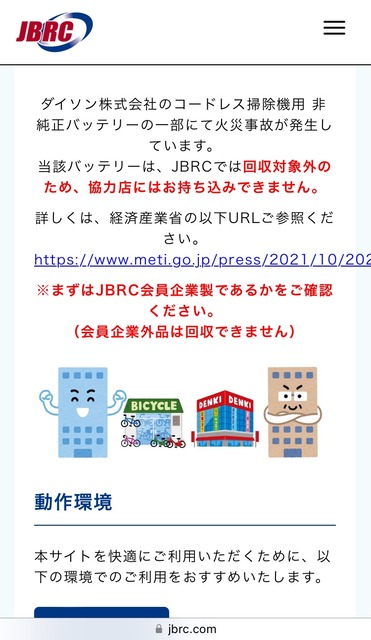
ええんか、、、???
75:名無し :2025/03/26(水) 22:19:16.573ID:1FXwly6wo
>>67
なんやねん相談ってアホかよ
79:名無し :2025/03/26(水) 22:19:34.829ID:/4xiOHeam
>>67
そら燃えるごみに捨てられますわ
責任逃れの馬鹿な大人ばっかりで
こんな世の中どうなってもいいってなる
85:名無し :2025/03/26(水) 22:20:40.798ID:ReJPaVZxM
>>67
もうこれ販売禁止にするか製品全部に個体識別番号で紐付けてライセンス製にするしかないやろ
92:名無し :2025/03/26(水) 22:21:22.785ID:ReFekmLS6
>>67
ワイんとこは回収やってたわ
膨張したやつ引き取らないとは書いてなかったし超優秀やわ
161:名無し :2025/03/26(水) 22:32:36.466ID:tfBgjs0SZ
>>67
もう神頼みしかないじゃん…
197:名無し :2025/03/26(水) 22:46:40.436ID:HOGIb04eU
>>67
メーカーや販売店「うちでは対象外なので自治体や相談してください」
230:名無し :2025/03/26(水) 22:59:28.212ID:75chi30CA
>>67
誰も責任取らない国
267:名無し :2025/03/26(水) 23:18:29.085ID:BkcmgBU3z
>>67
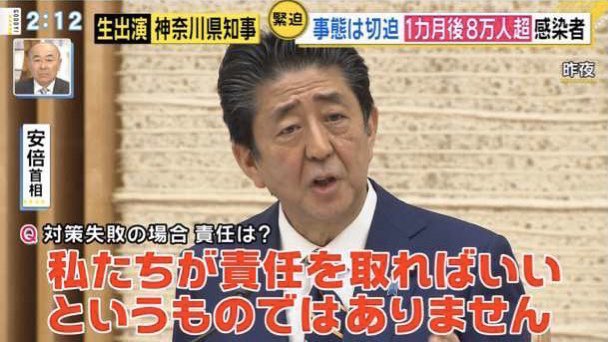
359:名無し :2025/03/27(木) 00:14:07.300ID:lmlhc3R.t
>>67
こんな態度じゃそら燃えるゴミに出されても仕方ねーわ
71:名無し :2025/03/26(水) 22:18:47.127ID:plQB0GnuL
メルカリで売れるから出してるわ
膨らむ前くらいに
72:名無し :2025/03/26(水) 22:18:59.028ID:PHGI/nKzy
回収ボックスに入れたらどう考えても落下衝撃音が聞こえたんやけどこれ発火のリスク上げまくりの回収方法やろ・・・
74:名無し :2025/03/26(水) 22:19:07.395ID:QTA.Pw9ZE
“不燃ごみ収集”の日作ってる自治体って神やな
76:名無し :2025/03/26(水) 22:19:27.950ID:B99uhq5GH
>>1
膨らんだモバイルバッテリーの処分方法
Ankerは自社製品だけ、CIOは他社製品も回収してる
ちなAnkerストアだと300円のクーポンが貰える
Ankerの「充電器回収サービス」を使ってみた | ROOMIE(ルーミー)
https://www.roomie.jp/2024/09/1312988/
89:名無し :2025/03/26(水) 22:21:12.470ID:ZKCW7jUfr
>>76
Ankerってマジで有能やなぁ
371:名無し :2025/03/27(木) 00:23:10.609ID:Dgo9yXqEj
>>76
Ankerさまさまやなあ
81:名無し :2025/03/26(水) 22:20:17.144ID:UTu3C0cM4
家電量販店に持ち込めばええだけ
82:名無し :2025/03/26(水) 22:20:26.026ID:0sdmPvU85
持ち歩くものやからなぁ
"うっかり"電車とかに置き忘れてもしゃーないかもなぁ…
98:名無し :2025/03/26(水) 22:21:51.084ID:o5EeOQtYA
ワイんとこ乾電池と一緒に捨ててええらしくて安心したわ
118:名無し :2025/03/26(水) 22:25:03.950ID:sCTEFcLYt
じゃあどうやって捨てればいいの定期
いい加減なんとかしろよ
125:名無し :2025/03/26(水) 22:26:20.777ID:qAV4pQAeU
>>118
真下に落石できるような仕掛けを作って30Mくらい離れてから落石させて発火させるのはアリだと思う
123:名無し :2025/03/26(水) 22:25:50.716ID:iIylGjG6H
ルール上問題ない行為
134:名無し :2025/03/26(水) 22:28:36.303ID:FGLwwBawH
車みたいに購入時に廃棄費用負担する形にしろよ
要件満たさないバッテリーは日本に入れるな
140:名無し :2025/03/26(水) 22:29:22.404ID:KT1It1Vvc
>>134
まあそれで良いよな
元々安いし200円くらいなら乗っかっても問題無い
147:名無し :2025/03/26(水) 22:30:01.488ID:er25XznBP
>>134
ほんまそれ
あと認証がないやつは販売禁止でええわ
中華モババとか飛行機の中で爆発してもおかしくないし
188:名無し :2025/03/26(水) 22:43:09.370ID:vQV.gMbfX
でも最近は火災事件が報じられるようになって、普通にゴミ出しで回収してくれる自治体も増えてるで
広島市
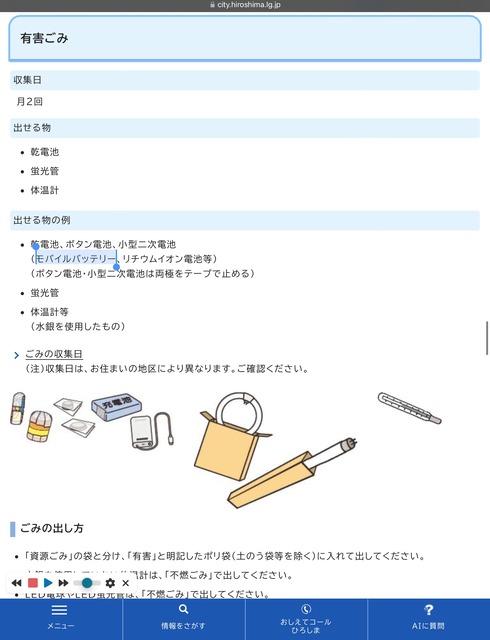
名古屋市
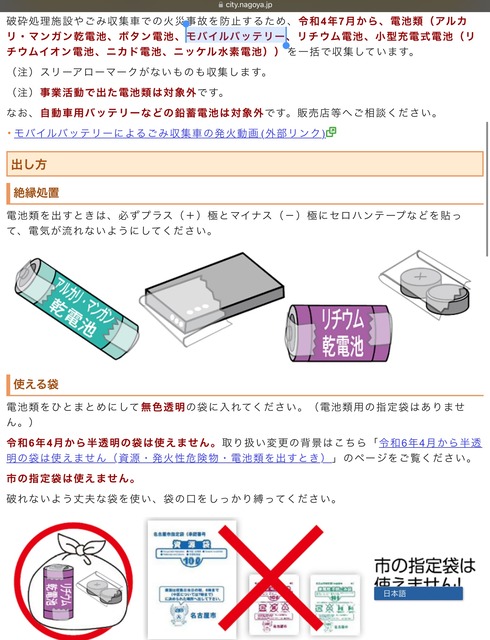
192:名無し :2025/03/26(水) 22:44:05.518ID:skiRu5Gxi
>>188
有能市やん
市長か環境局の職員が有能オブ有能
233:名無し :2025/03/26(水) 22:59:58.752ID:75chi30CA
>>188
市町村区ガチャやん
247:名無し :2025/03/26(水) 23:05:36.754ID:rBHPlh9kQ
結構買ってたわ
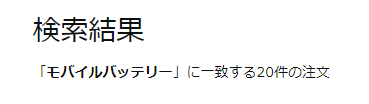
248:名無し :2025/03/26(水) 23:05:58.824ID:ttTAbyncE
スロットで負けてイライラしてうっかりパチ屋に忘れてしまう
252:名無し :2025/03/26(水) 23:08:24.696ID:rBHPlh9kQ
國がちゃんと法整備して回収するシステム作らんと
259:名無し :2025/03/26(水) 23:12:48.896ID:P847OlKnn
燃えるゴミは半分犯罪だろ
288:名無し :2025/03/26(水) 23:28:45.519ID:4E9hbSgdo
お前らのライフハック浸透してきたな
290:名無し :2025/03/26(水) 23:30:27.846ID:s0sJ1DDRE
うっかり空港で没収されるの一番すき
289:名無し :2025/03/26(水) 23:30:14.043ID:4E.mFWKru
100円ショップでどう考えても引き取ってもらえるか怪しいレベルの売ってるの社会問題よ