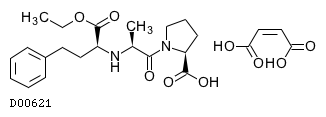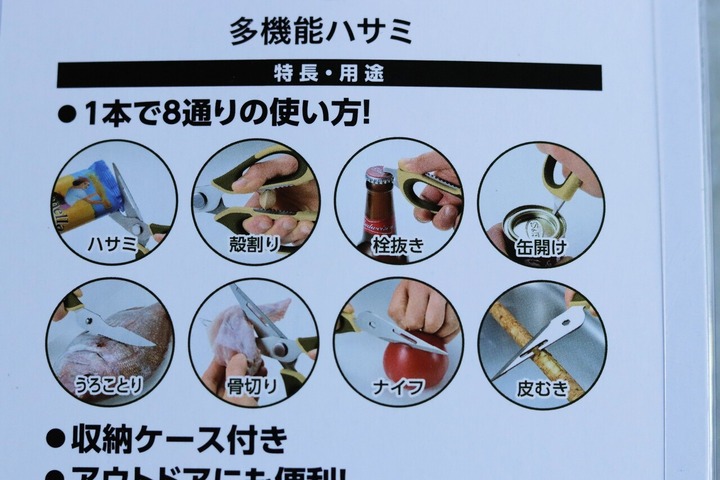「阿修羅」所載のあっしら氏の投稿だが、倫理学の問題として面白いので転載する。
この問題へのあっしら氏自身の回答も載せておくが、いまひとつ論理が分からない。まあ、私がいい加減な読み方をしているのだろうが、福岡登山隊の行為を肯定しながら、日本がそうでない社会(人を助ける社会)であってほしいというのは、ストレートにつながらないだろう。もし言うなら、「法的には無罪だが、人道的には有罪」と明確な説明をすべきだと思う。
(引用1)
96年福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為をどう評価します?
http://www.asyura2.com/0403/dispute17/msg/410.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 28 日 18:38:30:Mo7ApAlflbQ6s
真相ハンターKさんとのやり取りのなかで、「イラク邦人3名人質事件」の家族の言動を、内容ではなく言動そのものに対し非難(罵倒)した人たちを「カス」と呼びました。
かすかな記憶したなかった話でしたが、現在読んでいる『私物化される世界』のなかに、96年福岡チョモランマ登山隊がチョモランマ(エベレスト)北壁ルートで登頂に挑んだときに起きた「見殺し」行為が取り上げられていました。
(『私物化される世界』(阪急コミュニケーションズ:ジャン・シグレール著:渡辺一男訳:本体2800円)は読了後に推奨書籍として紹介したいと思っている)
福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為は後に国際的な論争を引き起こしましたが、是非のいずれでもあっても「カス」と言うことはできない価値観に基づく選択の問題だと思っています。
多くの方に、福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為は是か非か、そう選択した理由を投稿していただければと思っています。
ワガママで恐縮ですが、持論は保留にさせていただきます。
福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為に関する事実情報や議論情報をお持ちの方はそれも紹介していただければと思います。
【福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為の概要1】
『私物化される世界』が取り上げた「見殺し」行為の内容を転載する。
P.90~91
「 一九九六年五月十一日の明け方、二人の日本人登山家と三人のシェルパがエヴェレスト北壁の岩棚の下にかろうじて設営されたキャンプを後にした。彼らは高度八三〇〇メートルに達していた。彼らの目的は、北壁経由でエヴェレストの頂上(八八四八メートル)に立つことだった。五四八メートルの高度差と一五〇〇メートルの距離を克服するのに、下山も含めて最大で九時間と見積もられていた。それはぎりぎりの計算に基づいていた。
生還しようと思えば、暗くならないうちにふたたび第三キャンプに戻らなければならない。条件はひどくきびしい。嵐が起きた。全員が登攀にとりかかった。高度八五〇〇メートルの絶壁の上に岩鼻が張り出している。その雪の中、登攀ルートのすぐ数センチ脇に、一人のインド人登山家が倒れているのに一行は気づいた。負傷し、力は萎えて、すでに半ば凍死しかかっていた。しかし、彼はまだ話すことはできた。二人の日本人は立ち止まることなく、登攀を続けた。午前も遅くなって、高度八六三〇メートルの地点で一行はいったん停止した。垂直に切り立った壁、水に覆われた三〇メートルの高さの岩が阻んでいる。そこで彼らは酸素ボンベを交換し、少し食物を摂った。
ふと右手に目をやった日本人の一人は、そこにさらに二人のインド人を発見する。一人は横たわっていて、死んでいた。もう一人は雪の上にしゃがみこんでいる。生きている。
日本隊は登攀を続けた。メンバーのうち誰もその生存者に食べ物や酸素を与えなかった。言葉は交わされなかった。ただ視線だけが交わされた。
三時間半後、五人の登攀者は超人的な努力の末にエヴェレストの頂上に達した。
谷へ戻ってから、ネパール人シェルパは語っている。彼らはショックを受けた。高山への探検では、公海上の船長がそうであるように、リーダーに決定権がある。他の者たちは指示に従う。しかし、シェルパたちは置き去りにされたインド人のすがるような眼差しを忘れることができなかった。
インドと日本で議論の応酬があった。新聞はこの事件を大見出しで報じ、インドでも日本でも日本の登山家たちの行動がきびしく批判された。
このような事情を受けて、二人の日本人登山家は弁明のために記者会見を開いた。探検のスポークスマン、二十一歳の重川英介はこう説明する。「私たちは自力で頂上に登るのです。登攀のためにあらゆる努力を傾けます。疲労困憊していて、助けることができなかった。八〇〇〇メートルのかなたでモラルを発揮することは不可能です」」
【福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為の概要2】
1996年平成8年5月11日、福岡チョモランマ登山隊(隊長:矢田康史)の花田博志と重川英介、シェルパ3名が、チョモランマ(エベレスト、8848m)に登頂(インド・チベット国境警察隊を救助しなかったため、その後、論争となる)
http://www.ameame.com/dic/dic-his/his-06.HTM
(引用2)
私の見解http://www.asyura2.com/0403/dispute17/msg/507.html投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 30 日 17:21:19:Mo7ApAlflbQ6s
(回答先: 96年福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為をどう評価します? 投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 28 日 18:38:30)
皆さん、レスありがとうございます。
個々にレスを付けたい(付けるべき)という思いもありますが、ここでのお礼で代えさせていただきます。
(皆さんのお考えを読ませていただき、ほっとすると同時に暖かい気持ちになりました)
このケースを『私物化される世界』で取り上げた著者ジャン・シグレールさんの意図は後ほど引用させていただきます。
その前に私の見解を書き込みさせていただきます。
============================================================================================
スレッドの書き込みで「福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為は後に国際的な論争を引き起こしましたが、是非のいずれでもあっても「カス」と言うことはできない価値観に基づく選択の問題だと思っています」と書いたように、このケースをどう評価するかはとても難しいと思っている。
結論:福岡チョモランマ登山隊の「見殺し」行為は是認できる。
理由:チョモランマ北壁ルート登頂という、膨大な準備をかけ命賭けで挑んだ行為の真っ只中で遭遇した出来事であり、遭難していたインド人も同じ立場の登山家たちだと見て「見殺し」したとしても倫理的に法的にも誤りではないと考えるからである。
(遭難者がインド・チベット国境警察隊に属しているとはわからなかっただろうし、わかったとしても登頂をめざす登山家としてそこにいると思うのは自然だ。そして、遭難者がインド・チベット国境警察隊に属しているとわかった上での経緯ても結論は変わらない)
重川英介さんと花田博志さんは、ベースキャンプ周辺や日本で危難に陥っている人に遭遇したら、日頃鍛えた体力と知力を駆使して、他の人なら尻ごみするかもしれないケースでも助けようとする人たちなのかもしれない。
重川英介さんと花田博志さんは、自分たちが「見殺し」にしたインド人たちと立場が逆になったとしても、救ってもらえたらうれしいとすがる気持ちを持つとしても、「見殺し」されたからといって非難したり怨んだりすることはないはずである。
もちろん、インド人たちを実際に救出できたかどうかは別として、チョモランマ登頂を断念し、酸素ボンベの中身や食べ物を遭難者たちと分かち合い遭難者たちの体力が回復する道を選択することはできる。
(自分たちが帰還できる条件を確保した上で分け与えても遭難者たちが可能な助力を得ても下山できないことがわかったら、そこで「見殺し」にすることはやむをえないというより、そうすべきだと思う)
しかし、難関とされる世界最高峰チョモランマの北壁ルート登頂を目的とした事業に挑んでいる人達にそれを求めるのは、経営者(資本家)に競争関係にある他の会社の危難を救えと言うに等しい筋違いの要求だと思える。
(このケースで日本人登山家を倫理で非難するのなら、企業が、生き残りを賭けて競争を続け、他の企業の破綻に喜ばないとしても知らぬ顔をしている“日常”も非難しなければ筋が通らないことになる)
登山家は、頂上近くで遭難者に出会ったことで断念するくらいなら、端からチョモランマ北壁ルート登頂に目指さないように思える。
(キャリア志向なのかキャリアに価値を感じないかという違いで、世の中の見え方や出来事に対する感じ方が違うということをイメージしてもらってもいい)
このケースは、日本人登山家をサポートしたネパール人シェルパと日本人登山家の価値観の違いを際立たせているとも思う。
シェルパは、難関を克服する満足感や最高峰を極める喜び、そして、それらで得られる名誉とはほぼ無縁で、お金を稼ぐ目的=仕事として同行していたはずだ。すでに何度か北壁ルートでの登頂も経験しているだろう(名誉を得られる登山家よりも重い荷をかついで..)。
言いかえれば、自分や家族が生きるために高度8500メートルまで登ってきた人たちだ。だから、生きようとしている人として、「置き去りにされたインド人のすがるような眼差しを忘れることができなかった」し、置き去りにした日本人登山家を“告発”もしたのだろう。
日本政府は、「イラク3邦人人質事件」で、「テロには屈しない」という政治的価値観を尊重して3人を実質的に見殺しにした。
そのような政府の態度に抗して、人質の家族は「自衛隊の撤退も考慮しろ」と政府に訴えた。それを、“家族のとんでもない言動”として非難したり罵倒する人もいた。
私は、「テロに屈しても、人質を助けるためには...」という人も「テロに屈するべきではない」という人もカスだとは思わない。しかし、「テロに屈しても、人質を助けるためには...」という家族を、そのような言動をしたからといってバッシングしたひとはカスだと思っている。
そして、「テロに屈しない」はいいとしても、その裏で可能な人質解放策を講じなかったとしか思えないのみならず、人質家族バッシングを誘導した日本政府=小泉政権=連立与党の連中は最大のカスだと断ずる。
私は端からチョモラマン登頂をめざさない人間だが、社会が、「インド人たちを実際に救出できたかどうかは別として、チョモランマ登頂を断念し、酸素ボンベの中身や食べ物を遭難者たちと分かち合い遭難者たちの体力が回復する道を選択する」ものであってほしいと思っている。
おいそれとはそうできないたいへんなことだとはよくわかっているつもりだが、どうしてもチョモラマン北壁ルート登頂を達成したのならチャレンジし直せばいいじゃないかと思うし、それに価値を認める人が多いのなら断念した登山家たち人がチャレンジし直せるような世界であって欲しいと思っている。