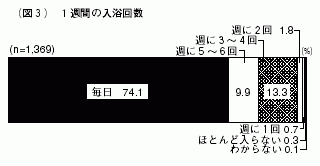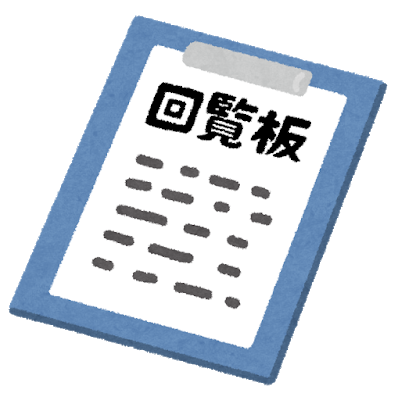
1 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:11:17 ID:1qo
家まで来てなんかよくわからん年会費?見たいのを払えって来るんや
平日なんて大学で参加出来んし休日にそんなの行きたくない
だから断ってんだが町内会に入ってその年会費とやらを払うのは必須だ言うねん
もちろんそんなの払う法的根拠無いから無視してるんやが2日に1回くらい来る
若いから甘く見られてるんかな?
これくらいで警察とかは迷惑よな?
2 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:11:48 ID:yoL
田舎なん?
5 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:33 ID:1qo
>>2
東京の辺境の方
4 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:16 ID:7Df
ホラー映画になりそう
8 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:50 ID:LOY
警察に行ってええで
不審者が来るって言え
13 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:19 ID:ECW
>>8
ルール上はそうやな
10 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:58 ID:oyO
一軒家とかで状況かわるからな
ゴミとか出してると町会費でまかなってたりするしな
11 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:13 ID:YsB
ゴミ置き場とか使ってるか?
17 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:43 ID:1qo
いやちっこいアパートだから一軒家ではない
でもゴミはそのアパート専用のとこ使ってる
19 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:14:11 ID:YsB
>>17
それやったら払う根拠はないな
通報
21 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:14:27 ID:NQo
>>17
アパートの大家に聞いたら?
68 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:20:24 ID:I2o
>>61
町内会費=飲み会費みたいなとこもあるし
一概にはいえんのちゃうか?
極端やけど横領してた案件もあったような
71 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:20:56 ID:YsB
というか町内会入るメリットはあるんか?
79 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:21:46 ID:UQw
>>71
ほとんどない
活動してるかも怪しい
82 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:22:11 ID:87g
賃料に町会費含まれてなかったっけ?
大家さんに聞いてみたら?
85 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:22:24 ID:1qo
>>82
今大家さんにLINEした
141 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:29:47 ID:YsB
700円でどんなサービスが受けられるん?
144 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:30:13 ID:1qo
>>141
言ってくれない
「払うもんなんだ」としか
236 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:46:46 ID:87g
何をしている団体や?
244 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:48:41 ID:pLu
>>236
近所の神社で祭りがある時に神輿を練り回してる印象しかないな
242 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:47:52 ID:QAG
自治会あるところは必ず自治会館なる小屋があるけど
イッチの所にもなんかそういうのあるんじゃ
245 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:49:18 ID:1qo
>>242
なんか1人のジジイの家が活動拠点らしい
248 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:49:39 ID:YsB
>>245
えぇ…
250 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:50:05 ID:pMc
>>245
なんか怪しいな
そこ本当に町内会なんか?
252 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:50:56 ID:gQL
>>245
それ多分本当にただの「ジジババの集まり」を町内会とかほざいてるだけやで
277 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:55:52 ID:1qo
大家以外から返信きたわ
1人除いて入居者全員払ってないわ
夫婦もいるのに変わった人たちや
278 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:55:54 ID:a4v
ワイ東京生まれ東京育ち
田舎のしきたり怖い
284 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:56:35 ID:6Sw
他の住居者の対処法も参考にしたいわね
328 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:05:28 ID:1qo
やったー!!!!!!!
大家さんからLINEきた
「何もしないで1人の家に集まってる老いぼれの集まりだから払う義務ないし無視していいよ」やって
名ばかりのただの老いぼれ集団らしい
しつこいようなら僕が介入します
とも言ってくれた
332 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:05:56 ID:z5m
>>328
サンキュー大家
339 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:41 ID:a4v
>>328
ええやつやん
342 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:51 ID:pMc
>>328
サンキュー大家
しっかりした人が大家で良かったな
345 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:07:06 ID:pLu
>>328
大家さん町内会をけちょんけちょんにこき下ろしてて草
まあよかったな
大家さんええ人やんけ
333 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:11 ID:gQL
これは良い大家
良いなぁ…
336 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:23 ID:6Sw
大家カッケェー
337 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:34 ID:VsE
大家とライン交換してる間柄に草
338 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:38 ID:1qo
あかん元々好きやったのにさらに惚れそうやわ
341 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:51 ID:gQL
>>338
…?女なんか?
343 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:07:02 ID:1qo
>>341
いや男やぞ
356 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:09:09 ID:J1t
一件落着そうでよかったわ
379 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:25:57 ID:1qo
みんなありがとな
無事解決しそうやわ
持つべきものはやっぱりおんJやな
田舎なん?
5 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:33 ID:1qo
>>2
東京の辺境の方
4 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:16 ID:7Df
ホラー映画になりそう
8 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:50 ID:LOY
警察に行ってええで
不審者が来るって言え
13 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:19 ID:ECW
>>8
ルール上はそうやな
10 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:12:58 ID:oyO
一軒家とかで状況かわるからな
ゴミとか出してると町会費でまかなってたりするしな
11 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:13 ID:YsB
ゴミ置き場とか使ってるか?
17 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:13:43 ID:1qo
いやちっこいアパートだから一軒家ではない
でもゴミはそのアパート専用のとこ使ってる
19 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:14:11 ID:YsB
>>17
それやったら払う根拠はないな
通報
21 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:14:27 ID:NQo
>>17
アパートの大家に聞いたら?
68 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:20:24 ID:I2o
>>61
町内会費=飲み会費みたいなとこもあるし
一概にはいえんのちゃうか?
極端やけど横領してた案件もあったような
71 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:20:56 ID:YsB
というか町内会入るメリットはあるんか?
79 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:21:46 ID:UQw
>>71
ほとんどない
活動してるかも怪しい
82 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:22:11 ID:87g
賃料に町会費含まれてなかったっけ?
大家さんに聞いてみたら?
85 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:22:24 ID:1qo
>>82
今大家さんにLINEした
141 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:29:47 ID:YsB
700円でどんなサービスが受けられるん?
144 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:30:13 ID:1qo
>>141
言ってくれない
「払うもんなんだ」としか
236 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:46:46 ID:87g
何をしている団体や?
244 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:48:41 ID:pLu
>>236
近所の神社で祭りがある時に神輿を練り回してる印象しかないな
242 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:47:52 ID:QAG
自治会あるところは必ず自治会館なる小屋があるけど
イッチの所にもなんかそういうのあるんじゃ
245 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:49:18 ID:1qo
>>242
なんか1人のジジイの家が活動拠点らしい
248 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:49:39 ID:YsB
>>245
えぇ…
250 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:50:05 ID:pMc
>>245
なんか怪しいな
そこ本当に町内会なんか?
252 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:50:56 ID:gQL
>>245
それ多分本当にただの「ジジババの集まり」を町内会とかほざいてるだけやで
277 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:55:52 ID:1qo
大家以外から返信きたわ
1人除いて入居者全員払ってないわ
夫婦もいるのに変わった人たちや
278 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:55:54 ID:a4v
ワイ東京生まれ東京育ち
田舎のしきたり怖い
284 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)10:56:35 ID:6Sw
他の住居者の対処法も参考にしたいわね
328 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:05:28 ID:1qo
やったー!!!!!!!
大家さんからLINEきた
「何もしないで1人の家に集まってる老いぼれの集まりだから払う義務ないし無視していいよ」やって
名ばかりのただの老いぼれ集団らしい
しつこいようなら僕が介入します
とも言ってくれた
332 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:05:56 ID:z5m
>>328
サンキュー大家
339 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:41 ID:a4v
>>328
ええやつやん
342 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:51 ID:pMc
>>328
サンキュー大家
しっかりした人が大家で良かったな
345 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:07:06 ID:pLu
>>328
大家さん町内会をけちょんけちょんにこき下ろしてて草
まあよかったな
大家さんええ人やんけ
333 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:11 ID:gQL
これは良い大家
良いなぁ…
336 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:23 ID:6Sw
大家カッケェー
337 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:34 ID:VsE
大家とライン交換してる間柄に草
338 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:38 ID:1qo
あかん元々好きやったのにさらに惚れそうやわ
341 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:06:51 ID:gQL
>>338
…?女なんか?
343 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:07:02 ID:1qo
>>341
いや男やぞ
356 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:09:09 ID:J1t
一件落着そうでよかったわ
379 :名無しさん@おーぷん:2020/09/08(火)11:25:57 ID:1qo
みんなありがとな
無事解決しそうやわ
持つべきものはやっぱりおんJやな